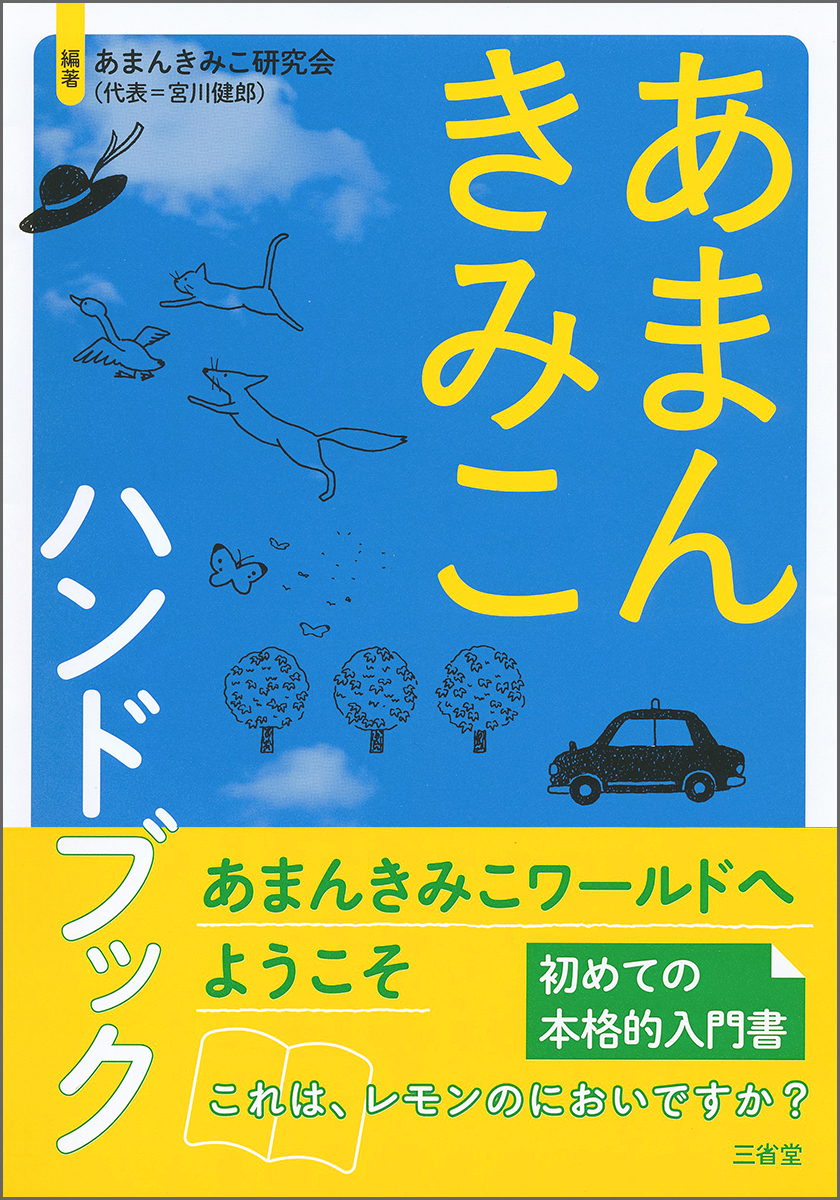
あまんきみこに関する初めての本格的入門書。40名の研究者・実践者が、作家・作品・教材について論じるだけでなく、キーワードから作品を横断的に読み解く。作品研究にも教材研究にも必携の一冊。
本研究会は、2016 年2 月に「あまんきみこに関する研究を推進し、その発展普及を図ること」を目的に設立されました。現在、年2回の研究会の開催と会報(年刊)の発行を主な活動として行っています。
〈代表・宮川健郎〉
1955 年、東京生まれ。現在、大阪国際児童文学振興財団理事長、武蔵野大学名誉教授。『国語教育と現代児童文学のあいだ』(日本書籍1993 年)、『現代児童文学の語るもの』(NHK ブックス1996 年)、『あまんきみこセレクション』①~⑤(共編三省堂2009年)など著書編著多数。
●はじめに
●執筆者一覧
●目次
●凡例
I章 あまんきみこの人と作品
1 人と作品
2 教科書に載ったあまん作品
寄稿 あまんきみこさんの叱り方 矢崎節夫
II章 あまんきみこの作品を読む
1 シリーズを読む
《松井さん》を読む
《ふうた》を読む
《えっちゃん》を読む
2 一つずつ読む
「白いぼうし」
「おにたのぼうし」
「雲」
「きつねみちは天のみち」
「天の町やなぎ通り」
「きつねの写真」
「口笛をふく子」
「おはじきの木」
「北風を見た子」
「くもんこの話」
「カーテン売りがやってきた」
「すずかけ写真館」
「ちいちゃんのかげおく」
「もうひとつの空」
「きつねのお客さま」
「海うさぎのきた日」
「夕日のしずく」
「青葉の笛」
「鳥よめ」
[寄稿]作品は作者のこころから 黒井 健
III章 キーワードからみるあまんきみこの 作品
雨/雪
色
歌
海
お母さん
開発
きつね
公園
戦争
空
月
時
友達
名前
ねこ/山ねこ
野原/林
乗り物
ピアノ
ぼうし
夢
[寄稿]あまんきみこさん 富安陽子
IV章 あまんきみこの周辺から
絵本
オノマトペ
書きかえ
紙芝居
声
授業
初期作品
同時代作家
びわの実学校
ファンタジー
満州
宮沢賢治
[寄稿]きつねのかみさま 松永 緑
V章 あまんきみこをもっと知る
1 研究への手引き
A テキスト
B 読書案内
2 年譜
3 あまんきみこ著作目録
・刊行年度順著作目録
・作品集収録詳細目録
●教科書掲載詳細一覧
●索引
●編著者紹介
あまんきみこは、一九三一年に旧満州で生まれ、一九六八年に連作短編集『車のいろは空のいろ』(ポプラ社)でデビューした作家です。その作家生活は五〇年をこえ、子ども/大人の読者たちを魅了してきました。
小川未明や宮沢賢治のような詩的で象徴的なことばで心象風景を描く「童話」が、もっと散文的なことばで、心のなかの景色ではなく、子どもという存在の外側に広がっている状況(社会といってもよい)や状況と子どもの関係を描く「現代児童文学」に転換する││これが日本の子どもの文学の歴史です。「現代児童文学」の成立は一九六〇年前後と考えられますが、長い戦争のあとの日本の子どもの文学は、「戦争」や戦争を引き起こすこともある「社会」を描かないわけにはいかなくなって、そのすがたを大きく変えました。
あまんきみこは、もうすっかり「現代児童文学」の時代になってからデビューした作家ですが、詩的、象徴的なことばで心象風景を描く、現代の「童話」の書き手として独自な世界をつくっていきます。あまんにとっての「戦争」は、「現代児童文学」とはまた別のかたちをとって描かれます。
散文的なことばで書かれる「現代児童文学」は長編化していきますけれども、詩的、象徴的なことばで書かれる、あまんきみこの作品のほとんどは、短編として結晶することになります。あまんの優れた短編は、デビュー間もない時期から教材化され、一九九〇年代以降は、各社の小学校の国語科教科書に最も多く作品が掲載されている作家になりました。子どもたちは、あまんきみこに教室でも出会います。
あまんきみこ研究会の設立準備総会と第一回研究会を開催したのは、二〇一六年二月二八日、武蔵野大学武蔵野キャンパスにおいてです。第一回研究会の研究発表は二題、宮川健郎「あまんきみことは誰か」と成田信子「「おにたのぼうし」教材化試論」でした。
年に二回の研究会は、その後、東京圏だけでなく、大阪や太宰府でも開催されました。あまんきみこ研究会は、あまんの作品の読まれ方にふさわしく、文学・児童文学の研究者と国語科教育の研究者/実践者がいっしょに議論をする稀有な場として成長しつつあります。現在の会員は四〇名ほどです。『あまんきみこハンドブック』は、あまんきみこ研究会の最初の出版物として企画された、いわば、「あまんきみこ研究事始め」です。研究会の中に編集委員会を設けて、二〇一八年の春から、その内容や体裁について議論を重ねました。編集と刊行を引き受けてくれたのは、二〇〇九年に『あまんきみこセレクション』全五巻を刊行した三省堂です。
『あまんきみこハンドブック』は、「あまんきみこの人と作品」「あまんきみこの作品を読む」「キーワードからみるあまんきみこの作品」「あまんきみこの周辺から」「あまんきみこをもっと知る」の五つの章で構成しました。II章の「作品を読む」に「シリーズを読む」と「一つずつ読む」の二つのパートを設けたり、III章では二〇のキーワードを掲げたり、あまんきみこのテクストにアプローチする、いろいろなルートをひらくことを試みました。童文学史の中のあまんきみこ、国語科教材としてのあまんの作品、授業の中のあまんの作品など、さまざまを考慮しながら、編集と執筆をすすめてきました。あまんきみこという現役で仕事をつづけている作家の作品をどのようにして相対化することができるか││それも、私たちが考えたことです。
『あまんきみこハンドブック』が、子ども/文学/教育の歴史と現在に関心をもつ方たちのお手もとに届き、あまんきみこの広く深く豊かな作品研究/教材研究があらためて始まることを願ってやみません。
二〇一九年八月
あまんきみこ研究会 代表 宮川健郎
*印はハンドブック編集委員
阿部 藤子 東京家政大学
遠藤 純 武庫川女子大学
大島 丈志 文教大学
木下ひさし* 聖心女子大学
熊谷 芳郎 聖学院大学
黒井 健 絵本画家
幸田 国広 早稲田大学
児玉 忠 宮城教育大学
佐藤多佳子 上越教育大学
佐野 正俊* 拓殖大学
菅野 菜月 北海道浦河高等学校
住田 勝 大阪教育大学
髙野 光男 東京都立産業技術高等専門学校
丹藤 博文 愛知教育大学
土居 安子 大阪国際児童文学振興財団
富安 陽子 児童文学作家
中地 文 宮城教育大学
中村 哲也 岐阜聖徳学園大学
成田 信子* 國學院大學
西田谷 洋 富山大学
西山 利佳 青山学院女子短期大学
畠山 兆子 梅花女子大学
早川 香世 東京都立深川高等学校
林 昂平 武蔵野大学附属千代田高等学院
福村もえこ 語り合う文学教育の会
藤田のぼる 日本児童文学者協会
藤本 恵* 武蔵野大学
松永 緑 ポプラ社
松本 修 玉川大学
三浦 和尚 愛媛大学
宮川 健郎* 大阪国際児童文学振興財団
宮田 航平* 東京都立産業技術高等専門学校
三輪 民子 児童言語研究会
武藤 清吾 琉球大学
村上 呂里 琉球大学
目黒 強 神戸大学
矢崎 節夫 童謡詩人
矢部 玲子 北海道文教大学
山元 隆春 広島大学
吉井 美香 郡山市立橘小学校

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の
リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い
平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。
教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。
ぜひご利用ください。