
鈴木 昌弘 仙台白百合女子大学
2023年12月14日
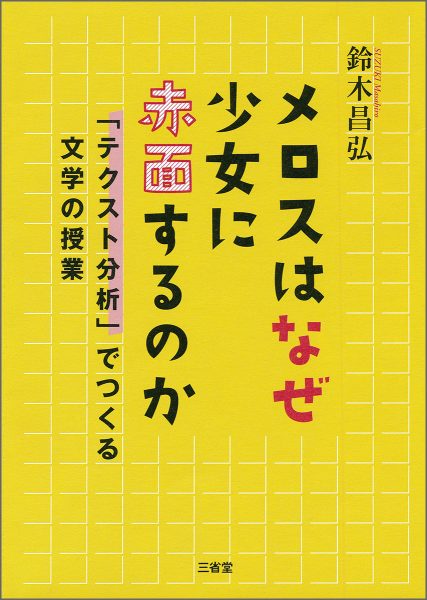
テクスト分析とは
「テクスト分析」という手法は、物語(テクスト)にある「表現しない」という表現で隠されたいくつかの「空白」を掘り起こし、それを「問」という形で顕在化して、「表現された」内容との整合性を図りつつ、それらを根拠にしながら真の主題あるいは隠された主題を探し当てる––というものである。ただそれだけであり、平たく言えば、物語の読みの勘所とそれにたどり着く道筋を示していると言える。そのために特別な技法や指導者しか知らない作者の伝記的事実についての知識を駆使している訳ではない。
だからこそ、この「テクスト分析」を学習者の実態に即してアレンジすれば、そのまま授業にすることができる。
この授業では、「問」によって学習者の知的好奇心が点火する。主題という一つの解を求めて、テクストの表現を根拠にして学習者が意見を出し合い、互いの意見を尊重しつつより高い次元の「解」を求めて「話し合い」活動となる。この過程が文学の読解と対極にあると誤解されている「論理的思考」である。
(『メロスはなぜ少女に赤面するのか 「テクスト分析」でつくる文学の授業』(鈴木昌弘) はじめに より一部抜粋)
『バースデイ・ガール』について
『バースデイ・ガール』は村上春樹の短編小説で、短編集『バースデイ・ストーリーズ』(中央公論新社、2002年12月)、『めくらやなぎと眠る女』(新潮社、2009年11月)などに収録されており、令和5年度発行の三省堂高等学校国語教科書「新 文学国語」をはじめ、中学校の国語教科書にも掲載されている作品である。
このWebコラムでは複数回にわたり、『バースデイ・ガール』についてのテクスト分析を行っていきたい。
なおコラム内の引用文は原則として『村上春樹 翻訳ライブラリー バースデイ・ストーリーズ』(中央公論新社、2006年)によった。
「語り」の構造
最後に、物語の現在から十数年前に遡行しているように見える、「オーナー」が「彼女」に「願いごと」の確認を求める場面になっているのは何故だろうか。
この場面は、物語の現在から十年前に時間を遡行しているのではない。
また「彼女」が物語の現在において、十年前を回想しているのではない。
「しかしたったひとつだから、よくよく考えた方がいいよ。可愛い妖精のお嬢さん」。どこかの暗闇の中で、枯れ葉色のネクタイをしめた小柄な老人が空中に指を一本あげる。「ひとつだけ。あとになって思い直してひっこめることはできないからね」
この最後の場面(第8場面)は物語の全体から浮いている印象を受ける。この場面がなくても物語の展開上は問題がないように思える。
さらにそんな印象に拍車をかけるのが、「彼女」が「その604号室の中にあった家具や置物のひとつひとつを、私は今でも細かいところまでありありと思い出せるの」と明言していたにもかかわらず、ここでは場所が特定されずあいまいに「どこかの暗闇の中で」となっていることである。
「細かいところまでありありと思い出せる」604号室をわざわざ「どこかの暗闇」と語るのか。「彼女」が「僕」に対して語っているのなら、改めて変更しなければならない理由はない。
「彼女」から「彼女」への語り、すなわち「彼女」自身の回想であっても、今更場所をあいまいすることも、急に記憶が薄れて場所が特定できなくなったということも考えにくい。
したがって「彼女」が語っているということは考えにくい。
それでは、この語りは誰が誰に向けて語られているのか。
この物語は全8場面で構成されている。
第1場面 勤めていた店の様子 語り手が読者に語る
第2場面 「オーナー」の習慣 「彼女」が「僕」に語る 視点人物「僕」
第3場面 二十歳の誕生日の出来事 語り手が読者に語る
第4場面 「オーナー」が願いごとを求める 「彼女」の独白(「僕」に語る体裁)、視点人物「彼女」
第5場面 「彼女」と「僕」の会話 視点人物「僕」
第6場面 「オーナー」が願いごとをかなえる 「彼女」の独白(「僕」に語る体裁)、視点人物「彼女」
第7場面 「彼女」と「僕」の会話 視点人物「僕」
第8場面 暗闇の中の「オーナー」 誰が誰に語るのか?
この物語は、三人称の語り手が「僕」を視点人物とするこの物語が語られている今と、「彼女」を視点人物とする「彼女」の二十歳の誕生日とから構成されている。
「僕」を視点人物とする場面では「僕」を通して見聞きしたこととして「彼女」の言動が語られている。「僕」の内面は語られるが、「彼女」の内面は叙述されることはない。
また「彼女」を視点人物とする場面では、「彼女」=「私」を通して二十歳の誕生日の出来事を語っている。それは第4場面と第6場面の二つの場面においてだが、いずれもその話の聞き手が「僕」なのである。
この場面のあとに次のように叙述されているので、この場面の語りは「彼女」が「僕」に向けて語られたものという形式になっている。
彼女は僕の顔を見る。「これって、本当にあった話なのよ。適当な作り話をしているんじゃないのよ」
「そのあと、オーナーと顔を合わせたことは一度もない」と彼女は言う。
いずれもそれらの場面の内容を「これ」「そのあと」という指示語で受けて、「彼女」の「僕」への二十歳の出来事を語っていたということを明示している。
第1場面についても、直接「語り手」が「読者」に語っている「語り」の構造になっている。
しかし、「僕」が「彼女」から聞いた話を整理して、語ったものと考えることもできる。そう考えた方が物語の構造として一貫性がある。
最後の場面
| 問11 | 物語の最後に「オーナー」が「彼女」に願いごとについて念押しをする場面が出てくるのは何故か。 |
さて、最後の場面を語るためには「彼女」の二十歳の誕生日に起きた「オーナー」との奇妙な出来事について詳しく知っていなければならない。当然のことである。
それができる人間は3人しかいない。当事者である「彼女」と「オーナー」、そして今「彼女」からそれを聞いた「僕」である。
「オーナー」が突如暗闇の中に現れて語り出したとは考えられない。
冒頭の場面と同じように「語り手」が直接「読者」である私たちに語っているということも考えられる。その役割は、二十歳の誕生日に「彼女」が勤めていた店の様子や彼女の当時の状況を語り、物語の世界に読者を円滑に導くことであった。しかし、最後の場面でも同じように円滑に「読者」を導くという役割のために「語り手」が直接「読者」に語っているという「語り」の構造が採用されているとは考えられない。
いずれにせよ、「語り手」が直接「読者」に語るという「語り」の構造では、私たちが最後の場面を解釈するには情報が少なすぎる。
すると消去法で答えは一つになる。
「僕」が「僕」に語っている、というものだ。そしてそれが私たち「読者」に届けられるという構造になっている。
別の角度から考えてみることにする。
そもそもこの物語は誰の物語なのか。主役は誰なのか。
「彼女」の二十歳の誕生日にアルバイトをしていた店の「オーナー」に「願いごと」を一つかなえてやると言われた。それがかなった、あるいはかなわなかった、というならば、間違いなく「彼女」が主役の物語である。
しかし、この物語はそれでは終わっていない。
「彼女」は「願いごと」の内容を明らかにせず、「僕」に「同じ立場なら、僕の二十歳の誕生日にどんなことを願ったか」を想像させる。しかし「僕」が思いつかないと答えると、「彼女」は「僕」に「とてもまっすぐな率直な視線」で「僕の目を見」て「あなたはきっともう願ってしまったのよ」と断言する。
しかもこの場面は、「僕」の視点から語られているために、私たち「読者」は、「僕」の視点で描かれていない彼の戸惑いを読もうとする。
なぜ自分の二十歳の誕生日の願いごとが思いつかなかったことが「もう願ってしまった」ことになるのか。「僕」の知らない「僕」の願いごとを「彼女」は知っているようだ。なぜ「彼女」は「僕」自身が知らない「僕」の願いごとを知っているのか。
こうして「僕」は「謎」の中に投げ出され、「謎」の虜となる。
「謎」を解きたいという「僕」の、そして私たち「読者」の欲望は点火される。
ここにおいて物語は「僕」が主役の「僕」の物語となっている。
つまり最後の場面は、「僕」が「僕」に語られたものである。
「僕」の二十歳の「願いごと」が思いつかないことが、なぜ「僕」自身の「願いごと」が「きっともう願ってしまった」という断言になるのか、その発言の根源をたどっていって彼の脳裏に浮んだのが、謎めいたオーナーの姿と言葉であったのだ。つまり二十歳の「僕」が「彼女」と同じ立場に置かれた姿を思い描く。「僕」が「彼女」の話から得たイメージを、「僕」が自分の心象風景として再現したのが、最後の場面なのである。(問11解答)
突然そのようなイメージが浮かぶものだろうか。不自然なようだが、「僕」にとってそれは難しいことではないように思われる。なぜならすでに「僕」は「時間のかかる願いごと」という抽象的な概念を「低温のオーヴンでゆっくりと焼かれている巨大なパイ料理のイメージ」という具体的なモノで思い浮かべることができている。
では、なぜ「暗闇の中」であって、604号室ではないのか。
「彼女」にとって604号室のディテールの記憶が重要な意味をもつのは、それが現実に起こったものかを確信するためである。その記憶があったからこそ、それが現実に起こったものと確信することができたのだ。だから、「彼女」にとってはこのディテールが必要だったのだ。
一方、この時の「僕」に意識されているのは、それが現実に起こったかどうかということではない。
「謎」の虜になったことで――それは「彼女」によって「謎」に巻き込まれたという方が近いかもしれないが――「ぼく」自身も「願いごと」を「オーナー」に求められる立場になっている。
「彼女」が頭の中で復唱した「なにものもそこに暗い影を落とすことのないように」というちょっと普通じゃないしゃべり方も「オーナー」自身がなにやら「暗い影」と関わりをもっていそうな雰囲気すら感じさせる。「オーナー」が用いた「暗い影」というメタファーが「オーナー」自身のイメージとして想起される。
だから、「オーナー」に一度も会ったこともない「僕」には、「オーナー」のイメージが時間も空間も超越した謎めいた神秘的な存在として迫ってくる。「オーナー」の神秘性が際立っているから暗闇の中に浮かび上がるイメージになっているのである。
ちなみに「僕」に604号室のディテールを思い浮かべる必要性が仮にあっても――実際には思い浮かべる必要性はないのだが――、「僕」にそれはできない。なぜならオーナーと実際に604号室で会ったのは「彼女」であって「僕」ではないからである。
『バースデイ・ガール』は何を物語るのか
ここからは、分析というよりも感想になる。
『バースデイ・ガール』という物語が物語るのは、身の丈にあったものこそが幸せであるが、その平凡さゆえにヒトは見過ごしてしまう。しかし身近であるということと、それをいつでも手に入れることができるということとは別である、ということである。だからこそ、身の丈にあった幸せが確実になるようにと「彼女」は願ったのである。
この物語はメーテルリンクが描いた『青い鳥』を思い起こさせる。しかしこの物語は『青い鳥』とは対照的な物語である。
「チルチル」と「ミチル」の兄妹は、夢の中で過去や未来の国に幸福の象徴である青い鳥を探しに行くが、結局のところそれは自分達に最も手近なところにある、鳥籠の中にあったということに気づく。「『青い鳥』は、すぐそばの自分たちの生活の中にあったのです。」最後には二人は鳥籠の「青い鳥」をあやまって逃がしてしまう。しかし「チルチル」は言う。「いつでも青い鳥は捕えることができる」と。
しかし、「青い鳥」を外に求めに行った後、それが身近なところにいることに気づいた「チルチル」と「ミチル」と違って、先の見通しの立たない混迷の始まりに二十歳を迎えた「彼女」は最初から「青い鳥」がどこか遠くにいるとは考えない。そしていつでも捕えられる訳ではないことを知っている。「彼女」は「青い鳥」がどこにいるかを、あるいはどこにいるべきかをすでに知っていたのだ。「青い鳥」は、「彼女」が願ったようにいま「彼女」と「ぼく」の日常の中にいる。
メロスはなぜ少女に赤面するのか 「テクスト分析」でつくる文学の授業
「テクスト分析」は,優れた物語がもつ「空白」を,「問」という形で顕在化させる。テクストを根拠に「解」を求める過程こそ論理的思考である。「テクスト分析」の手法で,国語の授業を力強くサポートする。
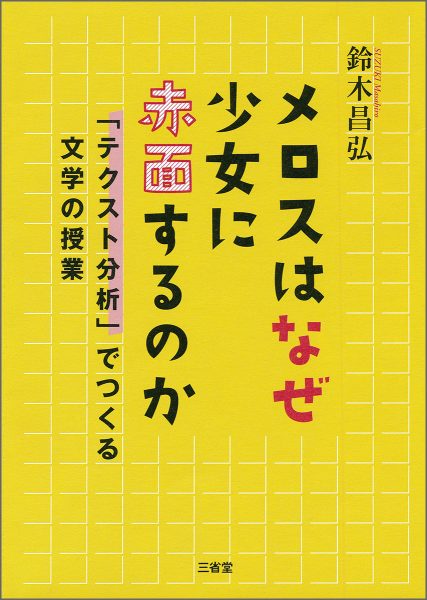
鈴木 昌弘 すずき・まさひろ 仙台白百合女子大学
大阪市に生まれる。大阪教育大学教育学部国語科卒。大阪市立中学校国語科教員を経て、同小学校教頭、同中学校教頭・校長を務める。小学校・中学校において国語科教育研修会講師などを務める。
現在、仙台白百合女子大学特任教授。三省堂中学校国語教科書編集協力委員。

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の
リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い
平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。
教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。
ぜひご利用ください。