
鈴木 昌弘 仙台白百合女子大学
2023年12月14日
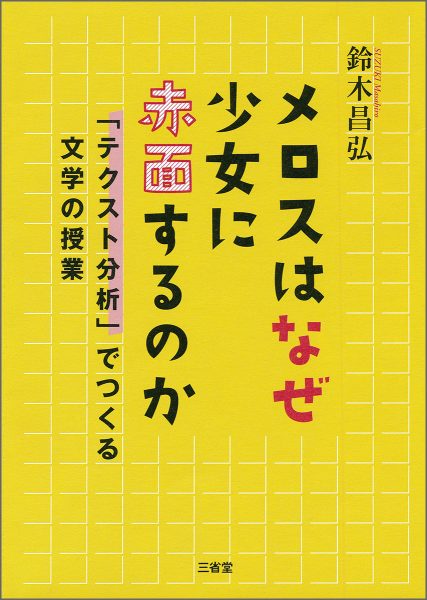
テクスト分析とは
「テクスト分析」という手法は、物語(テクスト)にある「表現しない」という表現で隠されたいくつかの「空白」を掘り起こし、それを「問」という形で顕在化して、「表現された」内容との整合性を図りつつ、それらを根拠にしながら真の主題あるいは隠された主題を探し当てる––というものである。ただそれだけであり、平たく言えば、物語の読みの勘所とそれにたどり着く道筋を示していると言える。そのために特別な技法や指導者しか知らない作者の伝記的事実についての知識を駆使している訳ではない。
だからこそ、この「テクスト分析」を学習者の実態に即してアレンジすれば、そのまま授業にすることができる。
この授業では、「問」によって学習者の知的好奇心が点火する。主題という一つの解を求めて、テクストの表現を根拠にして学習者が意見を出し合い、互いの意見を尊重しつつより高い次元の「解」を求めて「話し合い」活動となる。この過程が文学の読解と対極にあると誤解されている「論理的思考」である。
(『メロスはなぜ少女に赤面するのか 「テクスト分析」でつくる文学の授業』(鈴木昌弘) はじめに より一部抜粋)
『バースデイ・ガール』について
『バースデイ・ガール』は村上春樹の短編小説で、短編集『バースデイ・ストーリーズ』(中央公論新社、2002年12月)、『めくらやなぎと眠る女』(新潮社、2009年11月)などに収録されており、令和5年度発行の三省堂高等学校国語教科書「新 文学国語」をはじめ、中学校の国語教科書にも掲載されている作品である。
このWebコラムでは複数回にわたり、『バースデイ・ガール』についてのテクスト分析を行っていきたい。
なおコラム内の引用文は原則として『村上春樹 翻訳ライブラリー バースデイ・ストーリーズ』(中央公論新社、2006年)によった。
「僕」の最初の質問に対する「彼女」の「イエスであり、ノオね」という答え
| 謎7. | 「僕」の二つ目の質問である「君はそれを願いごととして選んだことに後悔していないか?」について、 |
| (1) | 「彼女」は「僕」のこの質問に即答せずに(「少しの沈黙の時間がある」)、「奥行きのない目を僕に向けて」「僕にひっそりとしたあきらめのようなものを感じさせ」る「ひからびた微笑みの影がその口もとに浮かんでいる」のは、何故か。 |
| (2) | さらに「彼女」が「僕」の質問をはぐらかすように、代わって「私は今、三歳年上の公認会計士と結婚していて、子どもが二人いる」「男の子と女の子。アイリッシュ・セッターが一匹。アウディに乗って、週二回女友だちとテニスをしている。それが今の私の人生」と「僕」に話すのは何故か。 |
| (3) | 「彼女」が語った「今の私の人生」について「僕」が「それほど悪くなそうだけど」と返したのに対して「彼女」がさらに「アウディのバンパーにふたつばかりへこみがあっても?」と聞き返しているのは何故か。 |
「彼女」は自分の「願いごと」が何であったのかを間接的ではあるが、「僕」に答えている。それを考察するための支点の働きをするのが、次の5点である。
(1)「僕」の最初の質問に対する「彼女」の「イエスであり、ノオね」という答え
(2)「僕」との会話での「彼女」の表情の変化
(3)「アウディのバンパーにふたつばかりへこみがあっても?」の意味
(4)ステッカーの意味
(5)「あなたはきっともう願ってしまったのよ」という断言。
「僕」の一つめの質問「その願いごとが実際にかなったのか」について、彼女はこう答えている。
「イエスであり、ノオね。まだ人生は先が長そうだし、私はものごとの成りゆきを最後まで見届けたわけじゃないから」
「願いごと」がどのようなものか。もちろん「誰かに言っちゃいけないこと」であるから、具体的には言ってはいない。しかし全く話さない訳ではない。(なぜ「誰かに言っちゃいけないこと」なのかは後に考察する)。
「まだ人生は先が長そうだし、私はものごとのなりゆきを最後まで見届けたわけじゃないから」からわかるように、「彼女」の「願いごと」は一生涯をかけてかなえられるものである。
ところで「イエスであり、ノオね」という答えは、質問に正面から対応した答えである。
それは例えば「答えられない」や「イエス、ノオのどちらでもない」という質問に対して答えをはぐらかすようなものとは本質的に異なる。
「願いごと」は一生涯をかけてかなえられるものである。したがって、それが実際にかなったかどうかを判断するためには、まだ先が長いこれからの人生におけるものごとのなりゆきを最後まで見届ける必要がある。だから「彼女」は現時点では「ノオ」であると答えている。
しかし、その一方で「イエス」と答えているのは、現時点までは「願いごと」(それが何であると具体的には言っていないが)がかなえられているということである。
すなわち、「彼女」の「願いごと」は一生涯をかけてかなえられるもので、その判断は人生の最後まで見届けた上でなければその正否は判断できないが、少なくとも現時点においてはかなえられていると言っているのである。
「僕」との会話での「彼女」の表情の変化
「僕」との会話の中で「彼女」の表情は次のように変化している。
| a. | 「奥行きのない目をぼくに向けている。ひからびた微笑みの影がその口もとに浮かんでいる。それは僕にひっそりとしたあきらめのようなものを感じさせる」 |
| b. | 「彼女は声を上げて楽しそうに笑う。それで、さっきまでそこにあったひからびた微笑みの影はどこかにふっと消えてしまう」 |
| c. | 「彼女はカウンターに肘をついて、僕を見る」 |
| d. |
「彼女はもう一度僕の目を見る。それはとてもまっすぐな率直な視線だ」 |
aの「奥行きのない目」は、明らかに「僕」に向けたものだ。「彼女」の口もとに浮かんでいる「ひからびた微笑みの影」も「僕」に向けられものである。したがって、「僕にひっそりとしたあきらめのようなものを感じさせ」た「あきらめのようなもの」とは、明らかに「僕」に対するあきらめの表れである。
では「彼女」はいったい「僕」の何にあきらめを感じたのだろうか。それは、二つめの質問「君はそれを願いごととして選んだことを後悔していないか?」のためである。
質問の何が「彼女」に「僕」をあきらめさせたのか。それは質問のあとの「彼女」の発言を見ることで明らかになる。その発言は「願いごと」に関係がないように思える次のようなものだった。
「私は今、三歳年上の公認会計士と結婚していて、子どもが二人いる」
「男の子と女の子。アイリッシュ・セッターが一匹。アウディに乗って、週二回女友だちとテニスをしている。それが今の私の人生」
「それを願いごととして選んだことを後悔していないか?」という質問に対して「彼女」は何故このような「今の私の人生」を語るのだろうか。
先に確認したように「彼女」は「願いごと」は現時点においてかなえられている、という実感をもっている。そのことについては「イエス」と答えて「僕」に伝えている。
それにもかかわらず「後悔していないのか」と「僕」は質問してくる。それが「僕」に対するあきらめの正体である。
つまり、「彼女」のあきらめの表情は「私が、今願いごとがかなっていると言っているのに、何故あなたは後悔していないかとしつこく聞くのか」という思いから発するものだ。(問7(1)解答)
そこで「彼女」が次に取った行動は、「願いごと」がかなった今が後悔に当たるものであるかどうかを「僕」に判断させることである。「僕」に判断させるためにはその判断材料を提供する必要がある。「願いごと」がかなったと「彼女」が実感している「今の私の人生」である。
「彼女」が語った「私は今、三歳年上の公認会計士と結婚していて、子どもが二人いる」「男の子と女の子。アイリッシュ・セッターが一匹。アウディに乗って、週に二回女友だちとテニスをしている」「今の私の人生」こそが「願いごと」がかなったその内容であった(ここで注意しなければならないのは、これは「願いごと」がかなった内容であって、「願いごと」そのものではない、ということである)。(問7(2)解答)
「アウディのバンパーに二つばかりへこみがあっても?」の意味
「彼女」が語った「今の私の人生」に対して「僕」は「それほど悪くなさそうだけど」と答えている。それを受けて「彼女」が言ったのが「アウディのバンパーにふたつばかりへこみがあっても?」である。これは、実際に所有している「アウディ」のバンパーにへこみがあるのだろう。
確かに高級車のカテゴリーに入る「アウディ」のバンパーのへこみを、それも二つもそのままで放置しているのを見かけることはない。見栄えを重んじるであろう高級車のオーナーならふつう早急に修理するはずだが、それを放置している。
「彼女」は、確かにそのことを指して言っているわけではあるが、表現している内容は「バンパーのへこみ」ではない。
何故なら、「僕」の「だってバンパーはへこむためについているんだよ」という答えに対して「ステッカー」をもち出し、さらにそれに続けて「私が言いたいのは」と切り出しているからである。
「ステッカー」の意味
「そういうステッカーがあるといいわね」と彼女は言う。「『バンパーはへこむためにある』」
これだけだとわかりにくいが、それに続く「私が言いたいのは」ということばと併せるとわかる。
「私が言いたいのは」の前に「『バンパーのへこみ』で」、ということばを補うと
「バンパーのへこみ」で私が言いたいのは、
となる。つまり、「私が言いたいのは」とは、「『バンパーのへこみ』で私が表現したかったことは、現実にある『バンパーのへこみ』のことではない。そうではなくて、」ということである。「僕」の誤った理解を訂正しようとする注意喚起である。
「だってバンパーはへこむためについているんだよ」という「僕」の答えと、おそらくそう答えている時の「僕」の雰囲気から、現実のバンパーの二つのへこみについて「僕」が言及している。――と、そう「彼女」は受け取った、その時は少なくともそう受け取ったのである。
したがって「ステッカー」のくだりは、「バンパーのへこみ」が現実の「バンパーのへこみ」を表現したものではないことを気づかない「僕」の察しの悪さに対する皮肉や当てこすりということになる。「ステッカー」を持ち出したのは「バンパー」からの連想で同じく車に関連するものだからだろう。
では、「バンパーのへこみ」は何を表現しているのか。
結論から先に言えば、先に話していた「今の私の人生」におけるマイナス面の補足である。それをメタファーとして表現したものである。「私が言いたいのは」の後に次のように続く。
「人間というのは、何を望んだところで、どこまでいったところで、自分以外にはなれないものなのねっていうこと。ただそれだけ」
これが「バンパーのへこみ」というメタファーが意味する内容である。つまり「彼女」自身がそれを解説したものである。
ここまでの「彼女」と「僕」のやり取りを、記述されていない彼女の内面も想像しながらまとめると、次のようになる。
「僕」の「願いごとはかなったか」という質問に、「彼女」自身は、先のことはわからないと保留しながらも現時点で「願いごと」がかなったと思っていて、それに満足している。満足しているというニュアンスを伝えているにもかかわらず(直接そうには言っていないけれども)、それを否定するかのように「僕」が「後悔していないか」と質問してくる。そのことにあきらめを感じながらも「彼女」は「願いごと」がかなっている「今の私の人生」を具体的に話して、これが後悔に値するものなのかどうかという判断を「僕」に委ねる。
ところが、「後悔していないか」と言ったわりに「僕」がいともたやすく「それほど悪くなさそうだけど」と答えたものだから、「彼女」はそんなに簡単に肯定してしまっていいの?という気持ちから「今の私の人生」のマイナス面を「バンパーのへこみ」というメタファーで出して、確認してみたのだ。(問7(3)解答)
その「僕」の答えから、「僕」が「バンパーのへこみ」がメタファーであることを理解していないと「彼女」は判断し、「私が言いたいのは」のくだりで、このメタファーの解説をしたのだ。
「あなたはきっともう願ってしまったのよ」という断言
| 問8 | 「私が言いたいのは」「人間というのは、何を望んだところで、どこまでいったところで、自分以外にはなれないものなの」について、 |
| (1) | 何を表しているのか。何故そんなことを唐突に持ち出すのか。 |
| (2) | それに対する「僕」の「そういうステッカーも悪くないな」「『人間というのは、どこまでいっても自分以外にはなれないものだ』」という返答に「彼女は声を上げて楽しそうに笑」い、「それで、さっきまでそこにあったひからびた微笑みの影はどこかにふっと消えてしまう」というように「彼女」の表情が一変したの何故か。 |
「僕」からの質問に答えるだけだった「彼女」が、一転して「あなたが私の立場にいたら、どんなことを願ったと思う?」を「僕」に尋ね出す。そして、その質問に「僕」自身が答えられないでいると、「あなたはきっともう願ってしまったのよ」と断言するのである。
質問を受ける立場にあった「彼女」がなぜ突然質問をする立場へ変わったのか。その理由を考えてみたい。
「彼女」が質問に転じたのは、「彼女」が「人間というのは、何を望んだところで、どこまでいったところで、自分以外にはなれないものなのねっていうこと。ただそれだけ」と言ったことに、先の「バンパーのへこみ」の答えと一見変わりがないような、「僕」が「そういうステッカーも悪くないな」「『人間というのは、どこまでいっても、自分以外にはなれないものだ』」と答えた後である。
正確には、その「僕」の答えに「彼女」は、「彼女は声を上げて楽しそうに笑」い、「それで、そこにあったひからびた微笑みの影はどこかにふっと消えてしまう」という反応を示した後である。
さらに、先ほどの「僕にあきらめを感じさせた」様子と、質問している「彼女」とでは明らかに異なっている。「彼女はカウンターに肘をついて、僕を見る」。そこには気持ちに余裕が生まれているように見える。また「あなたはきっともう願ってしまったのよ」と断言する時の「彼女はもう一度僕の目を見る。それはとてもまっすぐな率直な視線」も、核心を掴んだ確信に満ちているように見える。
つまり「彼女」が質問に転じた理由は、「僕」のこの答えを「彼女」がどう捉えたかということにある。
「バンパーのへこみ」のメタファーで表現しているのは「彼女」の欠点であったが、「僕」はそれを理解していなかったので、仕方なく「私が言いたいのは」以下で解説したのだった。
つまり、「人間というのは、何を望んだところで、どこまでいったところで、自分以外にはなれないものなの」で解説しているのは、「バンパーのへこみ」とは「今のままではいけないと思い、違う人間になろうと自分なりにこれまで欠点の矯正に努めてきたが、その欠点についてはどうしようもできなかったのだ」ということなのである。(問8(1)解答)
ふたたび「ステッカー」の意味
そんな「彼女」の表情がなぜ新たに持ち出した「ステッカー」のくだりで一変したのだろうか。
先に「彼女」が言った「ステッカー」は察しの悪い「僕」に対する皮肉であり、当てこすりであったことはすでに考察した。同様の意味なら、「彼女」にこのような変化は起こらなかったはずである。
ここでは「僕」は「ステッカー」で何を表しているのだろうか。あるいは「彼女」は「ステッカー」の意味をどのように受け取ったのか。
「ステッカー」にするということは、ある種のメッセージを短い文や句として固定化することであり、その固定化したメッセージを永久に留めようとする営みである。「そういうステッカーも悪くないな」とは、その内容を肯定し、永久化するという態度表明である。
すなわち、「『人間というのは、どこまでいっても、自分以外にはなれないものだ』」という「ステッカーも悪くないな」と言う「僕」の発言は、欠点のある「彼女」を、その「彼女」のこれまでの人生をあるがままに無条件に受け止め、その継続を願うということの表明に他ならない。
「彼女」自身が「僕」がその意味で「ステッカー」という言葉を使ったのだと実感できたからこそ、「彼女は声を上げて楽しそうに笑」い、「ひからびた微笑みの影はどこかにふっと消えてしま」ったのだ。「あきらめ」が解消され、安堵した表情である。(問8(2)解答)
さて、何故「彼女」は「あなたはきっともう願ってしまったのよ」と断言できるのだろうか。「僕」本人が「何も思いつかない」「何ひとつ」思いつかないと答えているにもかかわらず、である。
それは、「彼女」と同じ立場なら、「僕」が二十歳の夜に何を願ったかを「彼女」がわかっていると確信しているからである。
なぜ「彼女」は確信できているのか。「彼女」は「僕」が何を願ったかを知っているからに他ならない。
答えは一つしかない。「彼女」が願ったことが「僕」の願ったことだからである。
「彼女」の二十歳の誕生日の「願いごと」とは何か
| 問1 | 「彼女」は十年以上昔、二十歳の自分の誕生日に願いごとに何を願ったのか。 |
| 問9 | 「ねえ、もしあなたが私の立場にいたら、どんなことを願ったと思う?」について、 |
| (1) | 「声を上げて楽しそうに笑」ったあと、一転して「彼女」は自分だったら何を願ったかを「僕」に聞こうとするのは何故か。 |
| (2) | その質問に対して「僕」自身が答えられないのに、何故「彼女」は「とてもまっすぐな率直な視線で」見て「『あなたはきっともう願ってしまったのよ』」と断言できるのか。 |
「彼女」は十年以上昔、二十歳の自分の誕生日に願いごとに何を願ったのか。
「彼女」が願ったのは、「私」と一緒にいる人生を悪くないなと思い、それが続いてほしいと願う人と一緒になりたい――ということだったのだ。そして、その人が「僕」だったのだ。(問1解答)
「僕」の「願いごと」は、「彼女」によって願われたものである。つまり「僕」の「願いごと」は「『私』と一緒にいる人生を悪くないなと思い、それが続いてほしい」という願いである。
「僕」の「願いごと」は「彼女」によって願われたものであり、それも時間をかけてかなえられるものだった。ましてや「僕」が意を決してこの願いをかなえたいと願った「願いごと」でもない。
だから、「彼女」から「僕の二十歳の誕生日の夜に」「もしあなたが私の立場にいたら、どんなことを願ったと思う?」と短兵急に問われたところで、「僕」は「何ひとつ思いつかない」のである。
さきに「彼女は声を上げて楽しそうに笑」い、「ひからびた微笑みの影はどこかにふっと消えてしま」ったのは、「あきらめ」が解消され、安堵した表情である、としたが、それは正確ではなかった。
「僕」が「そういうステッカーも悪くないな」と言ったことで「僕」が「『私』と一緒にいる人生を悪くないなと思い、それが続いてほしい」と思っていることが確認できたのである。
つまり、「彼女」の「願いごと」がかなっていることが当事者である「僕」の口から直接確かめられたのである。(問9(1)解答)
それは同時に「僕」の「願いごと」がかなっている、ということでもある。したがって「あなたはきっともう願ってしまったのよ」と断言できるのだ。(問9(2)解答)
また最初に「彼女」が、「誰かに言っちゃいけないこと」として「僕」に願いごとが何であるかを教えなかったのは、「僕」がその「願いごと」の当事者だからである。
それを当事者に教えることは、当事者が意識して「願いこと」を変容させてしまうことを考えたからではないか。そのようにも想像することができる。
メロスはなぜ少女に赤面するのか 「テクスト分析」でつくる文学の授業
「テクスト分析」は,優れた物語がもつ「空白」を,「問」という形で顕在化させる。テクストを根拠に「解」を求める過程こそ論理的思考である。「テクスト分析」の手法で,国語の授業を力強くサポートする。
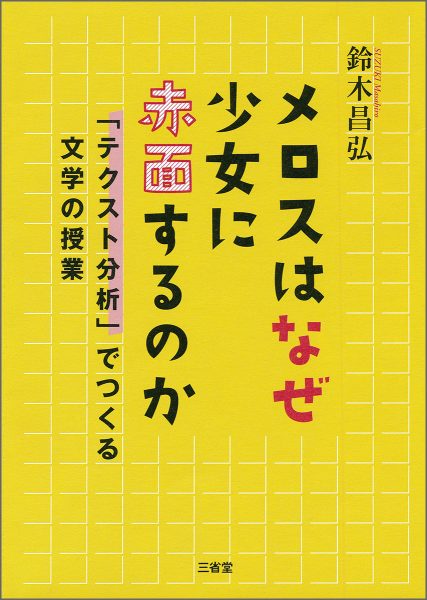
鈴木 昌弘 すずき・まさひろ 仙台白百合女子大学
大阪市に生まれる。大阪教育大学教育学部国語科卒。大阪市立中学校国語科教員を経て、同小学校教頭、同中学校教頭・校長を務める。小学校・中学校において国語科教育研修会講師などを務める。
現在、仙台白百合女子大学特任教授。三省堂中学校国語教科書編集協力委員。

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の
リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い
平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。
教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。
ぜひご利用ください。