
山田 和大 (尾道市立大学)
2025年03月13日
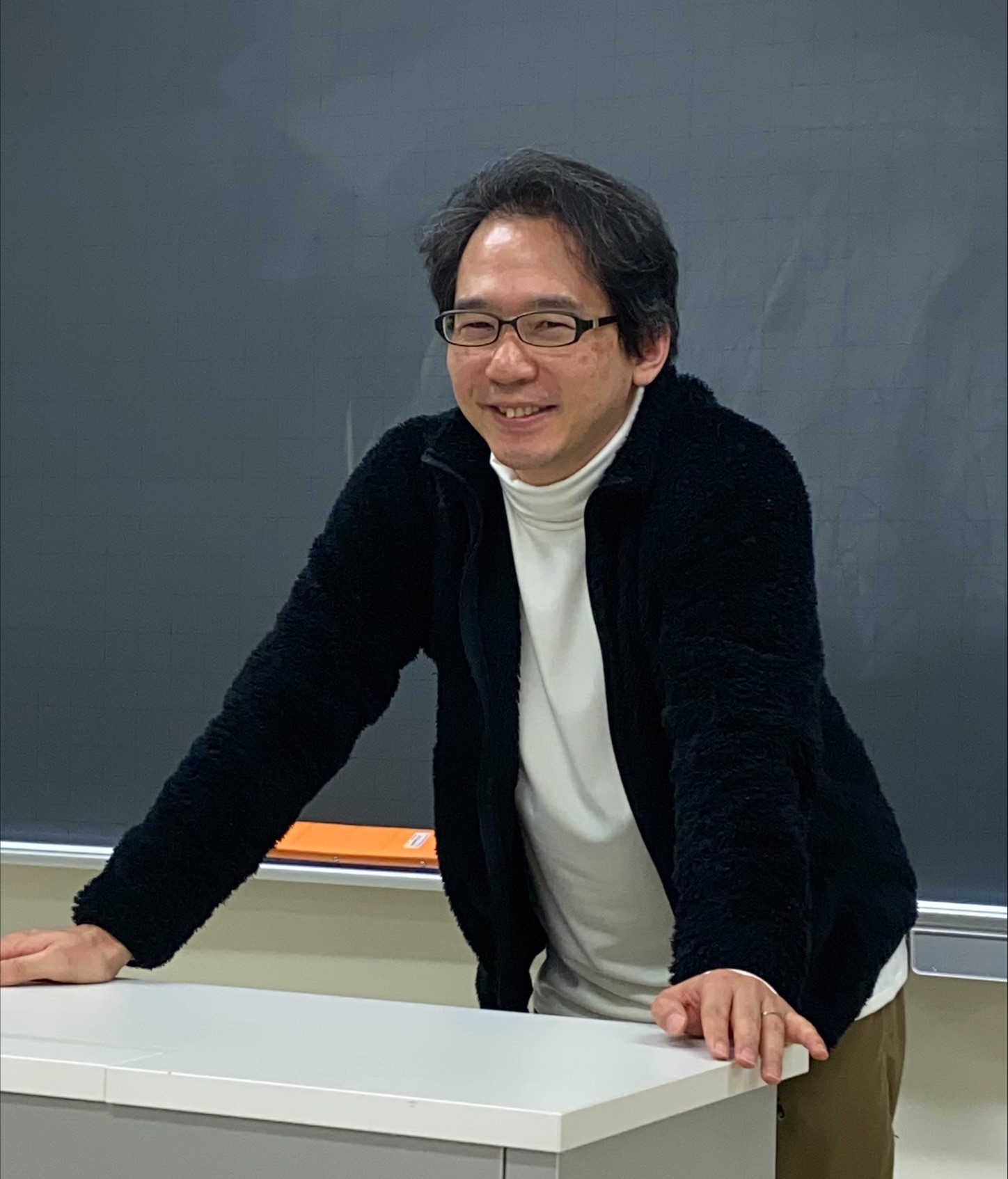
1.はじめに
平成30年告示学習指導要領により、国語科の科目は大幅に変更された。この変更に伴い、「読むこと」を〔思考力・判断力・表現力等〕の領域に入れている全ての科目で文章を「評価」することが指導事項として掲げられることとなった。本稿では、文章を「評価する」授業の一案として、「言語文化」に収録されている漢文教材を活用する授業の一例を示すこととしたい。
2.教材の特徴
本稿で使用する教材は、『十八史略』所収の「鶏口牛後」である。「鶏口牛後」は、『十八史略』巻一「春秋戦国 趙」に収録されている。まず、簡単に内容を示しておく。具体の本文、書き下し文、口語訳はのちに載せるワークシートを参照されたい。
はじめに、秦国が諸侯を恐れさせていたときに、蘇秦が合従策を燕王に提案して資金を得た後、趙を始めとする諸侯に対して「鶏口牛後」のことわざを使って説得を試みた結果、六国の合従がなったと述べる。
つぎに、蘇秦が遊説しはじめたころに説が受け入れられず困窮して帰ったときには家族が冷淡だったのに、六国の合従を成功させた後は家族が厚遇したため、あきれてしまったという内容を述べる。
最後に、六国の合従がなったのちに趙に帰って武安君に封じられたと言う。
ここで特に注意したいのは、時間軸の設定である。『十八史略』に先行する『史記』の記述をもとに時間軸を整理すると以下の通りである。
蘇秦の初期の遊説と家族による冷遇→趙王の説得→六国合従→趙への帰国途中に故郷により家族に厚遇されてあきれる→趙へ帰国し武安君に封じられる
『十八史略』は『史記』の構成をそのままに文章を削ったとは言えず、『史記』の文章展開を入れ替えた上で削除を行っている。具体的には、物語の核心ともいうべき蘇秦による諸侯の説得を始めにもってきて、その背景事情を述べるという順序にしている。これにより、『十八史略』の主な読者として想定されていたであろう歴史の初学者からすれば、興味を惹かれる事柄から歴史の理解に入り込んでいけるというメリットが生まれていると考えることができよう。文章の「評価」という観点からすると、こうした物語の展開の相違をふまえた授業を組むことができると考えられる。
(注)なお、現行の教科書においては、第一段落のみをとるもの(三省堂『新 言語文化』を含め、5者)、第一段落から第二段落までをとるもの(他社教科書2者)が見える。
3.授業実践案
先の述べた教材としての特徴を踏まえつつ、以下に簡略な授業案を示す。授業案は、平成30年度に筆者が高等学校教員だった時代に行った授業をふまえ、「言語文化」の授業として成立するようにアレンジしている。平成30年に行った授業の概略を示すために、簡易版の「単元指導案」(図1)及び「学びのプラン」(図2)を示す。「単元指導案」は、毎単元で作成し、同じ授業科目を担当する教員の共通理解を促すためのアイテムであり、授業を行う際の留意点なども記してある。留意点には、目安となる時間数も書いたが、実際にはこれより多く時間をとった。これをベースに、ほぼ同じ文言を使って生徒用にアレンジしたのが「学びのプラン」である。こちらには、生徒が振り返りを書くことができるようにした。
(注)「学びのプラン」については、筆者が平成28年度に参加した「言語活動指導者養成研修」において、横浜国立大学名誉教授 髙木展郎先生からご教示いただいたものをもとにアレンジした。
【学習指導目標】
|
古典の世界に親しむために、作品や文章の歴史的・文化的背景などを理解することができる。(〔知識及び技能〕(2)我が国の言語文化に関する事項 イ) |
|
文章の構成や展開、表現の仕方、表現の特色について評価することができる。(〔思考力、判断力、表現力等〕B読むこと(1)ウ) |
|
言葉がもつ価値への認識を深めるとともに、生涯にわたって読書に親しみ自己を向上させ、我が国の言語文化の担い手としての自覚をもち、言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を養う。(〔学びに向かう力・人間性等〕) |
【学習指導計画】
| 第一次 | 「学びのプラン」を配付し、単元の見通しを示す。『十八史略』の文章をAパート(蘇秦の説得「秦人恐喝諸侯」~「於是六国従合」)、Bパート(遊説初期の蘇秦「蘇秦者」~「嫂不為炊。」)、Cパート(合従成立後の蘇秦「至是為従約長」~「以賜宗族朋友。」)、Dパート(帰趙後の蘇秦「既定従約帰趙、粛侯封為武安君。」)に分割したものを読み、どのような順番で物語が展開していくかを考え、根拠とともに説明する。 |
| 第二次 | 『史記』の該当部分を訳文で読み、再度、A~Dパートの順を考えなおし、考えた根拠とともに説明する。 |
| 第三次 | 『十八史略』の原文の順を示し、表現効果を考えるとともに、『十八史略』のまとめ方について評価をする。「学びのプラン」を使って、単元の振り返りをする。 |
平成30年当時に使用していた教科書では、Aパート(「秦人恐喝諸侯」~「於是六国従合」)、Bパート(「蘇秦者」~「見季子位高金多也。」)、Cパート(「秦喟然歎曰」~「以賜宗族朋友。」)として形式段落が分かれており、分量にも大きな差が無かったため、この段落構成をそのまま生かして、知識構成型ジグソー法を行った。それぞれのパートごとにエキスパートグループを作って、パートごとに配付された訓点付き原文を読解してパートの内容理解を深め、そのご、ジグソーグループとして3人を基本とするグループとなって、それぞれのパートを担当した生徒がそのパートの内容を説明したのち、どういう順に並べるか、ということを考えるように仕向けた。正確な記録が残っていないので記憶頼みになってしまうが、『十八史略』をどういう順で並び替えればよいかということについて、当時の生徒の見解は主にA➔B➔Cという原文通りの順番、B➔A➔Cという『史記』に近い順番に分かれ、統一はされなかった。どうならべればよいかという全体での議論は、1時間ではおさまりきらなかったという記憶がある。当時使用した教材のBパートの中に、Aパートの前、後の時間がそれぞれ入っていたことも考えにくさにつながったことと思われる。
そこで、今回提示する案では、時間のまとまりが取りやすいようにパート分けに改変を加えた。この段階での読みの手法としては、知識構成型ジグソー法の手法をとることも考えられるが、本文の分量の差があるため、個人作業としたほうがよいと考えられる。
おそらく、多くの学校の教室では、この段階で全員が単一の順序を選ぶということはなかろう。この段階では一つの正解にもっていく必要はなく、むしろ生徒間での考え方のずれを単元の始めであらわにしたい。これによって、生徒たちのもつ、なまの感覚や思考に基づいた古典の読みに入り込めるようにすることができると考えられる。
なお、この段階で使用するワークシート案として2例示す。一つ目は、白文と訳文のセット(図3)、二つ目は書き下し文のみを示したもの(図4)である。このワークシートはデジタル上で使用することを想定してPowerPointで作成し、2ページ構成としている。1ページ目には、『十八史略』から白文と訳文のセット、ないしは書き下し文を示しており、順序についての作為が入らないよう、単純な長さによる配列をした。これを生徒に並べ替えさせる。そのとき、2枚目に並べ替えの理由を書くこと、及び理由を書く際の観点を示しておく。観点としては、「語の使い方、句法などの文法的な要素、文章内容のつながり、読者への伝わり方の違いなど」と示し、単純な感覚ではなく、本文に何らかの根拠をもって並べ替えができるように促す。2枚目の理由を書いたところで、グループで共有、ないしはMicrosoft Teamsや Google Classroom等のツールを使って全体で共有する。展開や生徒の思考がスムーズに進めるため、グループで共有してブラッシュアップしたものを、全体で共有するという流れをとるとよい。この第一次は、おおむね1単位時間から1.5単位時間程度で展開することが可能だと考えられる。
このような時間をとったのち、実際どのような展開が考えられるのか、ということを考えるために、『十八史略』のもととなる『史記』の順序を理解していく。『十八史略』と比較したときに、『史記』は文章が長いぶん、丁寧に事柄を記述していくように見えるという特徴がある。それゆえ、よく言われるようにある種の小説を読んでいるような感覚で読み進めることができ、時系列で並べられていても物語世界を十分に堪能、理解できる。おそらく生徒はこの段階では、『史記』の順に従って『十八史略』の文章を並べ替えたがることになると思われる。しかしながら、『十八史略』の文章で『史記』の順にしてしまうと、味気ない雰囲気になってしまう。ここに気づけばそれでよいし、気づかなくてもよい。大事なのは、『史記』との比較を通して文章を並び替えてみることで、どう並び替えるのがよいか、それはなぜか、ということについて思考をめぐらせることである。訳文とはいえ、それなりに長さをもつ『史記』を読み、並べ替えを再度考えるという過程をとるため、2単位時間程度の時間が必要となる。
第三次では、ここまでの流れを踏まえて、『十八史略』の原文を訓点付き白文で示す。ここまでの流れで、生徒は自分自身でどのように文章を組み立てていけばよいか、その組み立てにすることでどのような効果が生まれるか、ということを考えてきた。その考えをもたせた上で、文章を評価させるわけである。材料が何もない状態で文章を評価することは、大人であっても難しい。だが、ここまでの思考によって、文章の評価をするための自分自身の見方を得た状態であれば、十分に文章の表現や構成、展開に対して評価をすることができるであろう。ここでは、しっかりと評価をする文章を書かせるために1単位時間をまるまる使う。分量は生徒の状況にもよるが、400字詰め原稿用紙一枚程度書かせればよい。時間が許すようであれば、生徒が相互に文章を読み合ってコメントを付けたり、そのコメントをもとに推敲したりすることまでの展開を行うべきである。書きっぱなしではなく、推敲をすることで「評価」に関する思考を十分にめぐらせることができるためである。
並べ替えをせず、先に『十八史略』を読み、そのあと『史記』を読むという授業方法も考えられるが、この授業案では第一次が一番の肝になる。この第一次を設けることで、生徒起点の授業をつくることができ、生徒にとっての古典作品を読むことの必然性が生まれてくる。こうした授業を展開していきたいところである。
なお、〔知識及び技能〕については、歴史的な背景等に特化しているため、句法等の知識を付けるタイミングを設定していない。そのため、必要に応じて、単元の最後、あるいは複数の単元の後などにまとめて句法の時間を設けることも考えられる。また、句法にこだわろうと思えば、たとえば第三次の作文のときに、「寧~、無~」の効果が十分に見られるかなどといった観点から書かせるということも可能であろう。いずれにせよ、教室の実態に応じた判断が必要である。
4.まとめ
以上、文章を「評価」するということを目標とした授業の提案をしてきた。何かを評価して考えようと思えば、比較をしていくことが早道である。比較をするときに、現代文教材だと同じテーマのもので、なおかつ文章の構成や表現の相違があるものを探すこととなる。その点、漢文教材のうち、今回取り上げたような『十八史略』であれば、先行する史書をかいつまんでいるため、必ず文章の変更が行われており、比較する教材として使いやすいものと思われる。こうした特徴をうまく活用していけば、言語文化を始めとする国語科の授業づくりにおける効果的な教材選定が行いやすくなるだろう。
古典の授業は読むために必要なスキルや知識が多くあるため、どうしてもそのスキル等の習得のための正解到達を目指すことになりがちである。しかし、ここに示したように、古典作品は使いようによっては、高度な思考を可能にする教材ともなる。むしろ、古典として残ってきたほどの作品なので、そうした力を必ずもっていると考えて教材に対峙したほうがよいとさえ思える。古典のもつ力を、高等学校国語科教育の中でよりよく活かすための方法を考え続けたい。
主要参考文献
・漢詩・漢文教材研究会編『漢詩・漢文解釈講座 第9巻 歴史Ⅱ(史記・中)』(昌平社、1995年)
・漢詩・漢文教材研究会編『漢詩・漢文解釈講座 第11巻 歴史Ⅳ(十八史略・上)』(昌平社、1995年)
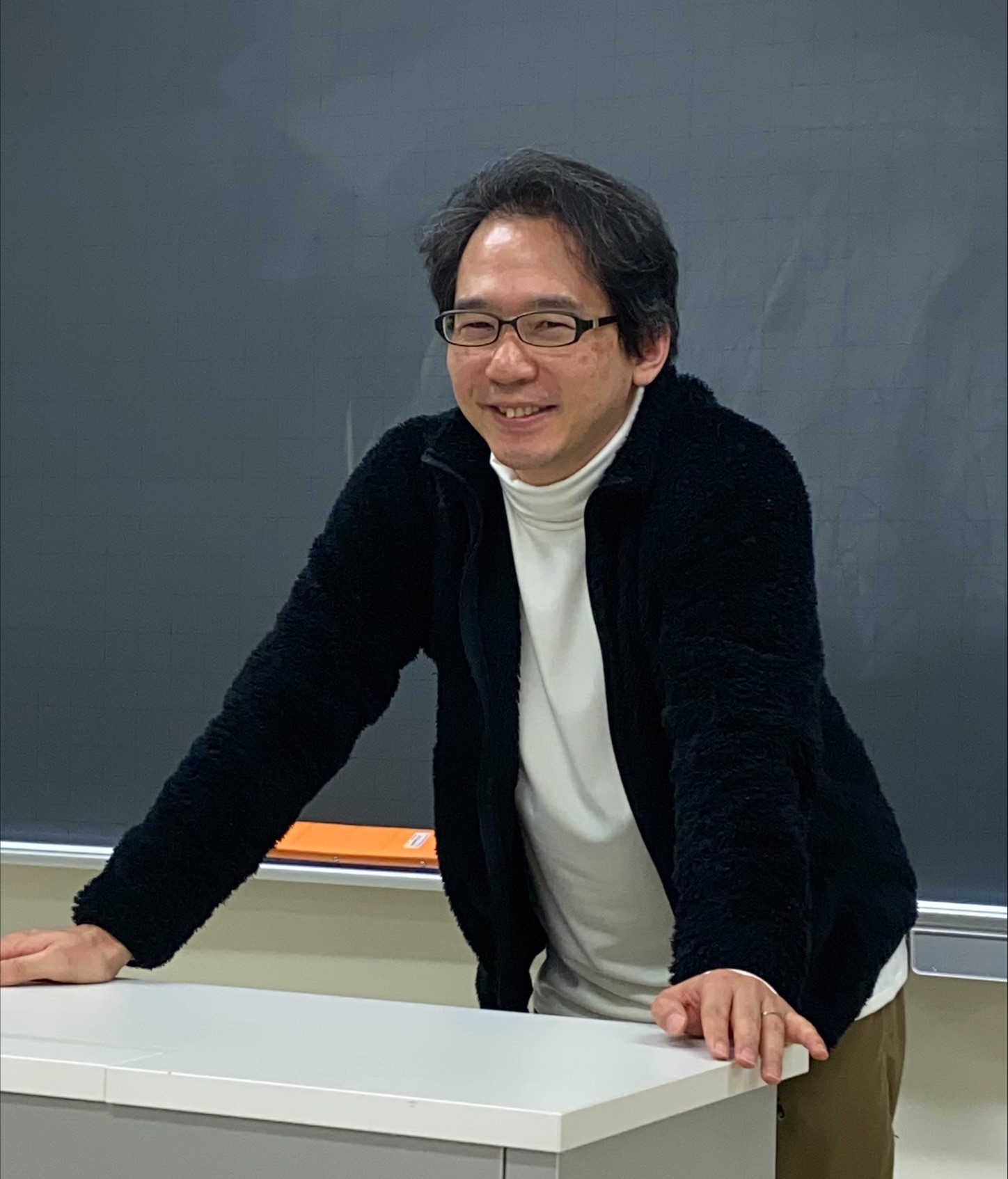
山田和大 やまだ・かずひろ (尾道市立大学)
尾道市立大学芸術文化学部日本文学科准教授。広島大学大学院文学研究科博士課程後期を単位取得退学後、広島県立高等学校教諭等、広島県教育委員会指導主事を経て現職。文学研究における知見を国語科の授業づくりにどのように生かせるかということを中心に、文学研究と教育研究のよりよい関係性を探っている。博士(文学)。

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の
リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い
平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。
教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。
ぜひご利用ください。