
室田 健善 (崇徳高等学校)
2021年04月08日

古文作品について興味を持たせる。そのために固定観念とは違う視点から古典作品を読むことにより、作品の面白さ、視点を変えてみることの大切さに気付かせる。
1.「ありがたきもの」を現代語訳する─文法事項の定着を図り、単語の学習を印象深くする
高校1年生に、まず「ありがたきもの」を適切な現代語に訳させる。普段の授業で文法事項(用言・助動詞)の反復学習をしており、この単元においても文法事項を確認、単語の学習をしながら現代語訳していく。単語の学習は語源を学習し、類義の単語を知ることで単語の意味が印象に残るような学習活動にする。例えば「珍しい」という意味を持つ古文単語を調べるという宿題を出し、生徒に発表させた。すると「ありがたし」「めづらし」「くし」「まれなり」「けうなり」などの単語が出てきた。文章でよく使われる「ありがたし」「めづらし」について取り上げた。「ありがたし」の語源は「有ることが難しい」で、「珍しい」という意味となる。「めづらし」は「愛づ」に形容詞を作る接尾語「たし」がついたもので、「賞賛する・珍重することはめったにない」という意味から「珍しい」という意味となることを説明した。また「まれなり」「けうなり」も取り上げた。ほかの単語においても単語の理解を深めるように工夫している。
2.『枕草子』について調べ、どのような作品かを学習する
「ありがたきもの」を読んだ感想を書かせる。そして『枕草子』という作品について、また『枕草子』がなぜ書かれたのかということを調べるという宿題を課す。授業の中で情報機器などを用いてグループで調べて発表するという方法も考えたが、コロナ禍での感染予防の観点と時間の短縮のため宿題にして調べてもらった。『枕草子』の成立年代や約300の章段からなること、類聚的章段・日記的章段(回想章段)・随筆的章段について説明を書いていた。生徒が書いたものを整理し、『枕草子』という作品について学習した。
3.『枕草子』が書かれた背景について学習し、『枕草子』がなぜ書かれたのかということについて視聴覚教材も使用しながら調べたものを考察する
生徒は最初『枕草子』が定子に向けて書かれたものである、ことを知らなかった。まず藤原兼家から道隆・道長から伊周や定子、彰子の系図を書き、人物関係について確認する。
また清少納言は中宮定子に、紫式部・和泉式部は中宮彰子に仕えたことや当時のサロンについて説明する。そして『枕草子』の誕生を扱った映像を教室で視聴し、生徒が調べた『枕草子』が書かれた意図を全員に紹介した。
そのなかに、定子をなぐさめるために書いた文章である、紫式部に対抗するために書いた文章である、日記的章段が中関白家(道隆家)の歴史的な記述であるというものがあげられた。そして全員に作者が『枕草子』を書いた意図は3つのうちどれかについて根拠とともに考えさせ、発表させた。紫式部に対抗するために書いたという考えにたった生徒は、定子とのやりとりを書くことで、彰子のサロンより優れていることを示したかったのではないかと発表した。また、中関白家の歴史的記述であるという考えにたった生徒は、日記的章段が中関白や定子のすばらしさを書くことにより、中関白家の栄華を書き残したかったのではないか、という意見を発表した。
大半の生徒が賛同したのは、定子のために書かれたという考えである。これは定子の兄である伊周、隆家が権力争いに負け、衰退し定子はつらい状況にあった。その時に敵のスパイと疑われ自宅に引きこもっていた、文を書くのを好む清少納言に白紙の紙を送る。清少納言は失意の中にある定子のために文章を書き、それを定子に贈る。定子は山吹の花びらに「言はで思ふぞ」と返事をする。この歴史的な背景を知り、定子のために書かれたという考えに賛同したようである。このようにして生徒の解釈が大きく変わったのである。
『枕草子』は「をかしの文学」といわれ、『源氏物語』は「あはれの文学」といわれる。定子を励ますには主観的でしみじみした情趣を表す「あはれなり」を使う内容ではなく、客観的で知的好奇心をくすぐる情趣を表す「をかし」を使う内容のほうが定子をなぐさめるには効果的だったからではないか、ということまでふみこむことができた。
4.『枕草子』の解釈がどのように変わったか、という生徒の感想
●作者の人物やものごとを鋭くとらえる観察眼と高い文章力という印象から、作者の定子に対する思いを知り、さらに文章から作者の温かい心を感じるようになった。
●視野が広がったことで、違った作品であるかのような感じになった。
●普段は気にならないような部分も気にして読むようになった。
おわりに
少ない時間だったが、授業の感想で、「視点が180度変わった。」「ほかの章段を読みたくなった。」という意見が多数あり、目標はある程度、達成できたと思う。しかし、解釈についてもっとディスカッションして学びを深めることができればよかった。
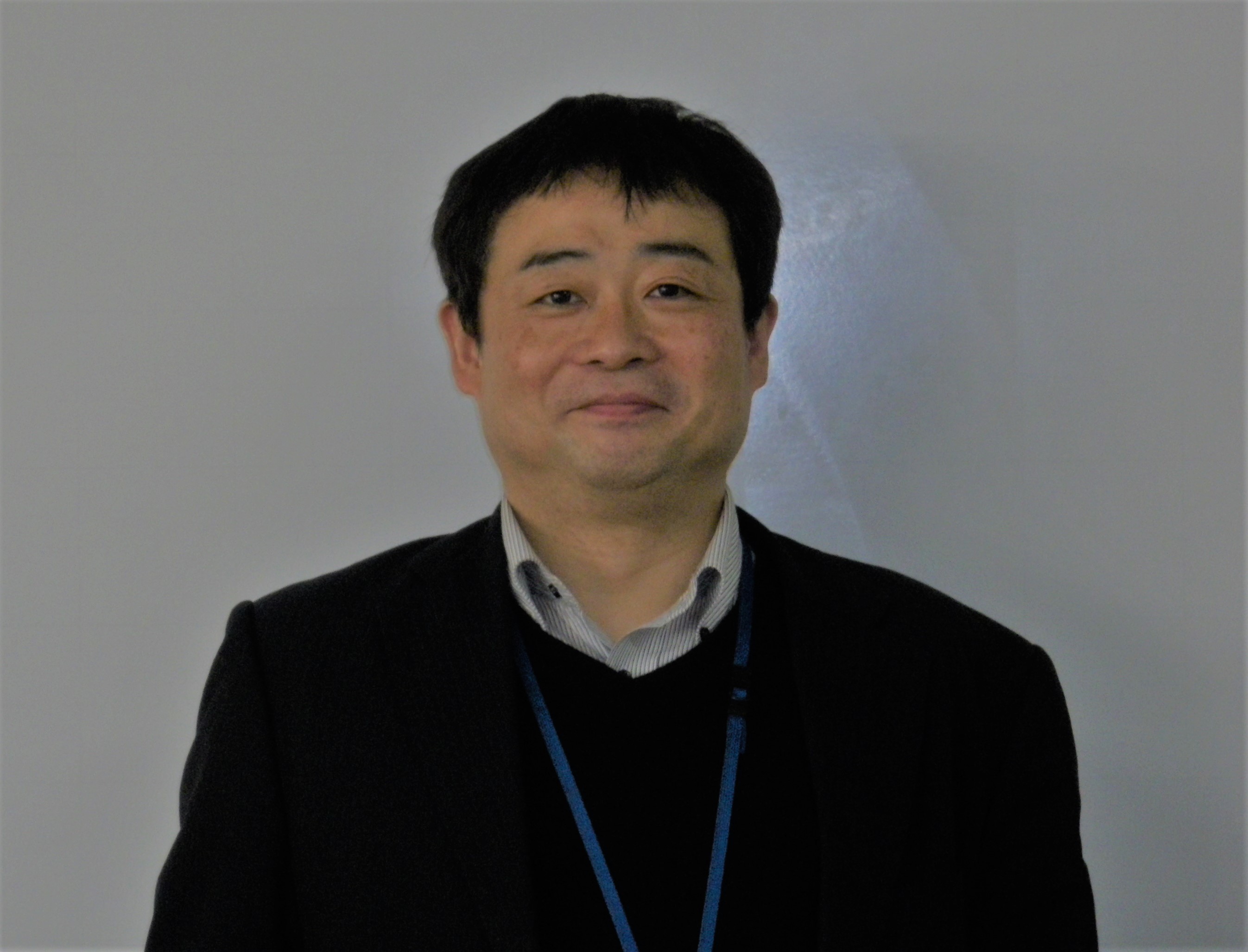
室田 健善 むろた・たけよし (崇徳高等学校)
崇徳高等学校専任教諭。大学での専攻は近代文学。古典の授業も得意としている。教育相談に携わり、生徒との触れ合いを大切にしている。

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の
リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い
平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。
教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。
ぜひご利用ください。