
浅野 雄大 (神戸市立須磨翔風高等学校)
2025年10月02日
1.はじめに
卒業後、生徒は自分自身で学んでいかなければいけません。そのような思いから、現在「個別最適な学び」の考え方を授業に取り入れています。学習内容そのものを学ぶことももちろん大切ですが、同時に「学び方を学ぶ」ことも必要だと考えます。「個別最適な学び」を通じて、生徒に少しでも「自ら学ぶ」経験をして欲しいと考えています。今回はその取り組みの様子をご紹介させていただきます。今まで地道に積み上げてきた実践を、生徒の実状に合わせて少しずつ最適化している状況です。まだまだ発展途上の取り組みですが、少しでも先生方の授業づくりの参考になれば幸いです。
2.授業の流れ
現在私が担当している高校3年「英語コミュニケーションⅢ」を例に、授業の流れを紹介させていただきます。私の授業では、教科書の各パートを3回ペースで進めています(例:Lesson 1 Part 1を3時間で完了。Lesson 1 Part 4までを計12時間で完了して一つのレッスンが終了)。内訳としては「1回目:内容理解(インプット)」「2回目:音読・暗唱(インテイク)」「3回目:発話(アウトプット)」です。そして一つのレッスンが完了したタイミングで、まとめの活動として「発表」や「やりとり」へとつなげます。
以下、これらの活動の中で「個別最適な学び」の要素が入っている箇所に★印をつけています。生徒の学びの様子が少しでも伝われば幸いです。
★…「個別最適な学び」の要素が入っている活動
2-1.内容理解(インプット)
★(1)英単語小テスト(帯学習) [10分]
①チャンツで発音確認
*ペンでリズムをとりながら交互に発音。教師⇒生徒。
②日→英で意味を覚える
*声に出す、書く、黙読など覚え方は各自で選択。
③ペアクイズ
*クイズの出し方は掲載順、ランダムなど各自で難易度を設定。
④小テスト
⑤ペアで相互採点
*復習を兼ねて、単語帳で確認して採点。コメントやイラストでお互いにフィードバック。
★(2)1分間プレゼン(帯学習) [10分]
①「今日のお題」に関する画像・表現をタブレットで検索
*例:Who is your favorite person?
②1回目:ペアで1分間英語を話す
*タブレットで画像を見せながら。聞き手はワードカウンターで語数確認+質問・相槌。
③「言いたかったけど言えなかった表現」をタブレットで検索
*調べた表現を用紙に記入。今後使えるように必ずメモをしておく。
④2回目:ペアを変えて、調べた表現を使いながら2回目に取り組む
*あらためて「言いたかったけど言えなかった表現」をタブレットで検索。用紙にメモ。
⑤Wordの音声入力機能を使用し、タブレットに向かって発話
*文字として記録。発話内容・語数・発音などの見える化。
⑥Teams内の個人フォルダに保存
*毎回保存して、発話の伸びを確認。
(3)本文の導入 [3分]
①教科書の内容に関する発問・クイズ
②ペアで話し合い・予想
*答えは伝えずに、その後の活動を通じて自分で気づけるように。
★(4)ディクテーション [5分]
①タブレットで教科書のQRコードを読み取り、各自で本文のディクテーションを行う
*同じ箇所を何度も聞き直す、通しで聞く、など方法は各自で選択。
②終了後、ペアで内容共有
③教科書で内容確認
*音声と文字の結び付け。
★(5)新出単語 [7分]
①ペアで新出単語の発音を予想
②タブレットで教科書のQRコードを読み取り、各自で発音確認
*発音をメモしながら確認。
③全体で発音確認後、チャンツで発音練習
*ペンでリズムを取りながら交互に発音。教師⇒生徒。
④ペアで発音練習
*ペンでリズムを取りながら交互に発音。生徒⇒生徒。
⑤日→英で意味を覚える
*声に出す、書く、黙読など覚え方は各自で選択。
⑥ペアクイズ
*掲載順、ランダムなど各自で難易度を設定。
★(6)長文読解 [5分]
①教科書のT-F問題・英問英答問題で長文読解
*英語力に合わせてワークシート、辞書、タブレット等の使用を選択。他者への相談も可。
②終了後、ペアで答えや内容を共有
*答え合わせは後回し。この後のKahoot!を通じて自分で気づけるように。
(7)Kahoot! [10分]
①今日学んだ単語や本文の内容をクイズ形式で確認
*生徒の様子や本文内容に応じて形式を変更。振り返り・理解度の確認を兼ねて。
②終了後、長文読解の答え合わせ
*Kahoot!で理解できなかった箇所をここで確認。
③本日のワークシートを写真に撮り、Teamsにアップロード
*学びの履歴として記録。正解した箇所、間違った箇所、メモなどがわかるように。
2-2.音読・暗唱(インテイク)
★(1)英単語小テスト(帯学習) [10分]
*前述の流れと同様
★(2)1分間プレゼン(帯学習) [10分]
*前述の流れと同様
★(3)音読 [15分]
①教科書のQRコードを読み取り、各自で本文の発音確認
*メモをとる、声に出すなど方法は各自で選択。
②本文の音声を確認しながら各自で音読練習
*練習方法は各自で選択。
★(4)Teams音読採点 [15分](※音読採点には、様々な学習アプリがあります)
①Teamsの音読機能を使い、各自タブレットに向かって音読。
②音読終了後、発音練習機能(リーディングコーチ)で各自キーワードの発音練習
*AIが発音を判定。お手本の音声を聞きながら合格をもらえるまで何度も練習。
③録音した音声を提出して、AIによる採点結果を教師から返却
*正確性と表現を各100点満点で採点。結果を各自で確認。間違った発音は音声で確認。
2-3.発話(アウトプット)
★(1)英単語小テスト(帯学習) [10分]
*前述の流れと同様
★(2)1分間プレゼン(帯学習) [10分]
*前述の流れと同様
★(3)リテリング [20分]
①本文の内容を絵とキーワードでまとめる
*まとめ方、キーワードの数などは各自で決定。
②個人練習
*練習方法は各自で選択。
③1回目:作成したリテリングシートを見せながら、ペアでリテリング
*ルーブリックで相互評価→フィードバック。
④修正・改善
*キーワードの追加や覚え直しなど。1回目よりも良くなるように修正・改善。
⑤2回目:修正したリテリングシートを見せながら、ペアでリテリング
*ルーブリックで相互評価→フィードバック。
(4)ライティング [10分]
①リテリングした内容を文章化
*自分で作成した絵・キーワードのみ見ながらライティング。内容理解度の確認を兼ねて。
②ペアで相互評価
*ルーブリックで相互評価→フィードバック。
★2-4.自己表現活動 [計3~4時間]
1年次:発表(プレゼンテーション)
2年次:発表→やりとり(プレゼンテーション→インタビュー)
3年次:やりとり(インタビュー)
*一つのレッスンが終わるごとに、教科書本文に関連した自己表現活動を実施。普段の授業から自己表現につながるように指導。「原稿作成→添削→練習(リハーサル)→発表・やりとり」の流れ。ここでも原稿作成方法や練習方法は生徒に委ねている。現在は3年次担当のためやりとり(インタビュー)を実施。
3.「個別最適な学び」について
私が大事にしているのが、「時間・目標設定」「選択肢の提示」「評価規準(基準)によるフィードバック」の三つです。
3-1.時間・目標設定
ただ漠然と活動を任せるのではなく、適切な時間設定や目標設定が必要だと考えます。与えられた時間に対して何をすればよいのか。その時間内で何ができるようになればよいのか。そのためにどのような教材や方法で取り組む必要があるのか。それらを自ら選択して決定することで、生徒は集中して活動に取り組むことができると考えます。
3-2.選択肢の提示
いきなり生徒に学び方を委ねるのではなく、学ぶための選択肢を教師側が提示する必要があると考えます。与えられた時間・目標に対して、どのような学び方・教材があるのかを知ることで生徒の学びの幅は確実に広がります。あらゆるリソース(教科書・ワークシート・辞書・タブレット・アプリ・友人・教師など)を活用する力を身につけることは、生徒の卒業後の学びにもつながると考えます。
3-3.評価規準(基準)によるフィードバック
生徒が主体的に学びに向かうためには、活動後のフィードバックが不可欠だと考えます。やりっぱなしで終えるのではなく、活動に対して評価規準(基準)によるフィードバックを行うことで自らの学習を客観視することができます。自分のできること・できないことを「見える化」することで、何をすべきかが明確になり、主体的に学びに向かうことができると考えます。
以上の三つを意識することで、「個別最適な学び」が生徒にとってより有意義なものになると考えます。授業中に生徒の学びや思考が止まってしまうのが一番もったいないことです。あらゆるリソースに頼りながら、その中で自分に合った学習方法・教材を選択する。それが「学び方を学ぶ」ということだと思います。3年次主任という立場もあると思いますが、今担当している生徒たちには、卒業後も学び続けられる力を身につけて欲しいと切に願っています。年次目標でもある「自律」を目指して、今後も試行錯誤を繰り返しながら日々の授業に取り組みます。
4.おわりに
偉そうに色々と書いてきましたが、私自身も日々悩みは尽きません。上手く行かないこともたくさんあります。今苦しんでおられる先生方も、現状を何とかしようともがき続けることできっと報われる時が来ると思います。「授業が変われば子どもは変わる」です。ともにがんばりましょう。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考文献
文部科学省(2018)『高等学校学習指導要領解説 外国語編・英語編』
マリヤン B. プレキシコ(1986)『ドルトンスクール方式』祥伝社
山本崇雄(2025)『「教えない」から学びが育つ 子どもが自律する教育のミライ』ウェッジ
工藤勇一(2022)『自律と尊重を育む学校』時事通信社
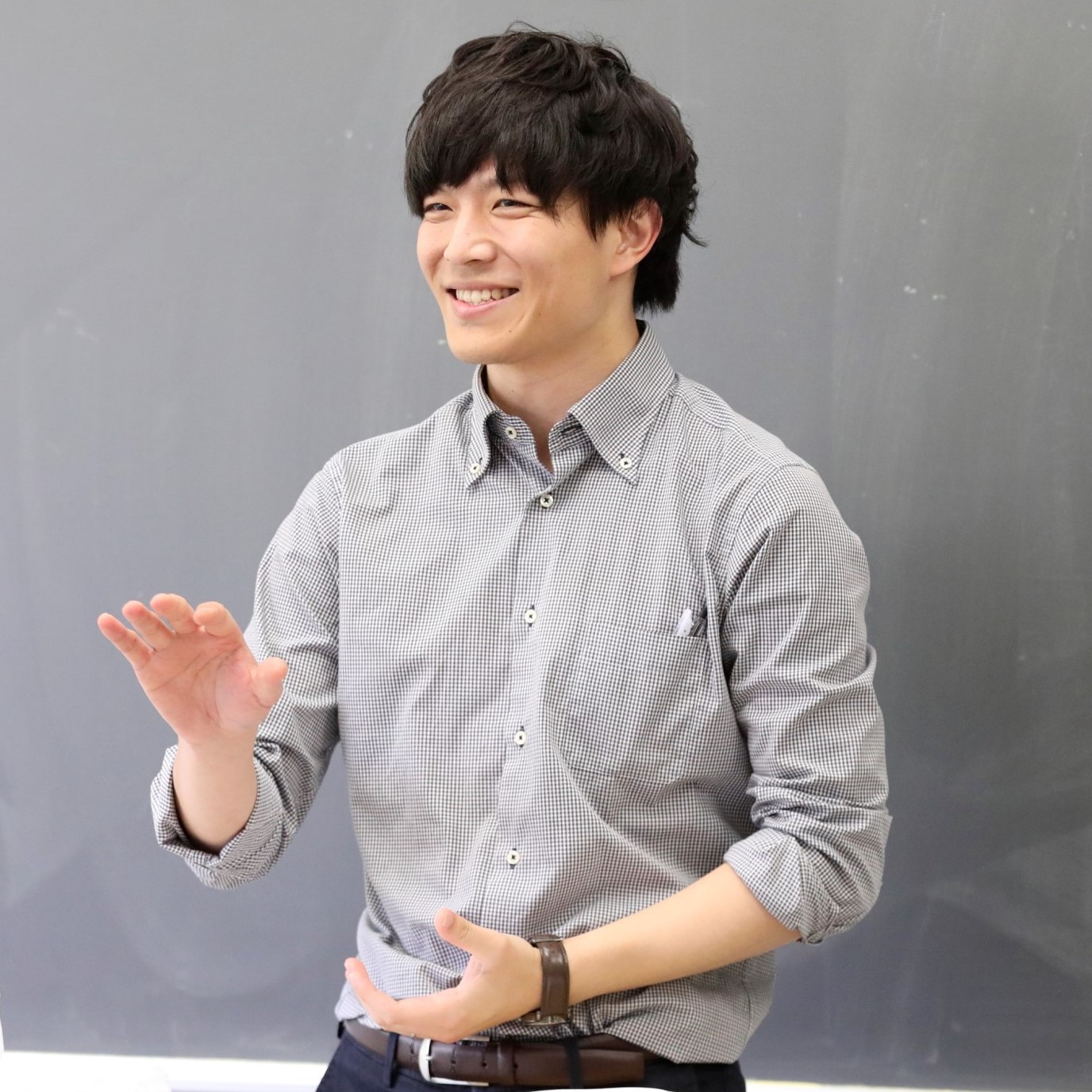
浅野 雄大 あさの・ゆうだい (神戸市立須磨翔風高等学校)
神戸市立須磨翔風高等学校主幹教諭(英語科)。同校のキャリアセンターチーフアドバイザー(進路指導部長・総合学科推進部長)を経て、現在は3年次主任および教育科主任。筑波大学大学院教育研究科修了。2013~2014 年に文部科学省・外務省主催、日本人若手英語教員米国派遣事業(デラウェア州)に参加。2019 年~2023年に Microsoft 認定教育イノベーター(MIEE)として、「英語×ICT」に関する授業実践を発信。著書に「中学校・高等学校4技能5領域の英語言語活動アイデア(明治図書出版)」。
『CROWN English CommunicationⅡ New Edition』(平成30年度版)─主体的で対話的な深い読みをすすめる「コミュニケーション英語Ⅱ」授業実践
2021年03月22日
橋詰 龍
『MY WAY English Communication Ⅱ New Edition』(平成30年度版)─「思考力・判断力・表現力」を促す具体的指導例
2020年11月24日
土屋 進一

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の
リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い
平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。
教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。
ぜひご利用ください。