
本コラムは、奥住桂先生が長年綴ってこられたブログ『英語教育2.0』をもとに、新たな視点と内容を加えて再構成していただいたものです。実践に根ざした具体的なアイデアと、英語授業への深い洞察が詰まったそのエッセンスを活かし、先生方の授業に役立つヒントをお届けします。
奥住 桂
埼玉大学教育学部・大学院教育学研究科、「NEW CROWN」編集委員
2025年10月22日
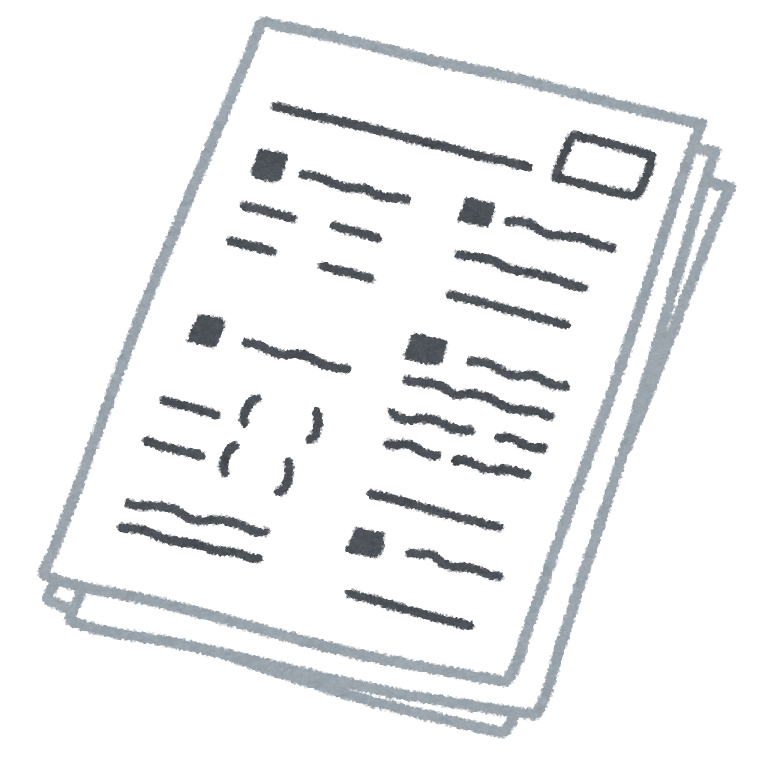
はじめに
今回ご紹介するのは、文法定着のために練習問題として取り組むプリント(問題演習用のワークシート類)の工夫です。そういう練習問題を授業で扱う場合の課題としては、
① 生徒によって取り組む時間に差がある
② 答え合わせで活躍する生徒がいつも同じ
といったものがあるでしょう。今回は、この2点をちょっとした工夫で解決できればと思います。
活動の手順
そこで、登場するのがこの「どっちをやっても『答え』が同じになるプリント」です。
作り方はシンプルで、例えば「関係代名詞 who」だったら、初級と上級の2種類の問題を用意し、以下のように左右に並べて一枚に印刷します。
|
関係代名詞 who ① 初級
1.名詞のかたまりを作ろう! (1) 髪の長い女の子 [ a girl / long hair / has / who ] _______________________________
(2) アメリカに住んでいる友だち [ a / lives / friend / the U.S. / who ] _______________________________
(3) 料理の上手な妹 [ can / a / cook / sister / who / well ] _______________________________
(4) 多くの人々を助けた医者 [ doctor / helped / people ] _______________________________
(5) プータンの農業のやり方を変えた男 [changed / way / farming ] _______________________________ |
関係代名詞 who ① 上級
1.名詞のかたまりを作ろう! (1) 髪の長い女の子 (has) _______________________________
(2) アメリカに住んでいる友だち (lives) _______________________________
(3) 料理の上手な妹 (cook) _______________________________
(4) 多くの人々を助けた医者 _______________________________
(5) プータンの農業のやり方を変えた男 _______________________________ |
生徒は、初級と上級の2つのコースのうち、自分でやってみたいほうを選んで取り組みます。
これだけだと、2つのレベルの問題を用意して、学習者に選択してもらうというだけのことですが、お気づきのように、「どちらをやっても答えが同じになる」というのがこのプリントの肝です。
大問1でいえば、左側の初級は (1) 〜 (3) が並べ替え問題で、(4) と (5) はヒントとなるキーワードが示されている問題になっています。一方、右側の上級では、少ないヒントをもとに問題に取り組むことになります。
他にも、左は並べ替え問題にしておいて、右は自分で1語補充して並べ替えるようにするとか、穴埋めのカッコ数を変えるとか、レベル差の付け方はいろいろあると思います。生徒の様子を見ながら適度な差をつけておくとよいでしょう。
生徒はどちらのコースで取り組むかを自分で決め、プリントを半分に折って、取り組む側だけを見ながら解答していきます。
使い方と作り方の工夫
メリットとして考えられるのは、まず同じ時間でもそれぞれの生徒に合った負荷がかかるので、クラス内の生徒の作業進度をある程度整えられるということです。そして、答え合わせの時は全文を答えさせれば、実はその生徒がどっちのコースをやったかは問題にならない(他の人にはわからない)というのも大きなポイントです。
そして授業後には、生徒の手元にもうひとつ「問題」が残ります。特に、授業で初級に取り組んだ生徒にとっては、ちょっとだけ難しくなった問題に、あとで(家庭で)もう一度チャレンジできますから、テスト勉強などにも活用できるわけです。「解答」は、左側に載ってますしね。
さらにこのプリントには、実は「中級」の問題も存在しているんです。ふだんは左側の初級をノート等で隠しておいて、つまずいた時だけヒント代わりに左側をちらりと覗きながら、右側の上級の問題に取り組む、というコースです。
でも、問題を2種類も用意するなんて、大変でしょう?
いいえ、それほどでもありません。先に初級の問題を作ってから、それをコピー&ペーストして、カッコを増やしたり、選択肢を消したりとちょっと手を加えるだけでいいので、慣れればふだんのプリント作成の1.25倍くらいの時間があれば作れるようになります。2枚分作るからといって2倍かかるわけではありません。
おわりに
こういった工夫で、生徒がそれぞれのレベルに合った問題に取り組むことができるようになり、なおかつ、どのレベルの問題を解いた生徒も平等に(むしろ苦手な生徒にとってはこれまで以上に積極的に)答え合わせにも参加できるようになる、と期待しています。
今どきであれば、デジタル端末で2種類の問題にチャレンジできるようにすることもできますが、個人的には、プリントを折るとか、ひっくり返すみたいなアクションも、授業のメリハリになるかなと思っています。ですので、まずはアナログに紙でやってみるのをオススメします。どうぞお試しください。
ブログ元ネタ:『どっちをやっても「答え」が同じになるプリント』(2012年2月28日)https://anfieldroad.hatenablog.com/entry/20120228/p1

奥住 桂 おくずみ・けい
・千葉県野田市生まれ
・獨協大学外国語学部英語学科卒業、埼玉大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学
・埼玉県公立中学校教諭、帝京大学、埼玉学園大学を経て、現在埼玉大学教育学部・大学院教育学研究科准教授
・最近の関心は「ゲーミフィケーション」と「演技」
・このところラーメン派から蕎麦派になりつつある自分に驚き

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の
リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い
平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。
教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。
ぜひご利用ください。