
本コラムは、奥住桂先生が長年綴ってこられたブログ『英語教育2.0』をもとに、新たな視点と内容を加えて再構成していただいたものです。実践に根ざした具体的なアイデアと、英語授業への深い洞察が詰まったそのエッセンスを活かし、先生方の授業に役立つヒントをお届けします。
奥住 桂
埼玉大学教育学部・大学院教育学研究科、「NEW CROWN」編集委員
2025年09月10日

はじめに
いわゆる「ビンゴゲーム」って個人的にはあまりやってきませんでした。書いて、聞くだけだと単調になりがちだし、準備や実施に時間がかかるし、宿題にしてやってこない生徒がいるとテンション下がるし…。
いや、ビンゴ自体はこれまでにも多くの実践が積み重ねられているので、指導を徹底して、ちゃんとしたやり方でやれば、育つ力はあるんだろうとは思いますが、何かもう少しアレンジができれば自分好みになるのにな、と考えてみたのが、こちら「VSビンゴ」です。
ふつうのビンゴは「聞くこと」がメインの活動で、音と文字を高速でつなげる練習です。「ビンゴする」という偶発性(ギャンブル性?)に刺激されながら、苦手な生徒でも楽しんで参加できる活動です。でも、やっぱり聞くだけっていうのがもったいないな、と感じていました。そこで、ペアでお互いに単語を言い合う形のビンゴにしたらどうだろう、と考えてみました。
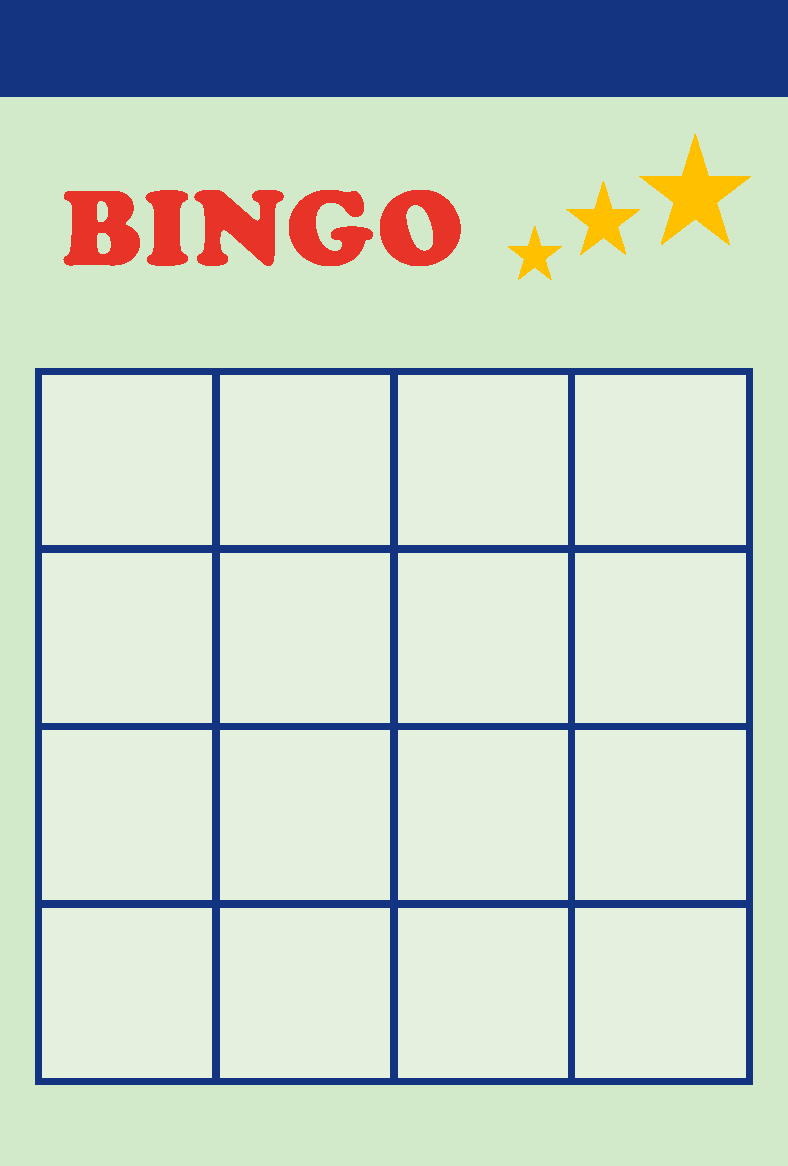
活動の手順
1.普通のビンゴと同じように4×4のマス目に単語を埋めていきます。
2.用意ができたら、ペアを作り、じゃんけんをします。
3.勝った生徒から交代で1つずつ単語を読み上げます。
4.相手が読んだ単語が自分のシートにあれば、消します。
(※自分が読んだときは、自分のシート上の単語は消さない。)
5.交代で1つずつ繰り返し、相手のシートの上で1列そろった方が勝ちです。
(※自分のシートの上でビンゴになったら負けです。)
つまり、「相手のシート上の並びを予想して、単語を読み上げるビンゴ」なんです。生徒たちは、こちらから何も言わなくても、ピンチになると勝手に「やべぇ、リーチだぁ」などと言って盛り上がっています。お互いに「この単語は読み上げられませんように」と心で祈りながら、ゲームを続ける不思議な面白さがあります。
意外な効能
この活動をやってみて気づいた生徒の変化は、「自分で単語を読まなくてはならないので、活動前の発音練習をしっかりやるようになる」ことです。読める単語(=相手を攻撃する道具)が少なくなると不利ですもんね。これは意外な(でもとても大きな)効能でした。みんな、ゲームを楽しみたいなら、頑張るんですね。(ちなみに、本当に読めない場合はスペリングを言うのを認めるのもアリでしょう)
また、このやり方だと、例えば単語を書いてくる宿題を忘れた生徒がいた場合でも、とりあえず3つだけ単語書かせて、その3つが読まれたら負け!とかにすれば、すぐにゲームに参加できるのもいいですね。
仕組みとしては、いわゆる「宝探しゲーム」とか「バトルシップ」みたいなゲームと同じで、ただのパターンプラクティスではあるんですけど、教科書に出てくる単語なんかをうまく組み込んで、ゲーム形式で楽しみながら何度も触れられるなら、結構いい活動なんじゃないかなと思います。(教師が前で読み上げるより、明らかに生徒の活動量が増えます!)
おわりに
このコラムでは、割とこういうゲーム的な反復練習のようなものをご紹介していますが、どうも最近巷で共有される実践が〔思考・判断・表現〕系の発展的で、複合的な活動に偏っているように感じています。もちろんそれも大切ですが、こういう地味な、〔知識・技能〕を定着させる、その手前にあるような活動も大きな意味があると思います。そうした実践も、こちらで共有していきたいなと思っています。
ブログ元ネタ:『VSビンゴ』(2005年11月17日)https://anfieldroad.hatenablog.com/entry/20051117/1132180060

奥住 桂 おくずみ・けい
・千葉県野田市生まれ
・獨協大学外国語学部英語学科卒業、埼玉大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学
・埼玉県公立中学校教諭、帝京大学、埼玉学園大学を経て、現在埼玉大学教育学部・大学院教育学研究科准教授
・最近の関心は「ゲーミフィケーション」と「演技」
・このところラーメン派から蕎麦派になりつつある自分に驚き

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の
リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い
平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。
教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。
ぜひご利用ください。