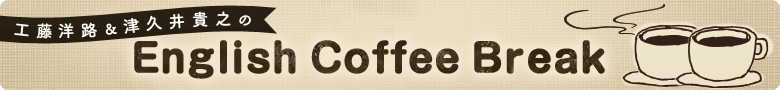
工藤洋路,津久井貴之
玉川大学,お茶の水女子大学附属高等学校
2018年10月01日
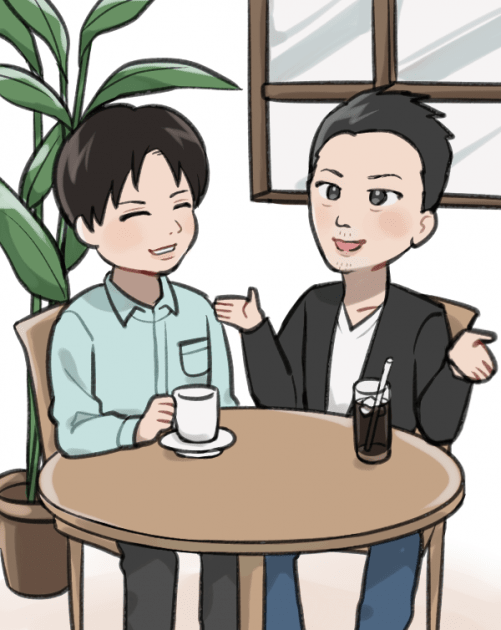
津久井
さて,第14回も,前回に引き続き,小学校英語のお話をしていきたいと思います。では,工藤先生,お願いします。
工藤
津久井さんも一緒に話してよ(笑)。
前回話したこと以外だと,小学校英語について思っていることの1つに,臨界期仮説があるんだ。
津久井
臨界期仮説。
工藤
うん。第二言語習得論を学ぶと必ずと言っていいほど出てくる臨界期仮説だけど,「10歳くらいを臨界期と呼んで,その年齢を過ぎてから新しい言語を学ぶと,ネイティブ・スピーカーのレベルには達しない」というものだよね。この説には反証もあるし,提唱されてから長い時間が経った今でも仮説のままだけど…ただ,一般的な感覚として,「早いに越したことはない 」というようなものはあるよね。
2020年からは正式に小学校3年生から外国語活動がスタートする,つまり,臨界期の手前の8歳から外国語学習が始まるね。
津久井
たしかに!
工藤
臨界期仮説では,臨界期を過ぎて新しい言語の学習をスタートすると,とくに音声面のスキルが伸びづらいということなので,8歳から学び始めると発音やリスニングの能力が伸びることが期待できるかな,ということなんだろうと思う。でも,現在の小学校の授業を見学すると,発音の指導があまりされていないことが多いんだよね…。
津久井
中学校の先生方と話していても,「小学校で外国語の学習経験があっても,やっぱり発音がちょっと…」という声はよく聞くね。
工藤
そうだよね。
まぁ,臨界期仮説は別にしても,大人より小学生のほうが音を再生する力があると思うから,小学校での発音指導は優先してやったほうがいいんじゃないかと思うんだけど。
自分が見た授業は,「自分の町紹介」っていう言語活動をカタカナ英語でやっていて…。小学校で使う語彙はカタカナになっているものが多いから,どうしても発音がカタカナになっちゃって,クラスでは日本人しかいない環境だから通じているけど,「この英語で本当に大丈夫?」って思うときもある。
フォニックスやチャンツもやってはいるんだけど,コミュニケーションの場面になかなか生かされていないっていうのが,「惜しいなぁ」と感じてしまう。
津久井
これからは,外国語活動は3年生から始まって,5・6年生では教科になるから,発音の教え方も本格的なものに変わっていくのかもしれないけどね。
工藤
期待したいね。
津久井
うん,期待はする。
けどね,小学校英語のメリットである「臆しないでペアワークができる」とか,「恥ずかしがらないで人前で話せる」とか,そういうことは認めていいんだけど,全部をそのまんまふわっと受け入れるべきじゃない,とも思っていて。「直すべきところは中学校でしっかり直す」というか,その代表が音声面なのかな,と思っているんだけど。
工藤
確かに,中学校で改めてしっかり指導しようっていう発想も大事かもね。
津久井
うん,でね,そのためには,「小学校で何を経験しているか」を知っていることがすごく大事。
小学校で,どの部分がしっかり身についているのか・身についていないのかを知らないまま一から全て始めるのではなくて,「ここは小学校でたくさんやってきていて,確かによくできている,だからこの先から入ろう」「逆に,あんまり指導されていないようだから,これまでの中1同様に導入しよう」って生徒の状態を見てフレキシブルに判断することがこれからの中学校の先生に求められると思う。
だから,今までの中1の指導がうまいっていうのでは通用しなくて,新しい中1の指導のうまさを作っていかなくちゃいけない。英語の授業は今までのように中学から始まるものではないから。
もしも,津久井先生が中1を担任したら
工藤
ちなみに,津久井さんが中学1年生の担任を任されたら,1時間目,どうする?
津久井
そうだな…,うーん…。
ええと,前提として,ほとんどの中学校では,一つの小学校の児童がそのまま進学してくるってことはまずないから,クラスの中に英語の好き嫌いや,学習の履歴もバラバラな生徒たちが混じっているわけですよね。
工藤
そうだね。
津久井
だからまず,その把握から始めなくちゃいけないよね。どんなことをやって,何を面白いと感じてきたのか。
例えば,自分なら,”my favorite English words”とか”my favorite English activities”をテーマにして,show and tell式に3分くらい話してみる活動を設定するかな。楽しかった活動を絵で書いてもいいし,小学校のとき先生にもらったカードを見せたり,歌を歌ったことが楽しかったなら,同じ小学校から来た生徒たちで前に出て歌を歌ったり。
工藤
中1の初めならやってくれるかも。
津久井
そうだよね。
それで,そのあとに,日本語でもいいから,「この活動のときにALTの先生がこんなふうに話していた」とか,「好きな教科の単語はこれ」みたいな対話があると,教師も学習履歴を把握できるじゃない。
アンケートとかも考えたんだけど,小学校の学習経験がactivityベースなんだから,中学校になった瞬間に中学校式にならなくてもいいのかなって思ったんだよね。
発達段階もあるから,いつまでも小学校と同じ雰囲気で歌は歌ってくれないけど,中学1年の初めならではの活動だし,こんな形で生徒同士もお互いのことを知れたら楽しかな,と。それに何より,先生がそれを把握できる。
工藤
本当は,地域の小学校を先生方が自分で見に行けるのが一番だけど,現実的にはなかなか大変だからね。
津久井
そこを織り込んでしまうのは,現実的には厳しい気がする。だからってわけではないけど,生徒自身に学習履歴を見せてもらえたらって,思って。
それで,その活動のあとに,自分が話したフレーズとか似た活動が教科書のどこにあるか探してみようなんてすると,教科書を開くきっかけにもなるかなって。
工藤
実際に見に行くのは難しくても,小学校の先生に6年生最後の発表活動をビデオで撮影してもらって,それを中学校の先生に渡すだけでも,児童(生徒)の学習履歴の最後の部分は共有できると思う。撮影して動画を渡すだけだから,それほど大変な作業ではないと思う。こんな感じで,簡単なことからでも学習履歴の共有を何か始めていければよいね。
|
※この連載は,お二人のざっくばらんなおしゃべりを企画化したものであり,工藤先生・津久井先生の公式発表ではありません。 |
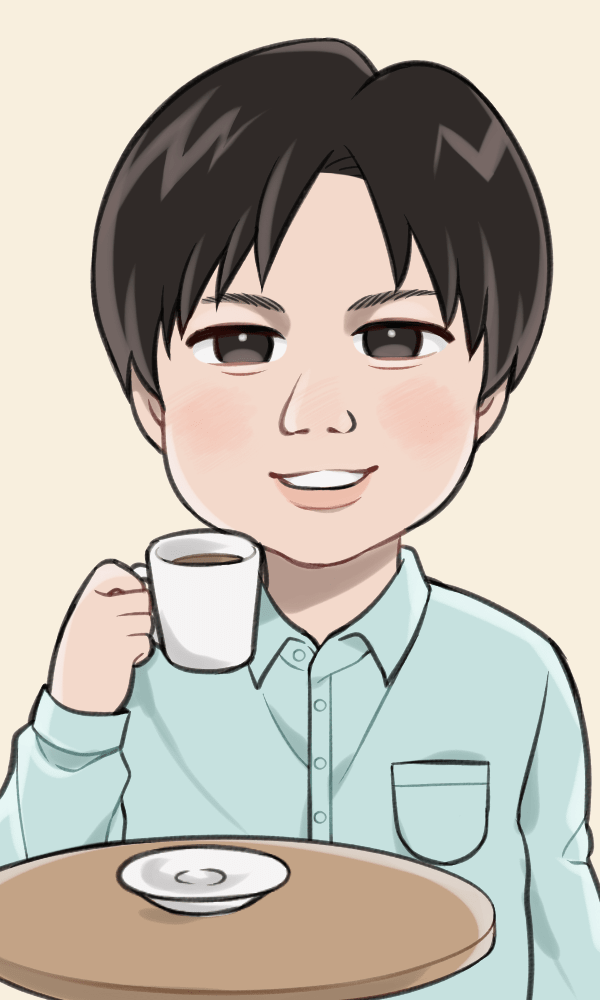
工藤洋路
くどう・ようじ
玉川大学,「NEW CROWN」編集委員
・1976年生まれ
・東京外国語大学外国語学部・同大学院博士課程前期・同大学院博士課程後期修了(学術博士)
・日本女子大学附属高等学校教諭等を経て,現在玉川大学文学部英語教育学科准教授
・高校教諭時代に担当した部活動は,陸上部
・カフェでよく注文するのは,カプチーノやフルーツジュース
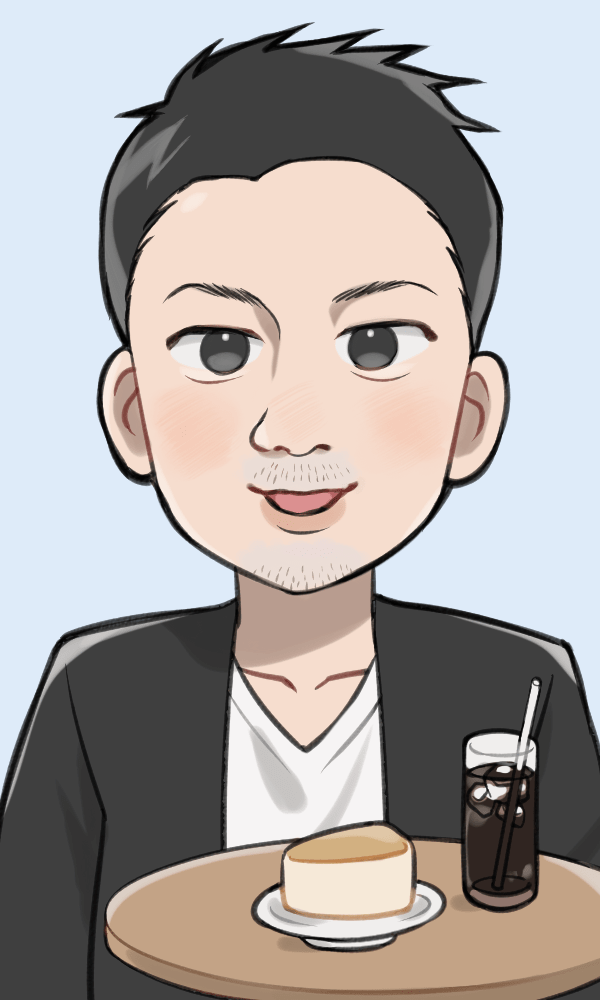
津久井貴之
つくい・たかゆき
お茶の水女子大学附属高等学校
1974年生まれ
・群馬大学教育学部・同大学院修了
・群馬県内の公立中高一貫校教諭等を経て,現在国立お茶の水女子大学附属高等学校教諭
・指導のモットーは,固定観念にとらわれずにチャレンジしていく
・カフェでよく注文するのは,ニューヨークチーズケーキとコーヒー

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の
リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い
平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。
教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。
ぜひご利用ください。