|
��֗��n�����u���w�v�Q�l���̃x�X�g�Z���[�B���ȏ��̈ꎚ���ɗ��_�I�ȉ�����������A�����Ƃ��ڂ����Q�l���B�w���w�T�E�U�̐V�����x�̓��e��S�ʓI�Ɍ������A�啝�ȑ��y�[�W�i48�y�[�W�j���s�����B�_�q�E��ɖ𗧂u�T�C�G���X�{�b�N�X�v��43�e�[�}���₵202�e�[�}�Ƃ����B�V�ے��ŁB�i�u���w��b�v���^�j�Q�F���B
���u���w�̐V�����v��������w�V���́u�������ߎQ�l���i���w�j�v �Q���̂����̂P���Ɏ��グ���܂����i2014�N9��9�����j�B
�y�Љ�z �u�[���m���⌻�ۂ̔����@�\��������A�ǂނ����ɉ��w�ւ� �������[�܂�܂��B���K�ƕ��s���ēǂށA���邢�͎����Ƃ��� �g���̂��ǂ��ł��傤�v
   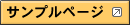
|
| *�u�T���v���y�[�W�v�͉摜�t�@�C���ŕʉ�ʂɕ\�����܂��B |

�m�� �g�f�搶�̂ق��̒���
 ���n��w�� ���w�̐V���K
���n��w�� ���w�̐V���K
 �Z���^�[�����E���n��w�@���w�̐V�W�����K
�Z���^�[�����E���n��w�@���w�̐V�W�����K
 �Z���^�[�����U���@���w��b�̑����K
�Z���^�[�����U���@���w��b�̑����K

�����ҏЉ�
 �m��
�g�f �i����� �悵�̂ԁj �m��
�g�f �i����� �悵�̂ԁj
�m�����n
1956�i���a31�j�N�@�ޗnj����܂�B
���s�����w�@���C���w�ȑ��ƁB
�ޗnj�����K�������w�Z�A�ޗǍ����w�Z�A���T�����w�Z���o�āA���݁A���������w�Z���@�B
�m�����n
�w���w�̐V���K�x �i�O�ȓ��j�w���w�̐V�W�����K�x �i�O�ȓ��j�w�Z���^�[�����U���@���w��b�̑����K�x�i�O�ȓ��j�ق�

���͂��߂�
�@��w�����Z���^�[�����̓����Ȍ�A�u��w�����̓����͊m���ɓ���Ȃ��Ă���A���͂�A���ȏ���s�̂̎Q�l���ł͂ƂĂ��Ή�������Ȃ��B�v�Ƃ������k�����̐����悭���ɂ��܂��B��ʂɓ�ւƂ���Ă����w�̓����ł́A���Z�ł̊w�K�͈͂����Ȃ蒴������w���{���x���̖�肪�A���C�ŏo�肳��܂��B���̂悤�ȑ�w���߂����āA����w�ɐ��サ�Ă��鍂�Z��������N�̒m�I�v�������A���̎u�]�����Ȃ������邽�߂ɏ����ꂽ�̂��{���Ȃ̂ł��B
�@���݂̍��Z���ȏ�������̎Q�l���ɂ́A�����̉��w���ۂɑ���ԗ��I�Ȑ����͈ꉞ�Ȃ���Ă��܂����A����ɂ�������˂����u�Ȃ������Ȃ�̂��H�v�Ƃ������k�����̑f�p�ȋ^��ɂ͂قƂ�Ǔ������Ă͂��܂���B���҂́A���N����̃v�����g�����g���Ď��Ƃ��s���Ă��܂������A���k�����̔M�S�ȗv�]���A���N���Ď��M�ɒ��肵������ł��B
�@�{���̓����́A���ȏ��{���̈ꎚ����O��I�ɏڂ��������E����������Ƃł���A�ӂ��̎Q�l����1.5�{���炢�̃y�[�W��������Ă��܂��B�܂��A�����܂ł����e�d���̕��j���т��A�܂Ƃ߁E�o�����E�����Ȃǂ̗��͋ɗ͏Ȃ��A���̕��̃y�[�W���͂��ׂĉ���ɂ��Ă܂����̂ŁA���e�̐[�܂�͑��̎Q�l���̂Q�{�ȏ�͂���Ǝv���܂��B���̂��ߖ{�����g���Đ^���ɕ�����A�m�炸�m�炸�̂����ɉ��w�S�̂ɑ���[���m�����g�ɂ��A�����Ə����̖ړI���B������邱�Ƃ͖��_�̂��ƁA����ɁA���N����w�i�w�����Ƃ��A�{�������Z�̉��w�Ƒ�w�̉��w�Ƃ̉˂����̖������ʂ����Ă��邱�ƂɋC������邱�Ƃł��傤�B
�@�{���́w���wIB�E�U�̐V�����x�w���wI�E�U�̐V�����x���o�āA���ʂ̐V����ے����{�ɔ����A�w���w�̐V�����x�Ƃ��ĐV���ɔ��s������̂ł��B����܂ő����̋M�d�Ȃ��ӌ��A���������������������A�搶���ɐ[������\���グ�܂��B
�@�܂��{���͎������łȂ��A���w��{�i�I�Ɋw��ł�����w�Z���◝�Ȃ̋��E���߂����Ă���w�����N�A����ɓ������狳�Ȏw���ɓ���ɂ߂Ă����鑽���̍��Z���w�̐搶���̎w��������Ƃ��Ă��𗧂��Ƃ��m�M���Ă���܂��B
�@�Ō�ɁA�{�����\���Ɋ��p�������̖ړI��B������邱�Ƃ�S���F�O����ƂƂ��ɁA����܂œ��l�A�����̕��X�̂��x���Ƃ����ڂ�����܂��悤���肢�\���グ�܂��B
2013�N2��
�m���g�f

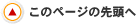
���M�҂̂ЂƂ���
�@�u�w��ɉ����Ȃ��v�Ƃ悭�����܂��B���ɂƂ��ĉ��w�̉����Ƃ́A�܂����ȏ��̓��e�����S�Ƀ}�X�^�[���邱�Ƃł��悤�B���������ȏ��ɂ́A���w��"��"�ƂȂ�K�v�ŏ���̂��Ƃ��������Ă���܂���B�{���́A�����"��"�ƂȂ�����J�ɂ������̂ŁA�ǂ�ł��������ɁA���̓��e�ɂǂ�ǂ�������܂�Ă�������s�v�c�ł��B
�@�l�ԂɂƂ��āA���͌ǓƂŋꂵ�����̂ł��B��������z���A�{���̎��͂����邽�߂ɂ́A�Ǐ��ɏo��A�������������ƍ��𐘂��ēǂݍ��ޕK�v������Ǝv���܂��B�u����A���w�ɓO���v�Ƃ�����������܂��B����͎��̗��܂Ō��ʂ��قǂ̊�͂ŏ�����ǂ߂A�����Ƃ��̐[���Ӗ����킩��悤�ɂȂ�Ƃ����Ӗ��ł��B�܂��A�u��������Ƃ����y��ɂ͗��h�ȉƂ����v�Ƃ������t������܂��B�����̂��Ƃ���������ƐS�ɍ��݁A�����̂��߂ɂȂ�{���̕��𑱂��Ă����ĉ������B�ǎҏ��N�̌䌒����S���F��܂��B
���w�K������X��
�����w�́A�n����ɑ��݂���l�X�ȕ����̐����ƕω��𗝉����A���̖{���𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ���w��ł���B���݂ł́A�������̋����ɕK�v�ȕ����̂����A�H�ƈȊO�̂قƂ�ǂ̕����́A�l�H�I�ɍ������邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�������̐����͊i�i�ɖL���ɂȂ����B
��20���I�ɓ���A���w�͕����w�݂̂Ȃ炸���̎��R�Ȋw�Ɩ��ڂȊW�������Ȃ��甭�W���Ă����B�Ƃ��ɁA�����Ɋւ���l�X�Ȍ����̐��ʂ��A�s�\�Ǝv���Ă��������̖{���I�ȉc�݂̉𖾂����\�ɂ��A���w�͐����w�E��w�E��w�̔��W�ɂ��傫�ȍv�����ʂ����Ă����B
�����ʁA"�n��"�Ƃ��������n�̒��ŁA�l�Ԃ̍s�����Y�����͎����̘Q��A���̉����Ȃǂ̐V���Ȗ��������N�������B21���I���鎄�����ɂƂ��āA����܂ł̖L���Ȑ������ێ����Ȃ��玝���I�Ȕ��W�𑱂��Ă������Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B
������A���̃G�l���M�[�̗L�����p�ƒn�����̕ۑS�Ƃ����ۑ���������邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă����w�̒m���ƋZ�p���s���ł���A���̎��R�Ȋw�Ƃ̊֘A��[�߂��A�V�������w�̖����͂܂��܂��d�v�ɂȂ��Ă���B
�����̂悤�ɁA���w���w�ڂ��Ƃ��鏔�N�����ւ̊��҂͂܂��Ƃɑ傫�����̂�����A�{���ɂ���āA���w�ւ̐������A�v���[�`�̕��@���w�сA���w�ɑ���^�̗�����[�߂Ăق����B

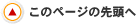
��P�ҁ@�����̍\��
�@��P�́@�����̍\���Ɖ��w����
�@�P�|�P�@�����̍\��
�@�P�|�Q�@���q�ƃC�I��
�@�P�|�R�@���w����
�@��Q�́@�����ʂƉ��w������
�@�P�|�S�@���q�ʁE���q�ʂƕ�����
�@�P�|�T�@���w�����̗ʓI�W
��Q�ҁ@�����̏��
�@��P�́@�����̏�ԕω�
�@�Q�|�P�@���q�̔M�^���Ɗg�U
�@�Q�|�Q�@�����̎O�ԂƏ�ԕω�
�@�Q�|�R�@�t�̂̏��C���ƕ���
�@��Q�́@�C�̂̐���
�@�Q�|�S�@�C�̂̐���
�@�Q�|�T�@�����C�̂Ə��C��
�@�Q�|�U�@���z�C�̂Ǝ��C��
�@��R�́@�n�t�̐���
�@�Q�|�V�@�n���̂�����
�@�Q�|�W�@�ő̗̂n��x
�@�Q�|�X�@�C�̗̂n��x
�@�Q�|10�@�n�t�̔Z�x
�@�Q�|11�@�n�t�̐���
�@�Q�|12�@�Z����
�@�Q�|13�@�R���C�h�n�t
��R�ҁ@�����̕ω�
�@��P�́@���w�����ƔM
�@�R�|�P�@���w�����ƔM
�@�R�|�Q�@�փX�̖@���ƌ����G�l���M�[
�@��Q�́@�����̑����ƕ��t
�@�R�|�R�@���w�����̑���
�@�R�|�S�@���w���t
�@��R�́@�_�Ɖ���
�@�R�|�T�@�_�Ɖ���
�@�R�|�U�@���a�����Ɖ�
�@��S�́@�_���Ҍ�����
�@�R�|�V�@�_���Ҍ�����
�@�R�|�W�@�d�r�Ɠd�C����
��S�ҁ@���@�����̐���
�@��P�́@��������f�̐���
�@�S�|�P�@���f�Ɗ�K�X
�@�S�|�Q�@�n���Q���Ƃ��̉�����
�@�S�|�R�@�_�f�E�����Ƃ��̉�����
�@�S�|�S�@���f�E�����Ƃ��̉�����
�@�S�|�T�@�Y�f�E�P�C�f�Ƃ��̉�����
�@�S�|�U�@�C�̂̐��@�Ɛ���
�@��Q�́@�T�^�������f�̐���
�@�S�|�V�@�A���J�������Ƃ��̉�����
�@�S�|�W�@�A���J���y�ދ����Ƃ��̉�����
�@�S�|�X�@�A���~�j�E���Ƃ��̉�����
�@�S�|10�@�����E����Ƃ��̉�����
�@�S�|11�@�X�Y�E���Ƃ��̉�����
�@��R�́@�J�ڌ��f�̐���
�@�S�|12�@�J�ڌ��f�̓���
�@�S�|13�@���C�I���ƍ���
�@�S�|14�@�S�Ƃ��̉�����
�@�S�|15�@���Ƃ��̉�����
�@�S�|16�@��Ƃ��̉�����
�@�S�|17�@�N�����E�}���K���Ƃ��̉�����
�@�S�|18�@�����C�I���̕����E�m�F
��T�ҁ@�L�@�����̐���
�@��P�́@�L�@�������̓����ƕ���
�@�T�|�P�@�L�@�������̓���
�@�T�|�Q�@�L�@�������̕���
�@�T�|�R�@�L�@�������̍\������
�@��Q�́@���b���Y�����f
�@�T�|�S�@�A���J���ƃV�N���A���J��
�@�T�|�T�@�A���P��
�@�T�|�U�@�A���L���@�@
�@�T�|�V�@�Ζ��ƓV�R�K�X�ƐΒY
�@��R�́@���b��������
�@�T�|�W�@�A���R�[���ƃG�[�e��
�@�T�|�X�@�A���f�q�h�ƃP�g��
�@�T�|10�@�J���{���_
�@�T�|11�@�G�X�e��
�@�T�|12�@����
�@�T�|13�@�Z�b�P���ƍ������
�@��S�́@�F����������
�@�T�|14�@�F�����Y�����f
�@�T�|15�@�t�F�m�[����
�@�T�|16�@�F�����J���{���_
�@�T�|17�@�F�����A�~��
�@�T�|18�@�L�@�������̕���
��U�ҁ@�����q������
�@��P�́@�V�R�����q������
�@�U�|�P�@�����q�������̕��ނƓ���
�@�U�|�Q�@�P���ނƓ�
�@�U�|�R�@������
�@�U�|�S�@�A�~�m�_
�@�U�|�T�@�^���p�N��
�@�U�|�U�@�j�_
�@�U�|�V�@����
�@��Q�́@���������q������
�@�U�|�W�@�����@��
�@�U�|�X�@��������
�@�U�|10�@�S��
�@�U�|11�@�C�I����������
�@�U�|12�@�@�\�������q
|