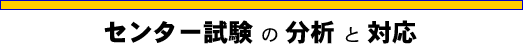
�����w�|��w���������w�Z�@�n�Ӂ@��
|

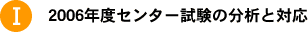
1. �S�̓I�ȌX��
�@���N�̃Z���^�[�����ɂ̓��X�j���O�����߂ē������ꂽ���A�M�L�͏o��\���E�ݖ␔�E�z�_�͍�N�x�ƕς�炸�A�e���͂Ȃ������B��N�ʂ��{�I�Ȗ�肪�������͂Ȃ��B������蕶�̑��ꐔ����N�x�Ƃقړ����ł���B�S�̂Ƃ��č�N�x���Չ����A���ϓ_�͍�N����10�_�����Ȃ����B�������A��N���l�A�܂���킵���ݖ�I����������������̂Ŗ��f�͋֕��ł���B
�@�R�~���j�P�[�V�����\�̖͂��Ƃ��ẮA
��1��A�F�P���������Ƃ����A�N�Z���g�Ŕ��b����\��
��1��B�F��b�̒��ʼn����̋���f����\��
��2��B�F�Θb�̗���𐳊m�ɓǂݎ��A����̈Ӑ}���Ă��鎖����c������\��
��5��@�F��b�̓��e����킩�����I�m�Ɉ����o���\��
����N�ʂ苁�߂��Ă���B
�@�܂��lj�͂ł́A
��3��F���͂̍\����_���I�Ɏv�l����\��
��4��F�}�\�����Ƃɕ��͂𐳊m�ɓǂݎ��\��
��6��F�o��l���̐S�����l�����킹�A����̋◬��𐳊m�ɒǂ��Ȃ��璷����ǂݎ��\��
���������B����������͂̑S�̓I�ȗ��������œI�m�ȏ���ǂݎ������̊w�K�p���������B
�@�������̑�4 ��A��5 ��A��6 ��̑��ꐔ�͍�N�x�Ƃقڕς��Ȃ��B�f���œǂ݂₷���A��Փx�͂���قǍ����Ȃ��B
2. ��̓I���e����
����1�⁄
�`���A�z�_�Ƃ��ɍ�N�x�ƕς�炸�B
A �A�N�Z���g�i4�_�j
�@�����̒��ŒP��̃A�N�Z���g��₤���B�i���ɂ��A�N�Z���g���قȂ�ʒu�ɂ���P��͏o�肳��Ȃ��������A��N�x�͏o�肳��Ȃ������A������J�^�J�i�p�ꂪ���������B�܂��A���N�͑S��3���߈ȏ�̌ꂪ����Ă���B�A�N�Z���g�̃��[���i-graph, -al, -logy �̃A�N�Z���g�̈ʒu�j��m���Ă���Ζ��Ȃ����A���o�œ�����̂͊댯�ł���B
B �����ł̒P��̋����i12�_�j
�@��b�i100�ꋭ�j�̗���ƁA�O��̔������e����|�C���g�ƂȂ��f������B�������i1�j��ruined �̂悤�ȐV����ǂݎ��\�͂ƁA�������i3�j�̇T�ƑO����Everybody �Ƃ������ΏƁE�Δ䂳��Ă��鎖����_���I�ɑ�����\�͂������B
����2�⁄
�`���A�z�_�Ƃ��ɍ�N�x�ƕς�炸�B
A ���@�A��@�A��b�i20�_�j
�@���@�A�C�f�B�I���A�\���A��b�\�͂f������B�����̌`��₤���ihave �{O�{�ߋ������k��4�l�Aallow �{O�{ to �s�莌�k��8�l�j�͈��������o�肳��Ă���B�܂��A�P�ꎩ�̂̒�`���͂Ȃ��Ȃ�A��@��R���P�[�V�����̗͂��ėv��������icome about�k��5�l�Awould rather�`�k��7�l���j���ڗ��B���ۂ̃R�~���j�P�[�V���������ɂ����Ďg�����{�I�Ȋ��p�\���̒m���������B
B �Θb�������i6�_�j
�@�Θb����������������B���b����4�ɑ������B�̒���̂���ӂ��Q�l�ɁA�ǂ̂悤�ȈӐ}�̂���ӂ����l����B�S�̂̕����̗���������������ʼn�b���L�̊��p�\���iHere you go.�k��1�l�AIt just slipped my mind.�k��2�l���j���������Ă����K�v������B
C ��吮���i12�_�j
�@�e���̒��ɕK���܂܂�镶�@���ځihelp �{O�{�����̌��`�k��1�l�A�W�㖼��what�k��2�l�Aare not permitted �{ to �s�莌�k��3�l�j���g���ĈӖ��̒ʂ������������B���@�ƂƂ��ɁA�u�`�Έȉ��v�k��3�l�Ƃ������A�������ʂɎg���Ă���t���[�Y���p��łǂ��\�����邩�ɂ���ɊS���Ă������B
����3�⁄
�`���A�z�_�Ƃ��ɍ�N�x�ƕς�炸�B�{���̌ꐔ�͍�N�x����50�����B
A �ڑ����[�i6�_�j
�@���ƕ����Ȃ���i��j��I�Ԗ��B���N�͑Δ�ƒlj���\��������߂���ł������B�̑O��̕�����c�����A���ڂ�t�ځA���R�A�����A�v�̂Ȃ���𐳂����������A�_�̓W�J���ǂ̂悤�ɂȂ���Ă���̂��𐳊m�ɓǂݎ��͂������B
B �������i10�_�j
�@�Z���p�b�Z�[�W�̒��ŕ���K�ȏ��ɕ��ׂ�������B���͑S�̗̂���A���ɋ̑O��̕����𗝉����Ă���������ƂɂȂ�B�I�����̕����̑㖼����w����ithis shyness, this plan�k��2�l�j�������Ă��邩�A�ڑ���\�����Řb���ǂ̂悤�ɓW�J����Ă��邩�iHowever�k��2�l�j�A�܂��A������w���㖼���̎g�������ia more advanced system��The system�� a system like this�k��1�l�j�ɋC�t�����Ƃ��傫�ȃ|�C���g�ƂȂ�B
C �K����[�i18�_�j
�@�`���Ɏ����ꂽ����i���̂ǂ��炩�̏ꏊ�Ɉ�����Ă͂߂���B�I�����̕����A�y�ё}���ӏ��O��̑㖼����w����A�ڑ������i��j�ɋC�����A�_���������W�J����悤���Ă͂߂Ă䂭�B
[30] There is, however, also some data suggesting that genetics, family income, and even the parents�f level of education may play a part in how likely a child is to suffer from allergies.
�̂悤�ɁA�����A�\���A�P�ꃌ�x���Ƃ��ɓ�Փx����������Z���Ԃœǂݎ��A���̏ケ�̕����{���̂ǂ��ɓ��邩���l�����킹�Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�u�P�ꁨ�����i�����S�̂̍\���v�𑨂��邽�߂ɂ́A�e����ǂݎ��͂Ƒ傫�Ȏ���ŗ���𑨂���̗͂������K�v�ƂȂ�B
����4�⁄�i35�_�j
�@�}�\�ǂݎ��lj��B���A�z�_�͂Ƃ��ɍ�N�x�ƕς�炸�B�{���̌ꐔ�͍�N�x����50�����B�}�\���Q�l�ɁA�W�J�����_����I�m�ȏ���͂�₤���B��N�ʂ�A3 �`4 ���ڂ���r�ΏƂ����������ɂȂ��Ă���B�}�\������Ƃ����Ă��A�����܂ł��{���𐳊m�ɓǂݎ��͂���{�ƂȂ�B�v�Z�����ē��������͏o�肳��Ă��Ȃ����A�}�\�ǂݎ��̗͈͂ˑR�v�������B
����5�⁄�i32�_�j
�@��b���lj��B���A�z�_�͂Ƃ��ɍ�N�x�ƕς�炸�B�b�҂̐��͍�N�Ɉ�������4�l�B
�@��[�k��A�l�͉�b�\��������ꏊ��₤���B�e�X�̂���ӂ̈Ӑ}����Ƃ���͉����i���ӁE���ӁA�b�̓]�����j��ǂݎ��B�{������ʂ�ǂ�ł�����g�����悢���낤�B�C���X�g��I�Ԗ��k��B�EC�l�ł͖{���̓r���őI��ł��܂����Ƃ̂Ȃ��悤�ɁB�b�̓W�J����ł́A����ꕶ�����Ŕ��f����ƌ�����������Ă��܂��\�����B�ЂƂЂƂ̎������Ō�܂ŏ���ǂ��Ċm�F���Ă����T�d�����v�������B
�@���e��v���k��D�l�ł́A�{����ǂݐi�߂Ȃ���q�ׂ��Ă�����e�𐳊m�ɂ��ނ��Ƃ���ł���B
����6�⁄�i45�_�j
�@�����lj��B���A�z�_�͂Ƃ��ɍ�N�x�ƕς�炸�B�{���̑��ꐔ�͍�N�x����30�����B���ꕶ��ǂ�Ŏ���ɓ�������k��A�l�Ɠ��e��v���k��B�l��2 ��ށB����ł͂��邪�A��z���܂߂���ʓW�J�ɒ��ӂ���K�v������B
�@�o��l���ׂ̍��ȐS������i���ړI�ɂ͖{���ɂ͏�����Ă��Ȃ��j�̂ŁA��b��b�̓W�J������[���ǂݕ����ł���͂�{���Ă����K�v������B�܂��A�����̑I�����͖{���ɍڂ��Ă��Ȃ��P��(�\��)�ŋ��߂���ꍇ�������̂ŁA��{�I�ȗދ`��͂��K�v�Ƃ����B
3. ��N�x�ʂ�̓_
[1] �}�[�N���y�єz�_
[2] ���̑���1�₩���6��܂Ō`���ɑ傫�ȕω��͂Ȃ��B
�@
4. ��N�x�ƕω��̂������_
[1] ��@���i��2��A�j�����������B
�@�R�~���j�P�[�V�����\�͏d���̌���ł��낤�t���[�Y�A�R���P�[�V�����֘A�̒m�����v��������肪���������ifor the sake of�k��2�l�Acome about�k��5�l�Ait is convenient�k��6�l�Awould rather �`�k��7�l�Ain the end�k��9�l�Aas far as�k��10�l���j�B��������p�p���T���g���A�p�a��a�p���T�ł͂킩��ɂ����p����L�̃j���A���X�̈Ⴂ�A�܂����{��ł͋�ʂ��Ȃ��Ă��p��ɂ͂���ދ`��̈Ⴂ�ɂ��ẮA�������璍�ӂ����Ƃ��d�v�ł���B
[2] ��̒�`���i��2��A�j���Ȃ��Ȃ����B
[3] �Θb�������i��2 ��B�j�̔��b����3 ����4 �ɑ��������B
�@��b�̗����ǂݎ��͂��܂��܂��K�v�Ƃ����B
5. �V�X���̓_
�s�Ԃ�ǂޗ͂��������i��6 ��A��2�A��4�A��5�j�����������B
�@�{�����Œ��ړI�ɂ͏q�ׂ��Ă��Ȃ����e�A�S���ǂݎ��͂��������B�{�����̒P������ǂ����߂Ă��������ł͐����ɂ��ǂ蒅���Ȃ��B�u�Ȃ����̂悤�ȍs����������̂��H�v�A�u���̎��̐S��́H�v�Ƃ������L���ȑz���͂�|���Ă����K�v������B
6. �����̊w�K�ő�Ȃ���
[1] ��ƌ�̂Ȃ���i��@�ACollocation�j�ɊS�����B
�@����P��ɓ����ہA���̌�ƂȂ��肪����p����L�̕\�����ꏏ�ɐg�ɂ������B���̂��߂ɂ͉p��ɂ�������G��A����邱�Ƃł���B�P����@�������ۈËL����̂ł͂Ȃ��A�Ղ����������������ǂނ��悵�A�̂�f�擙�ŋC�ɓ������䎌���o������悵�B����P�ꂪ�o�Ă����玟�ɂǂ���������̂��A�ɋC������K����g�ɕt���Ă��������B
[2] �l�C�e�B���̉p����A���ɂ���B
�@���X�j���O������݂̂Ȃ炸�A�A�N�Z���g�A�������A�\���i���Ɠ����̋�ꓙ�j�ɒ��ӂ��ē�������p����A���ǂ����邱�Ƃ���ł���B�\���I�ɉ��ǂ����邽�߂ɂ͂��������Ȃ��邾���ł͂��A���e�𗝉�����K�v�����邵�A�����������J�肩�����ēǂݍ���ł䂯�A�Ȃɂ����A�p��̉��ɑ��鋻���A�S���K������͂��ł���B
[3] �_���W�J���d�������lj�͂�{���B
�@�ǂ�ȓǂݕ��ł��ŏ��ɑS���ʂ��ēǂ݁A�_�̓W�J���ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩���܂��l����B�Z���^�[�����ł́A����P�ꂪ�g���Ă��Ă��A�ʂ̉ӏ��ŕK�����̐������قȂ�\���ŏq�ׂ���B�S�̘̂_���𑨂��Ă���e���̓ǂݎ��ɓ��肽���B�ꕔ�ɂ������߂��āu�����ĐX�������v�ɂȂ�ʂ悤�傫�Ȏ����{���A���ꂪ���[�����e�����ɂȂ���B
[4] �Ǐ���ʂ��ĖL���ȑz���͂���Ă�B
�@�����ǂލۂɓo��l���̐S������킹�ēǂݎ�邱�Ƃ�S�|����B���܂���Ȃ���A����͖{�̖{���̓ǂݕ��A�Ǐ��̊�тł���B�g�p�꒷���̎��h�Ƃ��������g�ł͂Ȃ��A�Ǐ��̐^�̊y���݂��������B
7. �Ō��
�@�Z���^�[�����͍��Z�Ŋw�Ԃׂ���{�I�������g�ɂ��Ă��邩�ǂ������������̂ł���B�R�~���j�P�[�V�����\�͂Ɛ��m�ȓlj�́B���̓�̗͂��琬���邱�Ƃ��w���̍���ɂ�������ƒu����������A"�Z���^�[������"�Ɠ��ʂɈӎ������Ƃ��A���k�̉p��͂͊m���Ɍ��シ�邱�ƂɂȂ�ł��낤�B
 �i II 2006�N�x�Z���^�[�������X�j���O�e�X�g�̕��͂ƑΉ��j �i II 2006�N�x�Z���^�[�������X�j���O�e�X�g�̕��͂ƑΉ��j

  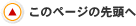
|