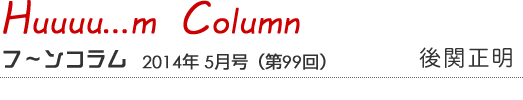
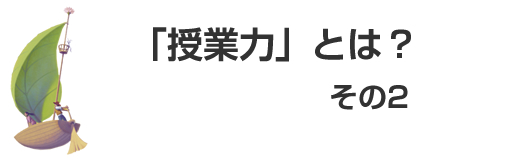
前回はNEW CROWN BOOK 2のLesson 6 "Uluru" を例にとり,授業の「導入」についてお話しました。簡単におさらいしますと「授業力」とは,授業実践のための『総合力』で,4つの要素(①言語材料や題材の知識,②一単位時間の起承転結のプロセスの確認,③授業の形態などに変化をつけること,④静謐な授業であること)が統合されることによって成り立つとしました。
前回「導入」の例としては,ターゲットセンテンスを授業時間内に,全員の生徒に発話させられるように,パターンプラクティス的に練習させました。30人学級で列ごとに発話する場合,一人ずつ全員が発話すれば,29回同じ文を聞くことになり,それだけ聞けばたいていの生徒はそれを覚えます。加えて,題材のオーストラリアについての話題など,先生がオーストラリアに行った体験など,それについていろいろなエピソードを話せば,英語で分からない部分があったとしても,生徒は身を乗り出して聞くものです。それに視覚教材,つまり先生自身の記念写真などあればこれほどよい教材はありませんね。こうして生徒をオーストラリアの世界に引き込むわけです。
さてここからが「授業力」とは?―その2の本題ですが,今回は授業をすすめるうえで,「展開」の起承転結を例示し,授業の形態などにもふれ,まとめと自己評価を含めた「振り返り活動」についてもお話しようと思います。 まず,「展開」に入る前に,2時限目の授業の導入は,前時の復習の仕上げとしてオーラルイントロダクションを下記のような《ワークシート1》を使って行います。同じ内容の英文を違う方法で何度も使うことによって生徒が英文に慣れることを狙いとしています。
《ワークシート1》
音声を聞いて,( )に聞き取れた英語を書き入れなさい。(綴りが分からないときは日本語でもよい。)
This is a ( ) rock. It is on a large, flat plain in ( ). Many people go there to ( ) it. The rock has two ( ). One name is from the British: Ayers Rock. Ayers was the name of a British leader. ( ) name is Uluru. It ( ) 'rock' in the language of ( ) native people. Which name do you like?
このワークシートの答え合わせは短時間ですませ,次に,まずヒントなしでGETのPart 1の英語をCDで聞かせます。2~3回聞かせたのち,Part 1の内容の一部を( )にした下記の《ワークシート2》を配布し,改めて今度はCDを聞かせながら( )内を埋めていきます。このときも分からなければ日本語でもよいと指示します。(この指示はスローラーナーのストレスを和らげます。)
《ワークシート2》
Part 1
Ken: How was your trip to ( ) ?
Emma: It was ( ). I'll ( ) you some pictures.
Ken: Oh ? You are ( ) a coat. Was it ( ) ?
Emma: Yes. It was ( ) there.
記入が終わったら教科書を見ながら自己採点あるいは隣同士で交換採点をしたのち,CDまたは教師による範読にrepeat させたりshadow reading させたりします。この活動を10分続けるとおぼろげながらGET の内容が分かる生徒が増えてきます。
次にUluruの写真を見せながらオーラルイントロダクションで使用したpassages,すなわち《ワークシート1》で使った英文を再び教師が生徒の顔をよく見ながら発話します。(このように同じ英文を何回も方法を変えて使うことを私はrecycling reading と称しています。)その時に生徒の表情やeye contactで理解の度合いがある程度つかめます。
そして教科書の内容の説明に入りますが,ここはいわゆる和訳が少し混じった方がいいと思います。なぜかと言いますと大半の生徒は分かったとしてもスローラーナーは必ずいるわけですから,その生徒たちのためにも日本語で説明して「分かった」と安心させることが授業へ集中力を持続させる秘訣です。また,中位の生徒にとっては,あいまいな部分が確認できたり,さらに難しいところにも挑戦しようとしたりする意欲がわくと思います。 また個々の生徒が本当に理解したかどうか確かめるには,ペアでの読み合わせの時に,相手への内容の説明で相手が分かったと言ったら,説明したその生徒も内容を理解していることになるでしょう。こうしたアクティビティを続けると相手が分かるように説明しなくてはならないのでより一層、内容把握に努めることになります。それが自発的に学習しようとする動機となり,集中心も高まり,望ましい学習態度が身についていくわけですね。
次の活動はGETのあとにあるPracticeです。Word Cornerの単語なども使って,できるだけバラエティに富んだ活動にしたいと思います。そして,まとめの段階に入ります。ここで学んだことが確かに身についたかどうかを試すために,先程使用した《ワークシート2》を再利用しますが(活動の内容はshadow reading, pair readingなど),個々の生徒への浸透度が計れる内容を考えて,次のような《ワークシート3》を作成しさらに深く教科書を読み込む仕掛けを用意しておくとよいでしょう。質問に答えるには少し難しいので,すべての生徒がその場でできなくてもよしとします。したがって時間がなければ宿題にしてもいいと思います。さらに簡単に記入できる《自己評価表》を配布し記入後に集めます。
これは教師が以後の授業へのステップに役立てます。
《ワークシート3(Q&A活動)》
1. How was Emma's trip to Australia ?
_________________
2. Did Emma show Ken some pictures ?
_________________
3. Why is Emma wearing a coat ?
_________________
《自己評価表》
今日の授業は・・・1. よくわかった
2. だいたいわかった
3. よくわからないところがあった
4. まったくわからなかった
これでLesson 6 "Uluru"Part 1 の授業は終わりますが,前回の「導入」と今回の「展開」「まとめと自己評価の振り返り」の中で始めに述べた「授業力」の3つの要素が満たせたと思うのですが,いかがでしょうか。
なお,Q&A活動のワークシートについては無理をせず宿題にしてもいいと述べました。宿題を回収して先生が採点し,注意を与えると英語が苦手な生徒も上位者もさらに伸びていくと思われます。
4つめの要素「静謐な授業」――穏やかな雰囲気の授業づくりのためにはどうしたらいいか……。これもいずれ一つの課題として取り上げたいと思います。
お忙しいでしょうが頑張ってください。以上,ご参考になれば幸いです。
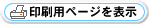
後関 正明 (ごせき まさあき) 先生
東京都墨田区立中学校で教諭,校長を長年務める。その後,東京都滝野川女子学園中・高校で教鞭をとる。現在,NPO法人「ILEC言語教育文化研究所」常務理事。2003年より國學院大学で教職課程履修の学生を教えている。
 フ~ンコラムバックナンバー (第1回~98回) フ~ンコラムバックナンバー (第1回~98回)
ご質問がございましたらニュークラウン指導相談ダイヤル(03-3230-9235 受付時間 月・火・木曜日 10:00
~ 16:00)へどうぞ。 メールの場合は「 問い合わせフォーム」へ 問い合わせフォーム」へ

  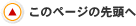
|

