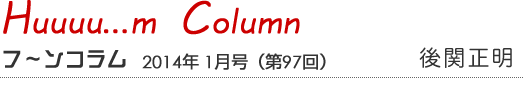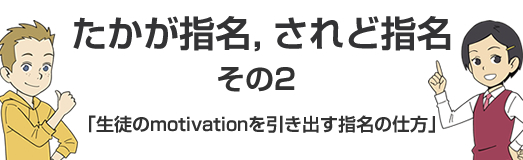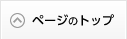|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teacher�F | Taro, are you a member of a baseball team ? | |
| Taro�F | Yes, I am. | |
| Teacher�F | So you can play baseball. OK. Can you throw curve? / Can you run fast? / Can you bunt well? | |
| Taro�F | Yes, I can. I can play baseball very well. | |
| Teacher�F | Thank you, Taro. Next, Jiro, stand up. Is Taro a member of a baseball team ? | |
| Jiro�F | Yes, he is. | |
| Teacher�F | Can he play baseball ? | |
| Jiro�F | Yes, he can. He can play baseball very well. | |
| Teacher�F | OK. Jiro. Thank you. Please sit down. | |
�ȂǂƓ��e���������ӂ���܂��Ȃ�������k�Ƃ�Q & A�����������ɂł���悤�ɂȂ�킯�ł��B���ɔے�̓������܂ޕ��̗��K��……
| Teacher�F | Risa, are you a member of a tennis club ? | |
| RIsa�F | Yes, I am. I am a member of a tennis club. (���̏ꍇthe tennis club�����@��K�ŁC���ł�the�͊��K��ł��������ł͖��Ȃ����Ƃɂ��܂��B���������t�͂���ƂȂ�the���g���ČJ��Ԃ��܂��B) | |
| Teacher�F | Can you play tennis ? | |
| Risa�F | Yes, I can, but I can’t play baseball. | |
| Teacher�F | Thank you, Risa. Next, Hanako, please stand up. Is Risa a member of a tennis club ? | |
| Hanako�F | Yes, she is. She is a member of a tennis club. | |
| Teacher�F | Can she play tennis ? | |
| Hanako�F | Yes, she can. She can play tennis very well. | |
| Teacher�F | Can she play baseball ? | |
| Hanako�F | No, she can’t. She can’t play baseball. | |
| Teacher�F | OK. Hanako. Thank you very much. Please sit down. | |
�@�@���̂悤�ȋ��t�Ɛ��k�Ƃ̑Θb�͑S�����ł���Ƃ͌���܂���B�����̒x�����k�ɂ�Yes.�Ƃ�No.�����̓����ł�Good!��Good job!�ȂǂƖJ�߁C���̒���ɋ��t��full sentence�Ō����C�����������Ƃ����悤�ȋ��t�̃t�H���[���K�v�ł��B�v����Ɋ�{��4�ŏq�ׂ��悤�ɋ��t�����k�Ɋ��Y�����Ƃ���Ȃ̂ł��ˁB�������狳�t�̐��k���v���������C�������`���C���t��M������C�������炿�܂��B�ł�����w���̎d���ƃt�H���[�̎d���ɂ���Đ��k�̉p����w�ڂ��Ƃ���motivation�����N�����邱�ƂɂȂ�C�܂��ꍇ�ɂ���Ă͋t��motivation�����킹�邱�Ƃɂ��Ȃ�킯�ł��B
�@�������s�����w���Ɋւ��Ă̂�����̕��@�́u�w���J�[�h�v�Ȃ���̂k��l��l�Ɏ����������Ƃł��B��������ȏ��̗��\���̗��ɃJ�[�h�̏�̕��������ЂÂ������܂����B���̃J�[�h�ɂ́C�ꎞ�Ԃ̎��ƂŃp�^�[���v���N�e�B�X�ȂǗƂɈ�l�����b�����⋓������ē������ȂǁC�v����Ɉ�l�Ŕ��b�������L�������܂����B�����1�`2�T�Ԃ��Ƃɋ��t�������Ɩڂ�ʂ��_������Ƃ��������̌l�̔��b�̉��킩��܂��B�����̌o���ł͈ӊO�Ɏw���̎d�����A���o�����X�̎�������܂����B���̎���1�������炢�����Ă���ƂȂ��S���Ɏw���������悤�ɒ������܂����B��������ƔN�Ԃ�ʂ��ăN���X�S���̌l�̔��b�����ω����܂����B�������ł��x��Ă��鐶�k�����b�͕��ϓI�ɂȂ�C�]���Ď��ƂŒu���Ă������Ƃ����悤�ȕ��͋C�͂Ȃ������悤�Ɏv���܂��B
�@�����Ŏw���ƕ]���̊W�ɂ��ď����G��Ă����܂��傤�B�l�̎w���̉͗Ƃ̏ꍇ�͂قړ����ł����C���̑��̑�ޓ��e�Ɋւ���Q & A�����ɂ��Ă���ɕ]���̊ϓ_���́u�R�~���j�P�[�V�����ւ̊S�E�ӗ~�E�ԓx�v�̍��ڂŕ]�����邱�Ƃ��ł��܂��B�������Q & A�̓��e�ɂ���Ắu�\���◝���̔\�́v�܂��́u����╶���ɂ��Ă̒m���E�����v�܂ŋy�Ԃ��Ƃ�����܂��B�����̕]���Ɋւ��ď����͎��Ǝ��œ��ɖڗ��������k���o���Ă������ƌ�ɋL�^���Ă����܂����B���ƒ��̃`�F�b�N�i�L�^�j�͐��k�ɗ]�v�ȃv���b�V���[��^����̂ŏ����͂��܂���ł����B������Q & A�Ŏ����I�ɋ�������ē��������k�Ɋւ��Ă͓��e�ɂ����܂����C�u�ϋɓI�Ɏ��ƂɎQ���ł����v�ƕ]�����ċL�^���C�ŏI�I�Ȓʒm�\�̏������ɋL�����Ă��炦��悤�ɒS�C�̐搶�ɂ��肢���܂����B
�@�ȏ�B�搶�̂��Q�l�ɂȂ�Ǝv���C�����̌o���k�������Ă��b�����܂����BB�搶�̎��H�̌��ʂȂǂ�����������������K���ł��B�ł͊撣���Ă��������B �@
�����s�n�c�旧���w�Z�ŋ��@�C�Z���N���߂�B���̌�C�����s���쏗�q�w�����E���Z�ŋ��ڂ��Ƃ�B���݁CNPO�@�l�uILEC���ꋳ�當���������v�햱�����B2003�N��蚠�{�@��w�ŋ��E�ے����C�̊w���������Ă���B
![]() �t�`���R�����o�b�N�i���o�[�@�i��1��`96��j
�t�`���R�����o�b�N�i���o�[�@�i��1��`96��j
�����₪�������܂�����j���[�N���E���w�����k�_�C�����i03-3230-9235�@��t���ԁ@���E�E�ؗj���@10�F00
�` 16�F00�j�ւǂ����B ���[���̏ꍇ�́u![]() �₢���킹�t�H�[���v��
�₢���킹�t�H�[���v��
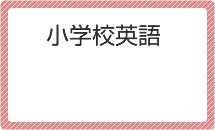 |
||
 |
||
 |
||