


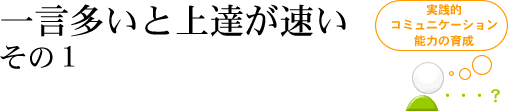
Q:「実践的コミュニケーション能力の育成」が叫ばれていますが,実際の教室でこの目標を実現させるためにはどうしたらいいでしょうか。
こういう質問を受けました。教育実習を目前に控えた大学4年生からです。ずいぶんと「大きな質問」でしたので一度の回答ではすまされず,2度・3度にわたりメールでやり取りしました。
実は,この問題は現職の先生方にも当てはまる課題でもあるので取り上げてみる価値はあると思いました。やはり授業法に関しては「 Plan - Do - See( Check ) - Act 」のサイクルの中で基本に立ち返る必要はありますね。実習生とのメールのやり取りで私が答えた事のあらましを述べてみたいと思います。
実践的コミュニケーション能力の育成というと,まず英語を聞いたり話したりすることができる能力だと思いがちですね。でもそればかりではなく,読んだり書いたりして他とのコミュニケーションが取れる能力も必要なわけですね。要するに実践的コミュニケーション能力の育成は4技能全部と関係があるということです。ですから先ほど「大きな質問」と言ったのです。ではまず初めに「聞く・話す」を中心とするコミュニケーション能力の育成に的を絞ってみましょう。
NEW CROWN 1,DO IT―TALK 1 (p. 18)を例にとって説明しましょう。モデル文では,新入生の健が,ALTのミラー先生に話しかけて「初めまして」と,初対面のあいさつをします。このページでは,初対面のあいさつと,相手に聞き返すときの言い方を学習します。
[指導過程]
- モデル文のリスニングと音読に時間をかけ,まず読めるようにする。
- 実際にALT とのTT ができる場合は,そのALTにMs Millerの役をしてもらう。これに慣れたらALTの実名を使って練習する。
- コーラスリーディングのあとは,S-Sで対話練習に入る。ここは,大切なコミュニケーション活動の第一歩なので全員に暗誦させてスピーキングの基本を学ばせる。
- なるべく多くの友だちと対話する。紹介サインシート(『アクティビティ アイディア集1』のp. 39にあるようなもので,友だちにサインを書き込んでもらう20個のマス目のあるシート)を配り,紹介し終わったら友だちにサインをしてもらう。
- 習熟の遅い生徒には,教師が相手をして支援する。または生徒の中から先生役を何人か選ぶ。
ここまでは,教科書にあるDO IT―TALK 1の基本的な展開ですが,これをもう一歩進めてさらに生徒にこのコミュニケーション活動の基本を身につけさせたいと思います。
「あの人はいい人だけど,いつも一言多いのよね」はよく聞かれるせりふですね。でも,こと英語の学習に関してはその「一言付け加えること」が上達へのアプローチで大切なのです。さてそこで,モデル文に何を付け加えればいいか…。ここから先生方の出番です。一例を挙げてみましょう。
先ほどのモデル文のKenとMs Millerはもう顔見知りになりました。そこで『アクティビティ アイディア集1』p. 38のモデル文を活用して独自のモデル文を作ります。すなわちKenとMs Millerのほかに,もう一組のペアを作り(久美とワン・ミンなど),紹介し合います。
Ken: Hello. This is my teacher, Ms Pat Miller.
Ms Miller: Hello. I’m Pat Miller. Nice to meet you.
Kumi: Hi. Nice to meet you too. I’m Kumi. This is my friend, Ming.
Ming: Hi. I’m Ming.
Ms Miller: Nice to meet you, Ming.
[『アクティビティ アイディア集1』(三省堂)38ページより]
KenがMs Millerを2人の友だちに紹介する場面です。このように4人一組になって対話を続ける練習をします。初めはちょっと入り組んでいて4人の関係をのみ込むのに時間がかかりますが,ワイワイやっているうちに,すらすら紹介できるようになります。
こんな一言なら決して余計な一言ではなく,初めのdialogを定着させ,さらに一言付け加えて発展させることになります。また,このモデルに例えば,I’m from Ryogoku Elementary School.(私は両国小学校出身です。),または,Mingなら,I’m from China.と付け加えて,広げることもできます。
このように,対話を自分で考えて膨らませていくことにも慣れてくると,実践的コミュニケーション能力の基本が身につくと思います。大いに一言も二言も多く話せるように指導したいものです。

| 後関 正明 (ごせき まさあき) 先生
東京都墨田区立中学校で教諭,校長を長年務める。その後,東京都滝野川女子学園中・高校で教鞭をとる。現在,NPO法人「ILEC言語教育文化研究所」常務理事。2003年より都内の私立大学で教職課程履修の学生を教えている。 |
|
 フ〜ンコラムバックナンバー (第1回〜36回) フ〜ンコラムバックナンバー (第1回〜36回)
ご質問がございましたらニュークラウン指導相談ダイヤル(03-3230-9235 受付時間 月・火・木曜日 10:00
〜 16:00)へどうぞ。 メールの場合は「 問い合わせフォーム」へ 問い合わせフォーム」へ

  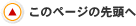
|

![]() 問い合わせフォーム」へ
問い合わせフォーム」へ
![]()

![]() 問い合わせフォーム」へ
問い合わせフォーム」へ
![]()