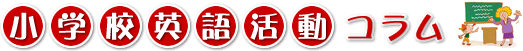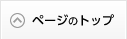|
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
�D I say an animal. Please choose the animal and put it on the right box. Are you ready? �iNo. 1, cow �˂P�̃}�X�Ɂu���v�̊G��u���B�^ No. 2, dragon �� �u���v�̊G���Q�̃}�X�ɒu���B�@���\��x�̊G���u���I���܂ŌJ��Ԃ��B�j
�E Now, what is the animal of this year?�i�q���g�Ƃ��āC���Ɂu2011�v�Ə����@��2011�N�̊��x�́u�������v�j
�F �u2011�v�𒆐S�ɁC���Ɂu2010�v�C�E�Ɂu2012�v�Ə����āCnext year, last year�̊��x���B
�G What is your animal?�i�q�ǂ������̊��x���B�j
�H Can you guess at my animal?�i3�q���g�Q�[���Ƃ��āC�l��������B�j
�I This is the last question.�i���x�̗R�����l��������B�@�����E�n�}��p�ӂ��Ă����B�j
�J �����ł����݁C���{���l�\��x�̏K�������邪�C���{�ƈႤ�_������C�Ƃ����b������i�u���̂����v�ł͂Ȃ��u�Ԃ��v���g���Ă��邱�ƁC�Ȃǁj�B
3�D�]���̎��݂ɂ���
�@��L�̎��Ƃ��s�������Ƃ́C���t�ɂ�鎩�ȕ]���Ǝq�ǂ������̕]�����܂Ƃ߂Ă݂܂��B
(1)�@�����i�S�C�j�ɂ�鎩�ȕ]��
�y��1�z�@�w�K�w���v�̖̂ڕW���ɂ���B�@ ���ɂ킩��₷��input�𑽗ʂɁC�A ���t�╶���̈������ɂ���C�B �O���[�v�w�K�Ȃǂ����p���C�ϋɐ������߁C���b�̋@��𑽂�����B
�y��2�z�@�]���̕W�L�@��P��������B�i�]����F���c�����C���c�قږ����C���c���P���K�v�j
�Ȃ��C���̕W�L�@�͎q�ǂ������ɂ��C���l�Ɏw�����Ă���B
| �]���̊ϓ_ | ��| | ���t���g�ɂ��]�� | �]�� |
|---|---|---|---|
| �p���input | (1) listening before speaking | (1) ���Ȃ蒉���ɂł����B�p���b�����ʂ��������Ǝv���B | �� |
| (2) �q�ǂ��ɂƂ��Ă킩��₷���p���₢�������ł������B | (2) Direction�̗^�������s���m�������B���̂��߁C�������ׂ����������q�ǂ���5�`6�������B | �� |
|
| ���t�╶�� | (1) ���x�̗R�����l��������q���g�͑Ó����������B | (1) ���E�n�}�������ƌ��ʓI�Ɏg�����������B | �� |
| (2) �����Ƃ̏K���̈Ⴂ�ɂ��Ă̐����͓K���������B | (2) Where is baseball from? �ȂǁC�܂������̗�������Ă���How about �eEto�u���x�v�f? �Ɩ₩����ׂ��������BModel�̊��p�ɍH�v���K�v�������B | �� |
|
| �ϋɐ� | (1) ����̎d���͋�����ϋɐ��������o���̂Ɍ��ʓI���������B | (1) �����C�^�X�N�̐�����w������w�I�m�ȉp��łł���悤�ɂ������B | �� |
| (2) �O���[�v�w�K�́C���ԂƂ̋������̈琬�Ɍ��ʂ����������B | (2) �݂��ɏ�����������C��э������肷��p������ꂽ�B | �� |
(2)�@�q�ǂ������̎��ȕ]��
���@�]���p���i�u�U��Ԃ�v�j��z�z���C3�̊ϓ_���當�͕\����3�i�K�̊�ŕ]���������B
�����kA�̗၄
| �]���̊ϓ_ | ��| | �]�� |
|---|---|---|
| �ǂ�ȓ_������ �Ȃ�܂������B |
�p�ꂪ����킩��悤�ɂȂ����B���x����������`��������Ƃ͒m��Ȃ������B�\��x�̍Ōオ�u���̂����v�ł͂Ȃ��C�u�Ԃ��v���ƕ����āC���ǂ낢���B | �� |
| �����̗ǂ������_�� ���ł����B |
�킩��Ȃ��Ƃ������������C�O���[�v�ŋ��͂ł��āC�y���������B | �� |
| �����Ƃ���肽���_�� ����܂����B |
�X���[�q���g�Q�[�����āC�����Ƒ����������킩������Ǝv�����B | �� |
�����ۂɎq�������ɔz�z�����u�U��Ԃ�v�p����
| �ǂ�ȓ_������ �Ȃ�܂������B |
||
| �����̗ǂ������_�� ���ł����B |
||
| �����Ƃ���肽���_�� ����܂����B |
4�D�]���̌��ʂɂ���
�@���t�ɂ�鎩�ȕ]���Ǝq�ǂ������̕]�����r��������ƁC���Ƃ̎��I����ɖ𗧂������Ȗʂ������Ă��܂��B�q�ǂ����������Ɂu�U��Ԃ�v�������鋳���������悤�Ɏv���܂����C���������ȕ]�����C�q�ǂ������́u�U��Ԃ�v�Ɣ�r�E�ΏƂ��邱�Ƃɂ��C���L�̂悤�Ȍ��ʂ�������Ǝv���܂��B
�@�@ �q�ǂ����u����킩���Ă����v�̂́C���t���H�v���ė^����input�̌��ʂ�������܂��C�A ���ʁC�u�킩��Ȃ��Ƃ����������v�̂́C���t�̉p��ɂ��w�����̂������Ȃǂ��s�K���������߂�������܂���B�B ���ȕ]���Ǝq�ǂ������́u�U��Ԃ�v���p���I�Ɋ��p����C���t�̎��Ɨ͂̌���ƁC�q�ǂ������̎��M�▞���x�����߂邱�Ƃɑ傢�ɖ𗧂��낤�Ǝv���܂��B
�@�����āC�C �q�ǂ������ɗ^����ϓ_�Ƃ��ẮC�u�ǂ������_�͂���܂����v�ȂǁC�m��I�ȕ\�����g�����Ƃ���ł��B
�@�Ȃ��C�D �q�ǂ������̕\���̒��ɁC����C�u�y���������v�C�u���ɂȂ����v�ȂǂƂ����P���ȕ\������ڗ��N���X�����Ȃ�����܂���B�Đ��Ɋׂ炸��ɑn�����ɕx�݁u�l����q�ǂ��v����Ă����ł��ˁB
5�D������
�@����́C�P�ʎ��ԓ��i����ЂƂ̎��Ɓj�̕]���ɂ��ċ�̓I�ɏq�ׂ܂������C����́C�w���C�܂���1�N��ʂ��Ă̕]���̎��g�݂ɂ��āC��̗�������Ȃ���l���Ă݂����Ǝv���܂��B
����́C�n糎��v�搶�ɁC�w���C�܂���1�N��ʂ��Ă̕]���̎��g�݂ɂ��āC���w���������������Ǝv���܂��B
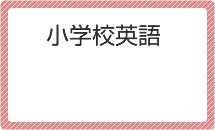 |
||
 |
||
 |
||