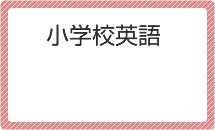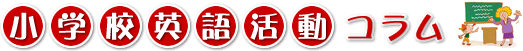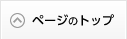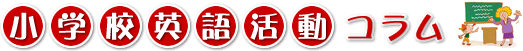
![[第22回]評価:小学校外国語活動をどう進めるか(1) ―学習指導要領と評価の在り方について](../img/e-english/title_022.gif)
渡邉時夫 (清泉女学院大学)
1.「外国語活動」の目標と評価の関係について
評価を考えるときは,目指すべき具体的な目標が明確でなければなりません。それでは「外国語活動」の目標を新しい『小学校学習指導要領』(文部科学省)で確認してみましょう。
第1 目標
外国語を通じて,言語や文化について体験的に理解を深め,積極的にコミュニケーションを図る態度の育成を図り,外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら,コミュニケーション能力の素地を養う。
そして『小学校学習指導要領解説』(文部科学省)によると,目標は次の3つの柱から成り立っています。
① 外国語を通じて,言語や文化について体験的に理解を深める。
② 外国語を通じて,積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図る。
③ 外国語を通じて,外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませる。
3つの目標すべてが,「外国語を通じて」行われることを明記しています。ただ,これだけでは,具体的にどのような内容の授業をするべきかが見えてきません。そこで,目標を踏まえ,第5学年・第6学年の2学年間を通じて達成されるべき内容として,次の2つの事項を設定し,それぞれの事項の内容についてはさらに詳しく説明しています。
第2 内容
〔第5学年及び第6学年〕
1.外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図ることができるよう,次の事項について指導する。
(1) 外国語を用いてコミュニケーションを図る楽しさを体験すること。
(2) 積極的に外国語を聞いたり,話したりすること。
(3) 言語を用いてコミュニケーションを図ることの大切さを知ること。
2.日本と外国の言語や文化について,体験的に理解を深めることができるよう,次の事項について指導する。
(1) 外国語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに,日本語との違いを知り,言葉の面白さや豊かさに気付くこと。
(2) 日本と外国との生活,習慣,行事などの違いを知り,多様なものの見方や考え方があることに気付くこと。
(3) 異なる文化をもつ人々との交流等を体験し,文化等に対する理解を深めること。
1は主としてコミュニケーションに関する事項について,2は主として言語と文化に関する事項について説明しています。そして,1と2を内容とする活動が外国語を通して行われることで,目標③の「外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむことができる」と考えられます。
2.評価の在り方について
目標と指導内容が明確になったところで,具体的な指導手順や指導方法を考えていきましょう。
Teaching Plan(指導案)を考える際には,常に評価の観点を意識し明確にする必要があります。つまり,授業を通してどのような結果が得られれば「良し」とするか,日々の授業や一定の期間を見通しての授業について,期待される結果や成果を常に分析的に評価していかなければなりません。
『児童生徒の学習評価の在り方について(報告)』(文部科学省,2010年3月24日)には,次のように記述されています。
3.学習評価の今後の方向性について
(2) 今回の学習評価の改善に係る基本的な考え
(目標に準拠した評価による観点別学習状況の評価や評定の着実な実施)
…中略…,各教科における児童生徒の学習状況を分析的にとらえる観点別学習状況の評価と総括的にとらえる評定とについては,目標に準拠した評価として実施していくことが適当である。
これによると,「外国語活動」については,学習指導要領に定める目標について観点を設定し,学習評価を行うことが適当である,としています。
そして「外国語活動」は教科ではないので,「指導要録」の表記を含め,数値による評価はなじまないとされ,文章による評価を行うことが適当とされています。
また,『小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)』(文部科学省,平成22年5月11日)の中では(別紙1),「外国語活動」の評価の観点について,学校の設置者は「外国語活動」の目標を踏まえ,下記(別紙5)を参考に設定するよう述べると共に,観点を追加して記入できる旨も明確にしています。
別紙1 小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等
〔2〕 指導に関する記録
2 外国語活動の記録
小学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)小学部における外国語活動の記録については,評価の観点を記入した上で,それらの観点に照らして,児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴を記入する等,児童にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。
評価の観点については,設置者は,小学校学習指導要領等に示す外国語活動の目標を踏まえ,別紙5を参考に設定する。また,各学校において,観点を追加して記入できるようにする。
別紙5 各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨
(小学校及び特別支援学校小学部並びに中学校及び特別支援学校中学部)
2.外国語活動の記録
(1) 評価の観点及びその趣旨
<小学校外国語活動の記録>
| 観点 |
コミュニケーションへの関心・意欲・態度 |
外国語への慣れ親しみ |
言語や文化に関する気付き |
| 趣旨 |
コミュニケーションに関心をもち,積極的にコミュニケーションを図ろうとする。 |
活動で用いている外国語を聞いたり話したりしながら,外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しんでいる。 |
外国語を用いた体験的なコミュニケーション活動を通して,言葉の面白さや豊かさ,多様なものの見方や考え方があることなどに気付いている。 |
なお規準については,国立教育政策研究所が,すべての教科について,今年(平成22年)8月末に案を,11月には確定した内容を公表する予定です。「外国語活動」については,教科ではないため公開されていませんが,今年度末までに事例という形で公表するようです(具体的に事例が出されるという,この部分が大切です)。
上記の「趣旨」を具体化し,授業のテーマや内容に照らして評価できるように,例えば下記のように,具体的な「基準」を設けるとよいでしょう。
例) 正月明けに「十二支」を扱った場合の基準
① 「十二支」が中国から伝わったことを知り,中国でも「子年」や「巳年」など,十二支があるが,十二番目は「イノシシ」ではなく,「ブタ」になっていることが英語を通して気付いていたか。
② 十二の動物について,英語とイラストが一致するようになっていたか。
③ ゲームでは,グループが仕事を早く完成できるよう協力していたか。
など
3.まとめ
授業の後,「規準」に照らして評価し,「規準」そのものの反省を含め,授業全体の改善を試み,次の授業の実践に活かすというプロセスを繰り返すことになります。これがPlan⇒Do⇒Check⇒ActのいわゆるPDCAサイクルです。評価の方法については,『小学校外国語活動研修ガイドブック』(文部科学省)にも一部が載っていますが,以下のような多様な方法が考えられます。その時々のねらいに応じて最善の方法を選択していただきたいです。
①子どもの行動観察,②子どもの発話観察,③子どもの作品評価(例えば『英語ノート』の提出),④子ども自身の振り返り,⑤子どもの相互評価,⑥聞き取り,⑦アンケート,⑧その他
また,どのような時間のまとまりで評価していくについては,単位時間,単元,レッスン,学期や年間が考えられます。
個々の授業や,学期や年間を通しての授業など,具体的な評価については,次回から述べていきたいと思います。
次回は,渡邉時夫先生に,長野県の或る小学校が最近実施した研究授業を取り上げ,評価の実際についてまとめていただきます。
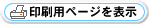
 小学校英語活動コラム バックナンバー 小学校英語活動コラム バックナンバー

  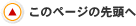
|