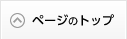『中学生の国語』Q&A
4 伝統的な言語文化について
1.新設の「伝統的な言語文化に関する事項」は,どのように教材化されていますか。
「本編」(必修)では,「伝統的な言語文化に関する事項」を取り立てた教材と,各領域の指導と関連させた教材との二つの柱で構成し,学習のさらなる充実を図りました。
一つめの柱である「取り立てた教材」では,学年冒頭の単元を「伝統的な言語文化」としました。長く語り継がれてきた優れた古典の音読・暗唱から一年間の学習を始め,また,日常生活と古典とのつながりに目が向くように構成しています。特に1年生では,小学校での国語学習との接続を考え,既習の古典教材を取り上げ,生徒が安心して,繰り返し学べるように配慮しています。
二つめの柱には「領域と関連させた古典学習」を位置づけ,古典作品を味わうなかで,領域学習と関連させながら,生活の中に古典を生かすことに主眼をおいています。引用したり,自分で考えて表現したりする活動を通して,古典が決して特別なものではなく,自分たちにとってより身近なものとなるように教材化しています。特に3年生では,後半教材だけでなく,学年冒頭の「伝統的な言語文化」単元でもこうした観点を加味しており,高等学校の古典学習への接続にも配慮しています。
2.『中学生の国語』の「本編」(必修)は,なぜ全学年とも単元「伝統的な言語文化」から始まっているのですか。
新しい学習指導要領では新たに「伝統的な言語文化に関する事項」が設けられ,以前にもまして「伝統的な言語文化」が重要視された点を考慮し,教材化を行いました。
「伝統的な言語文化」とは,いわゆる古典の学習だけではないと捉え,特に1年生では現代語・文語詩,和歌,俳句など韻文作品を声に出すことから学習を始めるようにしています。
また,学年はじめに持ちうる知識で十分に学習を進められるように,次の点に配慮しています。
① 作品には現代語訳を併記し,内容理解における負担を軽減すること。
② 作品紹介や古典を学ぶ意義などを平易な文章で掲載し,学ぶ意欲を高めること。
- 三省堂教科書
- 国語教科書
- 『中学生の国語』
- 『中学生の国語』Q&A
- 4 伝統的な言語文化について