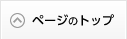『中学生の国語』Q&A
3 単元について
1.『中学生の国語』の「本編」(必修)では,単元を復活させたのですか。
従来よく見られた話題単元(テーマ単元)とは異なり,「言語能力単元」で構成しています。身につけたい国語の力を明確に示した新しい単元です。
2.各単元はどのような考えで,複数の教材を位置づけているのですか。
単元は,その単元でつけたい主な言語能力の育成を目指して教材を配しています。同じ単元に属する教材は,領域や学習活動が異なっても,目指す言語能力は同じになります。
例えば,1年生の単元「表現力2」(単元目標:わかりやすく述べる)には「読むこと」教材と,「書くこと」教材が位置づけられています。この場合,「読むこと」教材では,どのように「わかりやすく表現」されているかに着目して読むことが学習の中心になり,「書くこと」教材では,どのように「わかりやすく表現」するかが学習の中心になります。このように,「読むこと」と「書くこと」の両面から学習することで言語能力を育成します。
3.単元名の後ろについている言葉は何を意味していますか。
その単元で育成したい言語能力を,“学習活動として”生徒にもわかりやすい表現で示しました。何を学ぶのかが理解しやすいので,「学習の見通し」をもち,「主体的な学び」を促すことができます。 (例)1年「表現力1 的確に表す」
4.なぜ単元扉には問いかけがしてあるのですか? 配当時数はありますか。
単元扉の小さな問いかけは,その単元の学習と関連しています。「まずは自分で考えてみる」(自分の考えをもつ)ことから学習をスタートできるように配慮しました。
また,配当時間はありません。授業の導入として短時間扱ったり,授業以外の時間に生徒が自主的に読んで考えたりするなど,柔軟な取扱いが可能です。
5.「単元目標」と,各教材に示された「学習目標」とは,どのような関係がありますか。
「単元目標」にはその単元で育成すべき言語能力を示し,「学習目標」にはその教材を扱った学習指導で習得を目指すべき言語能力を示しています。
「単元目標」は,各領域を貫通した普遍目標・上位目標,「学習目標」は,領域ごとの具体目標・下位目標と捉えることもできます。
さらに,「学習目標」には学習活動も示しました。その言語能力は「どのような学習活動」を通して身につけようとしているのかが明確にわかります。
- 三省堂教科書
- 国語教科書
- 『中学生の国語』
- 『中学生の国語』Q&A
- 3 単元について