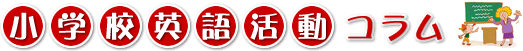
![[第28回]外国語活動必修化の初年度を振り返る(1)――小学校6年生ご担任の意識調査](../img/e-english/title_028.gif)
渡邉時夫
(清泉女学院大学客員教授・信州大学名誉教授)
1.はじめに
小学校の外国語活動は,必修化されてから1年が経ちました。前年度末(平成24年3月)に,長野県内の小学校6年生ご担任の教員を対象にアンケート調査を実施し,外国語活動について多面的考察を試みました。その一部を紹介しながら,「コミュニケーション能力の素地の形成」に関する教員の意識について考えてみたいと思います。
- アンケートの対象:まず,長野県の小学校の約半数(191校)を占める地域からその3分の1の学校(65校)を無作為で抽出し,さらにそれらの学校の6年生担任教員の中から無作為に1人ずつを抽出。
- 回収率:91%(65名中60名が回答)
- 調査方法:多肢選択と自由記述の質問に,郵送にて回答を依頼。
2.調査結果
(1)英語を聞き,話す力について
学習指導要領において小学校の外国語活動は,「基本的な英語」に慣れ親しむことになっています。授業者(担当教員)は,教育の成果について,どのように評価しているのでしょうか。
まず,英語を聞いたり,話したりする点について,担当教員による子どもたちの評価を見てみましょう。
下記の3つの質問に答えていただき,その結果がグラフです。
<質問1> 英語を聞いて理解する力は相当伸びたと思うか。
<質問2> 英語らしい発音が身についたか。
<質問3> 英語で自己表現できる子どもは半数以上いるか。
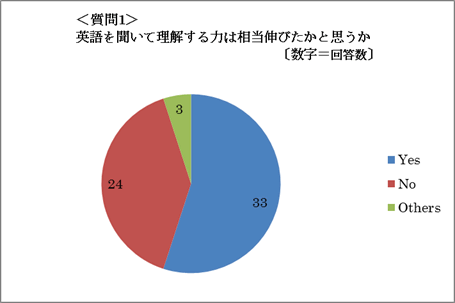
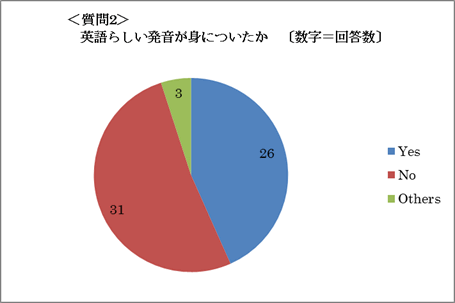
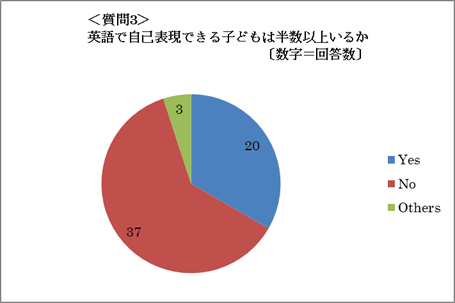
<質問1について>
「英語を聞いて理解する力」の育成は,外国語活動の中心的な目標です。「相当伸びたか」という表現が曖昧であったためかYesの評価が33校(55%)留りであったのはやや意外でした。反面,Noは全体の40%(40校)を占めていることも気にかかります。「英語がわかってきたぞ! 楽しい!」という子どもたちがもっと増えてほしいです。
この結果の背景として,指導に当たる教員が英語を話す機会が少ない,単に,What sports do you like? ―I like baseball.などのターゲット・センテンスを繰り返しているような授業内容が多い,子どもたちにとってわかりにくい英語を使い過ぎることなどが原因になっているかも知れません。
次のグラフをご覧ください。
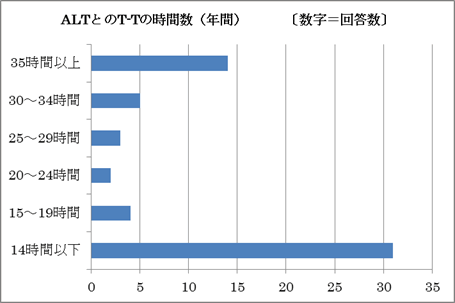
これを見ると,ALTとのT–Tの授業時間数が年間14時間以下だった学校が多いことがわかります(51%)。つまり,外国人のALT(Assistant Language Teacher: 英語指導助手)とのT-T(ティーム・ティーチング)の授業が少なく,英語のインプット量が十分でないことがその背景にあることも考えられるのです。
T-Tの授業時間数が年間30時間を超えている学校の67%が,「英語を聞いて理解する力」が伸びたについて,Yesと答えたのに対し,30時間以下の学校のではYesはわずか37%にすぎず,大きな開きがありました。さらに記述式で,「今後どのような改善を求めたいか」回答を求めたところ,90%の教員が「ネイティブ・スピーカーまたは英語のできる日本人のALTの増加」を求めていました。また,「外国語活動は英語のできる教員が担当すべきだ」というコメントも散見されました。
<質問2について>
「英語らしい発音が身についたか」の評価については,Noの回答が31校(52%)となり,Yesの26校(43%)を上回りました。「音声に敏感である」ことを大きな理由の1つとして英語を小学校に導入した経緯を考えると,授業の進め方や,ALTの配置であったりICT等の機器の充実など授業環境等に何らかの問題がないか,検証する必要があると思います。筆者は,多くの授業を参観させていただきましたが,わかりやすい英語をたくさん使うT-Tの授業を受けている子どもたちは,英語らしい発音を自然に習得している傾向が強いように思いました。今後は,英語のインプットの質と量について一層注目・留意する必要があるように思います。
<質問3について>
「英語で自己表現できる子どもは半数以上いるか」の評価については,下記程度の英語を想定して「学習した英語を使って自己表現できる生徒の割合」をたずねました。
“My name is Watanabe Tokio. I like sports. I like baseball very much. My birthday is June 30th.”
クラスの中で半分以上の子どもが,このような自己表現ができるという回答をいただいた教員は20校(33%)で全体の3分の1でした。残りの3分の2に当たる37校(62%)の教員によると,そのような自己表現のできる子どもはクラスの半分に満たない(あるいは一部に過ぎない)という評価でした。
(2)積極的な態度の育成について
「積極的な態度の育成」は,外国語活動の主たる目標の1つです(第25回)。学習指導要領には,「積極的な態度」の定義は抽象的であり,積極性の程度について明確にされていませんが,回答者の反応を見てみましょう。
下記4つの中から1つを選択していただき,その結果をグラフにしました。
「積極的な態度」を
(a)大多数の子どもが身につけた
(b)身につけた子どもは半数くらい
(c)身につけた子どもは一部のみ
(d)身についたかどうか疑問
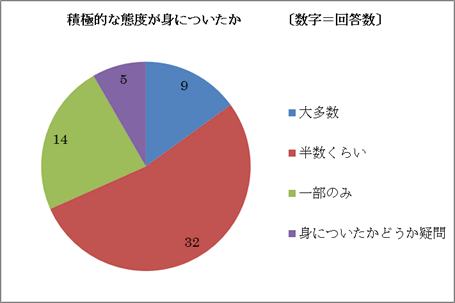
「大多数の子どもは積極的な態度を身につけた」と考えた教員は,60校中9校(15 %)に過ぎず,「半数程度か一部のみ」,と評価している教員は60校中46校(77%)にも及んでいます。「積極性を修得した子ども」は,クラスの中で半数以上いる,という意識を持った教員がもっと増えてほしいです。
積極的な態度について,筆者は,「英語の学習を通して,考え,気づき,自分の(個性的な)意見を明確にして,仲間や他人の前で,その意見を述べることができる姿勢」だと考えています。小学校の段階では,子どもたちは先生や仲間からの問いかけに対して,Yes,No,あるいは単語やフレーズひとつひとつをはっきり発音したり,逆に相手に対して聞きたいことをジェスチャーや絵などの実物を援用したりして,コミュニケーションの糸口を引き出す工夫のできる子どもを育てたいと思います。大声を上げて,ただゲームを楽しんでいるだけの子どもが,積極性があるとは言えません。
(3)素地の育成について
最後に,総合的な評価として,学習指導要領で示された「コミュニケーション能力の素地」を育成できたと言えるかどうかについて,たずねました。「コミュニケーショ能力の素地」については,聞いたり,話したりする英語力や積極的な態度だけでなく,文化やことばについての理解も含める必要があります。しかし,後者については,評価の難しさもあり,今回は,特定して調べることをせず,総合的に考えて「コミュニケーション能力の素地」が育成できたかどうか回答を求め,教員の意識を探ってみました。その結果は下記のグラフの通りです。
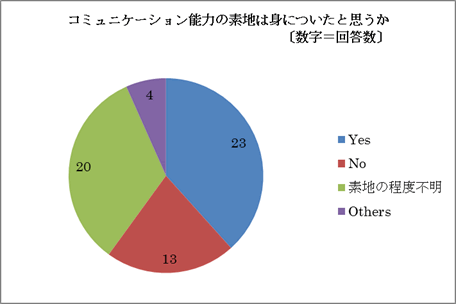
「できたと思う(Yes)」という回答は60校中23校(38%)に過ぎませんでした。注目すべきは「どの程度の成果があればコミュニケーション能力の素地を築いたことになるのか(素地の程度が不明)」という疑問をもっている教員が3分の1(20校)を占めている点であり,「素地を築いたとは思えない(No)」と回答した教員を含めると33校(55%)に上っています。
学習指導要領では,「コミュニケーション能力の素地を養う」ことが目標となっていますが,その内容と程度が明示されていないため,目標が定かではなく,教育上深刻な問題,と言わざるを得ません。このような状況で教育を進めていかなければならない直接的で主たる原因は外国語活動が「教科ではない」という事実だと思います。教科でないが故に,「教科書」もなく,「専門性」を持った教員もいない,という状況は再考しなければなりません。
3.おわりに
ALTの増員のALTの採用数については,自治体によって,放置できないほどの差がついているようです。これは,憲法で保障されている「教育の機会均等」の原則を考えると,深刻な情況だと言わなければなりません。しかも,今回の調査によって,ALTとのT-Tの多少が教育効果の差を生んでいることがある程度露呈された以上,各自治体(市町村),あるいは各都道府県で,この問題の解決に取り組むことが急務です。
また,小学校教員の多くが英語運用力向上のための研修を望んでいながら,自治体がその機会を計画的に提供していない現実もあります。教員の負担に配慮しつつ,効果的な研修の機会を工夫してほしいと願っています。
次回(第29回)は,4月に新入生を受け入れた中学校教員の意識調査の結果について述べてみたいと思います。
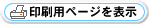
 小学校英語活動コラム バックナンバー 小学校英語活動コラム バックナンバー

  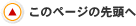
|

