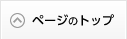|
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元 | 単元ごとの活用率(%) ※70%以上の活用率に色をつけた |
比較的好評だった単元(○印) 比較的不評だった単元(×印) |
||
| グループA | グループB | グループA | グループB | |
| Lesson 1 世界の「こんにちは」を知ろう | 100 | 89 | ○ | ○ |
| Lesson 2 ジェスチャーをしよう | 89 | 56 | × | × |
| Lesson 3数で遊ぼう | 100 | 89 | ―― | × |
| Lesson 4 自己紹介をしよう | 100 | 78 | ○ | ○ |
| Lesson 5 いろいろな国の衣装を知ろう | 78 | 44 | × | × |
| Lesson 6 外来語を知ろう | 100 | 67 | ○ | ○ |
| Lesson 7 クイズ大会をしよう | 78 | 67 | ○ | ―― |
| Lesson 8 時間割を作ろう | 67 | 89 | × | × |
| Lesson 9 ランチ・メニューを作ろう | 67 | 89 | ―― | ○ |
| Let’s Enjoy 1 “Head, Shoulders, Knees and Toes”, サイモン・セズ・ゲーム | 44 | 56 | ―― | ―― |
| Let’s Enjoy 2 かくれている動物さがし | 22 | 33 | ―― | ―― |
| Let’s Enjoy 3 英語コミュニケーションすごろく | 33 | 22 | ―― | ―― |
(3) 調査結果からみた『英語ノート』の活用実態
アンケートの結果から,次のことが分かりました。
①いずれのグループにも,『英語ノート』をまったく使っていない学校はありませんでした。これまでのところ『英語ノート』の重要度の高さははっきりしており,『英語ノート』を仕分けの対象とした政府の選択は誤りであったと指摘できると思います。
②全体的にグループAの『英語ノート』の活用率が,グループBと比べ,比較的高いことが分かります。ALTの授業参加が少なく,担任の教師(HRT)が『英語ノート』に頼っている様子が読みとれます。
③グループBの場合には,主としてALTが独自に用意した教材を使ったり,また学校や地域で積み重ねてきた独自の教材を主として活用したりして,『英語ノート』は補助教材として使っている学校が多いようです。
④グループAの活用傾向を見ると,Lesson 7以降は,それまでのレッスン(Lesson 1〜6)と比べ,活用率が徐々に下がっています。取捨選択をせず,Lesson 1から始めて順を追って『英語ノート』を活用している様子がうかがえます。平成21年度は移行期間でもあることや,学校行事などが入ったりして,35時間をフルに「外国語活動」に充てられない学校が多いことも理由の1つかもしれません。平成23年度からは,学校行事や指導計画の調整などを行うことで,すべてのレッスンを活用する学校が増えてくるのではないかと予測されます。
⑤グループBの場合には,『英語ノート』の内容を取捨選択して活用していることが分かります。
⑥Lesson 1, 4, 6の3レッスンは,両グループ共に好評で,一方,Lesson 2, 5, 8の3レッスンは,両グループ共に不評だったことが分かります。将来,改訂する計画があれば,この資料を参考にしてほしいと思います。
⑦3つのLet’s Enjoyは,両グループとも活用率が低いので,その原因を明確にする必要があると思います。
3. 『英語ノート』の改善への提言
今回のアンケート調査の過程で,小学校で長年英語の指導に携わってこられた先生方やALT(複数名)からさまざまなコメントをうかがいました。それらをふまえ,『英語ノート』の課題について筆者の考えを述べたいと思います。
(1) 語彙や英文について
異文化理解とコミュニケーションを大きなねらいとしていることは高く評価できますが,語彙や英文の提示について,レッスン間の連携に配慮が欠けているように思います。特にLesson
5は,新出語彙や構文が多く,困難であると感じた学校が多かったようです。アンケートの結果を見ても,このレッスンは,両グループ共に比較的評価が低くなっています。
(2) 題材の取扱いについて
異文化の紹介が,やや偏しているように思います。題材の選択や発想などの視点に,柔軟性や多様性を求めたいと思います。ALTもその点について,危惧しているようです。例えば,Lesson
5の衣装の紹介というテーマ自体はわるくはないのですが,もっと多様な国を登場させてもよいのではないでしょうか。『英語ノート』だけを使用する場合の大きなマイナス点にもなりかねません。その点では,『英語ノート』は,あくまでも補助教材として位置づけることが望ましいかもしれません。また,現場の先生からは,Lesson
8は教科名が多いため,子どもたちにとって負担が大きすぎるという批判もありました。
(3) チャンツについて
チャンツが全体として短すぎるのではないかと思います。もう少しだけ長く,しかも内容があり,子どもたちの興味がわく作品を選んでほしいと思います。
(4) 指導資料について
指導資料は,簡単なものでいいので英語版も必要と思います。日本語の読めないALTも少なくないからです。また,日本語版の内容をALTに伝えるほどの英語力がないHRTが多く,指導資料の内容を充分理解し,活用できないALTが少なくないようです。今回の調査で,この点について悩んでいるALTが多いことも分かってきました。
(5) 『英語ノート』の付属CDについて
子どもたちには英語のインプットを多量に与え,場面や文脈からメッセージのおよその内容が理解できるような力(素地力)を身につけさせたいという願いを持っている教員が多いと思います。しかし,そのためには,『英語ノート』の付属CDの内容をもう少し豊かにし,例えば,もっと繰り返したり,スピードを速くしたり遅くしたりするなどの工夫がほしいと思います。また,CDなど音声を用意する際は,場面や役割を考慮して人材を選ぶなどの工夫により,多様な英語のlistening
inputが提供できるよう改善してほしいと期待しています。
4. おわりに
前回の号から,行政刷新会議「事業仕分け」に触れながら『英語ノート』の今後について考えを述べ,また独自に行った調査をもとに,内容の改善点をいくつか指摘させていただきました。『英語ノート』が平成24年度以降も継続して無償配布されるのか定かではありませんが,改訂の仕事を怠ることはできません。個人的にも,そしてマスコミや学会などを通して,文部科学省にはこの点を強く要望したいと思います。
なお,次回の号では,『英語ノート』を補うのに相応しい教材について考えてみたいと思います。
《参考文献》 『英語ノート 1』(文部科学省)
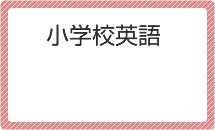 |
||
 |
||
 |
||
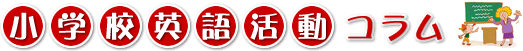
![[第17回]『英語ノート』について ② 「『英語ノート』活用実態報告と『英語ノート』改善への提言」](../img/e-english/title_017.gif)