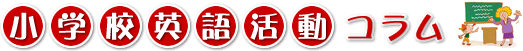
![[第15回]研修について―その2 ことばや文化の指導に関する研修のポイント](../img/e-english/title_015.gif)
渡邉時夫 (清泉女学院大学)
1. はじめに
「外国語活動」を前倒しして実施している中都市の小学校(全部で6校ある内 の4校を対象)で,「ことばや文化の指導」について聞いたところ,41%の先
生がどうしてよいか困っていると回答し,22%の先生は,学校の方針がはっきりしていないので,個人的に実践している,と回答していました。「総合的な学習の時間」の枠内で実施していた頃は,異文化(国際)理解を指導の中心に置いていたが,「コミュニケーションの素地を養う」ことを目標とする「外国語活動」になって,「ことばや文化」を授業の中でどう扱うのか,悩んでいる教員が多いことが伺えます。
そこで,今回は「ことばや文化」の指導に関して,どのようにして学んだらよ いか,研修の方法について考えてみたいと思います。
2. さまざまな先生の授業を参観すること
県教委や市町村教委,さまざまな研究会等が主催する研究授業をできるだけたくさん参観することをお勧めします。異文化理解教育に関する書籍や専門家の講演から学ぶこともできますが,何と言っても生の授業を参観することが一番です。授業の進め方だけでなく子ども達の反応からも学ぶことができるからです。出身国や文化背景の異なるALTによって,取り上げる話題やテーマが異なる点も魅力です。他校のALTやTTの授業から文化やことばについての指導のあり方を学び取りましょう。筆者の経験から3例を挙げてみます。
その1 スコットランド出身のALT
− Can you〜?がTarget
子ども達が日本の「お手玉」の遊びを紹介しようと計画し,“Can you play otedama?” と聞いて,扱うお手玉を3つ,4つと増やしていきました。ところが,ALTが5つ,6つを難なく使えることが分かり,子どもたちはびっくり仰天。スコットランドでも「お手玉遊び」があることを知り,少し視野が広がりました。話が進んで,話題がお手玉の中に入れる物に及びました。日本では小豆を使うことが多いのですが,スコットランドでは羊の骨を小さくして使うことを知りました。スコットランドでは土地が痩せているので野菜などの栽培には適さないため,羊を飼うことが一般的であり,お手玉を作るにも羊を使っているようです。子ども達は,環境と生活がいかに密接に結びついているかを,
間接的に学んだのです。また,活動を通して学ぶ,という英語活動のねらいに沿った授業でした。
その2 オーストラリア出身のALT −
How do you go, bus or train?がTarget
雪のある日本にはサンタがそりに乗ってくるけれど,雪のないオーストラリアにはどのようにして来るのだろうか。子ども達に一瞬考えさせた後,隠し持っていたサーフボードに乗ってやっているサンタの絵を見せたところ,子ども達には大受けでした。また,オーストラリアのサンタは,靴下の中ではなく,クリスマスツリーの下にプレゼントを置いていくことを知って,二度びっくり。子ども達の世界が一気に広がりました。
その3 シンガポール出身のALT /
アメリカ出身のALT − What do you eat? がTarget
食べ物が話題になり,シンガポール出身のあるALTは,イギリスの影響が強いシンガポールではfish-and-chipsを食べることを紹介しました。子ども達はchips
がfried potato と同じ物であること,同じものがアメリカではFrench fries と呼ばれていることを初めて知りました。 同じ食べ物が,3つの国で異なった単語で呼ばれていることに驚いたようす。
また,ピザを話題にしたクラスがありました。
アメリカ出身のあるALTは日本人が好むピザと彼女がアメリカで常食していたピザを示し,日本人はマヨネーズやコーンを具にしたピザを好むがアメリカ人はそのような具は使わないという話をしました。この時子ども達は,chips
の場合とは逆に,pizzaという同じ英単語が国により異なった食を表していることを知りました。「名前」と「物」との関係を知った貴重な体験でした。
3. 教育委員会等の研修会で勧めたい学びについて
専門家や指導主事などの講義から学ぶことも大切ですが,このような機会に ぜひ取り入れて欲しいのは,グループに分かれての情報交換です。主催者側が,参加者に事前準備をして出席するよう要請しておくことが必要です。例えば, 次のような進め方はいかがでしょうか。
(1) 実践した「文化やことば」の指導について下記の視点から具体的に発表し合う。
(a) TTか,単独か (b) テーマ (c) 言語材料
(d) 使用した教材(できるだけ持参する) (e) 指導手順
(f) 成果と改善点
(2) それぞれの発表の直後に,質問,感想,改善点などについて意見交換
(3) 発表の中から一般化できそうな実践を選んで,実演してもらう。
筆者の参加したグループでは下記のような発表がありました。
(1)
単独指導。colorsをテーマ。”How many 〜 are there?” 果物や野菜などを題材にした後,中国の国旗を取り上げた。”How
many stars are there in the Chinese flag?”大きな星は共産党,4つの小さな星はそれぞれ労働者・農民・知識人・民族資本家を表していることを教えた。
(2) Colors とshapes をテーマ。世界の国旗を題材に。星を用いた国旗や,赤,青,白,黄が多く使われていることに気づいた。日本の国旗も白と赤であることに再認識。星の大きさや数に意味があることに気づいた。
(3) カナダ人ALTとのTT。日本とカナダの学校給食の比較。カナダではなぜ食事を選べるシステムになっているのか,その歴史的背景などを学んだ。
上記のように興味深く,参考になりそうな発表にたくさん触れることができるでしょう。各自持ち帰って実践してみることはもちろんのこと,学年会や英語活動の担当者の会などで話題にしてほしいと思います。
4.個人レベルの研修
毎日が研修です。参考書,インターネット,ラジオやテレビ番組(例えばNHKの『BEGIN Japanology』)など,英語や異文化についての情報は無尽蔵です。「ことばや文化」について個人研修として今回特に次の2つをお勧めいたします。
(1) 外国人による日本語弁論大会やそのビデオなど
一般に外国人による大会や,中国人など特定の国籍の人による弁論大会などが頻繁に開催されています。市町村の教育委員会主催のものも多く,ビデオの入手などもそう難しくありません。NHKは,毎年開催しています。外国人のスピーチにより,日本文化や日本語について意外な事実に気づかされることがあり,授業にも使える題材が少なくありません。例えば,英語と違って日本語は「ピッチ(pitch)」を重んずる言語であるため,「葉が黄色い」と「歯が黄色い」の発音の区別をしていることや,「テレビ」を単独に言う場合と「テレビ番組」と言うときでは「テレビ」の発音を変えている,ことなどが外国人にとっては大変難しいことなどを,最近外国人のスピーチで聞き大変おもしろく感じました。子ども達にも是非経験させたいと思いました。
(2) ALTなど外国人から学ぶ姿勢を常に持つこと
いつも知識欲を強く持ってALTなどに接していると,英語と日本語との違いなどに気づく力が育ちます。例えば,日本語の「指」を取り上げますと,手だけでなく足にも使っています。しかし,英語では手の場合はfinger,
足の場合は,別の単語(toe)を使っています。日本語では,足の「親指」とか「小指」と言うことはありますが,足の「人差し指」とは言いません。また,日本語では人を差す時に使う指を「人差し指」と呼んでいますが,アメリカなどでは,指で人を差すことはタブーとされています。また,英語では鼻と上唇の間の部分は唇の一部と考えられ,He
grows moustache on his lips.などと言うそうですが,このような情報は書物ではめったにお目にかかることができません。いわゆる「口コミ」によって得られる情報です。このようなinquisitive(知識欲のある)な姿勢は,異文化やことばを学ぶ時には最も大切な資質と言えると思います。
5.おわりに
ことばや文化を学ぶためのさまざまな研修方法や場面について述べて見ました。しかし,教員一人ひとりの学ぼうとする姿勢こそが最も大切だと思います。ことばや文化について気づく力を高め,それによって得た知識や経験を教員が互いにシェアし,英語を使いながら楽しい英語活動を作り上げていきましょう。
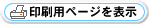
 小学校英語活動コラム バックナンバー 小学校英語活動コラム バックナンバー

  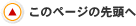
|

![]()

![]()