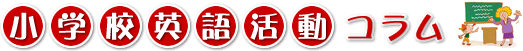
![[第5回]小中学校の先生が求める「外国語活動」の目標と課題〜 これまでの議論の整理 〜](../img/e-english/title_005.gif)
渡邉 時夫 (清泉女学院大学)
1 具体的(現実的)な目標をどう捉えるか
「新学習指導要領解説」(文部科学省,以下「解説」)では,外国語活動の目標は次の3つから成り立っています。
外国語を通じて,
① 言語や文化について体験的に理解を深める。
② 積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図る。
③ 外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませる。
上記の目標に向かって努力すれば,「コミュニケーション能力の素地」を養うことができる,というわけです。しかし,①〜③のいずれをとってみても,これらの文言だけでは目標の内容や程度が曖昧に感じられます。そこで,これまでのコラムをご執筆いただいた3人の先生(西澤先生,小山先生,水野先生)のお考えを整理し,「目標」を一層明確にしてみたいと思います。
3人の先生のお考えが共通で,中身もはっきりしているのは,②と③についてであり,特に③については具体的でわかりやすかったと思います。最も大きな考え方の柱は,「話す」ことよりも「聞く」活動に重点をおきましょう,ということでした。しかも,単語や英文を正確に聞きとるのではなく,先生などが話すときに補助として使うイラスト,写真,実物,地図,表や図形,先生のジェスチャーや表情・声色などにヒントを得て,「話の概要」を捉える力の育成を目標としたいと述べています。このことを目標として授業を進めると,子どもたちは「自分は英語がわかる」という自信が持てるようになり,必然的に英語の授業が楽しくなり,結果的にコミュニケーションにも積極的になる,というお考えでした。
「正確な英語を話す」ことを強要される従来の英語の授業とは雰囲気が異なり,子どもたちは楽しい雰囲気の中で,英語のinputを浴びる授業を受ける確率が高くなるでしょう。小学校では正確な発音や文法的に正しい英文を沢山覚えることよりも,英語特有のリズムやイントネーションの習得を最も大切にしたいものです。
「解説」にも,「積極的な態度とは,外国語を注意深く聞いて相手の思いを理解しようとしたり,自分の思いを伝えることの大切さを実感することだ」と述べています。
What sports (food) do you like? I like tennis. Can you
play baseball well? Yes, I can.など情報のやりとりに必要な簡単な会話力は,先生や友だちの英語をしっかり聞く活動の結果として身につくものだ,という考えも3名の先生に共通です。
従来の英語教育では,ともすれば発音の正確さが強調され過ぎる傾向が強くありました。そのために,英語を運用することに自信を失ってしまった日本人がどんなに多かったことでしょう。西澤先生は,「native
speakerの英語を目標とするような時代は,もう終わりにしよう」と提案しています。国際補助語としての英語を目標とする考えに私も大賛成です。
日本人には,日本人特有のアクセントや英文の使い方もあることを肯定すべきです。実は,小学生は,英語が専門ではない担任の先生がネイティブスピーカーのALTなどと立派に英語でコミュニケーションしている姿を見て,自然にそのような認識をもつようになっています。韓国人の英語も中国人の英語も英米人の英語も,国際補助語としては,価値に優劣はありません。水野先生は,「すべての言語と文化に同等の価値がある」という公平な価値観を学ばせたいと提言されていました。①の「言語や文化について理解させる」ことの一番重要な点であり,柔軟性のある小学生には,ふさわしい学習目標であると思います。そのような教育観に沿って授業が進められるとき,小山先生が力説されているような「positive
attitudeを身につけた生徒の育成」が外国語活動を通して実現されるのだと思います。
2 「目標」に係わる課題
「解説」が目標の第一に取り上げている「言語と文化についての理解」は,具体性に乏しく,中身が曖昧なところがあると思います。例えば,「解説」は,他の2つの目標と同様,言語と文化の理解も「外国語を通して」なされなければならない,と述べています。それに対して,水野先生は,「日本語で教育してもよい。ただ,体験させて終わり,というやり方はまずい。必ずfollow-up
が必要だ。目指す価値観を自然に身につけることは難しいからだ」と提案されました。水野先生の意識の中に,言語や(自文化を含めた)文化について,すべて英語で理解させることは小学生には難しいという想いがあるのでしょう。小山先生と西澤先生は「文化の理解」の重要性は述べていますが,その内容と指導法については触れていませんでした。言葉や文化については,英語を通して理解させることは可能だと思いますが,その中身や方法が具体化されておらず,多くの先生に共有されるところまで至っていない,ということでしょう。このことについては,次回から「指導法」について,様々に実践されている小中学校の先生に,具体的に発表していただくことになっていますので,ご期待ください。
3 言葉と文化について
また,言葉や文化についての指導に係わって,「解説」の中身に一部不安な点があるので,ここで指摘させていただきます。「解説」は,次のように述べています。
「文化に関しては,理解を深めることに留まらず,例えば,地域や学校などを紹介したり,地域の名物などを外国語で発信することなども考えられる。」
この点について,皆さんはいかがお考えでしょうか。自分の学校についての紹介として,例えば,次のような表現を想定してみましょう。
My school stands near the center of my city. It has
many large buildings.
My school buildings are very high. You can see my school from many
parts of the city. About 1,000 students are learning in our school. My
classmates like baseball. Every day we play baseball after school.
このように,英語で発信することを求めすぎると,子どもたちは次第に自信を失い,英語に興味を失っていく者もでるかもしれません。英語で独自の考えや気持ちを表すということは思いのほか難しいということを,誰もが,認識する必要があります。
(top-down的に)聞いて理解することを主たる目標にする必要性を述べてきましたが,問題は,誰が英語を話すのか,ということです。十分な数のALTの先生は間に合っていない。 中核教員から研修が始まりましたが,外国語活動を担当する教員すべてが研修を受け,少なくともCDやDVDを活用して,十分なinputを子どもたちに浴びせることができるほどに英語の力量をあげるまでにはかなりの時間を要するでしょう。
ご参考までに,長野県内の小学校の先生の中から無作為に選んだ120名を対象にアンケート調査をし,英語を教えた経験と他の教員の英語の授業を参観した経験の割合についてグラフにまとめてみました(グラフ1:年間担当時数,グラフ2:他の教員の授業参観経験割合)。果たして,上記の目標が十分に達成できるのか,非常に心配に思えました。こうした事情は,長野県に限ったことではないと思います。ほとんど100%の回答者が,ALTの先生とのT-Tが実現できるよう,条件整備をお願いしたい,と切々と訴えています。政府には,その責任を着実に果たしていただくよう,切望いたします。
<グラフ1>
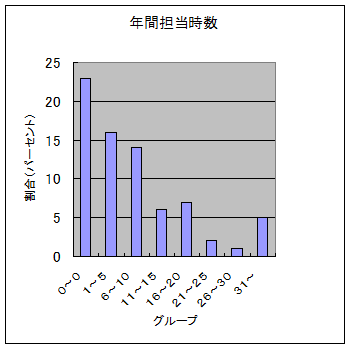
<グラフ2>
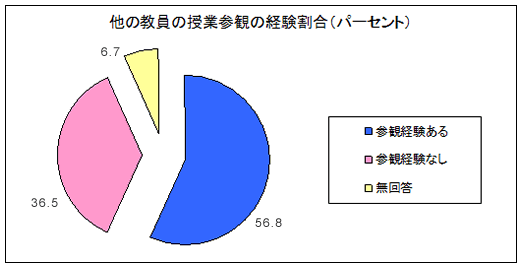
渡邉時夫(清泉女学院大学)
次回は,「指導法」について,小中学校の先生に,具体的に発表していただきます。
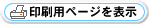
 小学校英語活動コラム バックナンバー 小学校英語活動コラム バックナンバー

  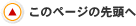
|

![]()

![]()