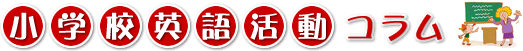
![[第4回]中学校が期待する「外国語活動」の中身](../img/e-english/title_004.gif)
水野 知也(福島県福島市立蓬莱中学校教諭)
1 はじめに
小学校の英語の授業参観,小学校の先生方とのティームティーチング,また,小学校と中学校の連携についての話し合いなど,小学校の先生方と関わる機会が多くなりました。それらを通して感じていることは,小学校の先生方に対して期待する外国語活動は,先生方が実践しやすい方法と内容であることが最も大切であるということです。このことは,消極的に聞こえるかもしれません。しかし,当然のことながら,先生方は,外国語活動だけを行っているのではありません。学級経営と教科指導を同時進行しながら,校務や生徒指導をもこなしています。多忙な日々の中で,新しく外国語活動を行うわけですから,特別な労力を注がなければできない方法や内容では,準備・計画された活動の完璧な効果を期待することはできません。年度の目標を算数指導としている先生にも,生徒指導を研究している最中の先生にも同じように実践していただくには,実施可能性(取り組みやすさ)を最重視したものにすることがとても大切であると考えます。
2 言語と文化に対する公平な価値観の育成
それでは,小学校の外国語活動に期待することについて述べたいと思います。まずは,すべての言語と文化は平等であるという価値観の育成です。このことは,将来,国際的に活躍する可能性のある子どもたちには不可欠な価値観です。世界中にはさまざまな言語があります。英語は,その中の1つの言語にすぎません。「英語は,タガログ語よりエライ」などといった,言語間に優劣など存在しません。言語はどれも平等です。また,文化についても同様です。箸やスプーンで食事をする文化は,手で食事をする文化より上等であるなどというのは間違いです。これは,文化の違いであり,自文化と違う文化を軽蔑することがあってはいけません。刺身として魚を生で食べる日本文化に対して「魚を生で食べるなんてグロテスク!」などと軽蔑されたとしたら,日本人として不快に思うのと同じです。そして,すべての言語と文化は平等であるという価値観が,私たち教師にもきちんと備わっているのか?と,自らを意識的に見つめなおすことも忘れてはいけないと思います。
この価値観を養う授業は,必ずしも英語でなくても行うことができます。また,道徳や総合学習の授業と関わらせることもできます。映像や写真の活用や,地域に住む外国出身者の協力,また,他言語や異文化とふれあう体験活動や自文化と他文化の比較を通して,言語や文化を平等に捉える価値観を教師が明示的に示します。このようにして,継続的に子どもたちに考えさせれば価値観を養うことができます。ここで注意しなければいけないのは,「体験させて終わり」ではだめだということです。必ず教師の導きが必要です。地域によって異なるかもしれませんが,子どもたちの普段の生活の中でそのような価値観に自然と気づくことはかなり難しいからです。
3 英語のリズムの豊富な体験
次に,英語のイントネーションやアクセントなどのリズムを数多く体験することです。日本語と英語の大きな違いの1つにリズムがあります。このリズムを,CD,DVDやPCを使って,教師(担任の先生)も一緒に体験するというスタイルの授業を提案したいと思います。担任の先生がモデルとなって教授するという授業は,私たち中学校の英語教師が,今年度から音楽を指導しろと言われても無理であるのと同じように,すべての小学校の先生方に実践していただくのは,すぐには不可能です。したがって,先生方も子どもたちと一緒に体験しながら,自らも学ぶというスタイルがよいのではないでしょうか。強弱で表現する英語のリズムを知識で知っていれば,「『赤』は『レッド』ではなく,『レーッ』のように聞こえるね」と,体験後に教師が示していけばよいのです。このようなスタイルの授業は,もしALTの先生がいらっしゃらない場合でも,日本人の担任の先生だけでも行うことができます。加えて,授業を通して日本人である小学校の先生方も英語のリズムを学習することができます。こうした経験を積んでいけば,将来的には,小学校の先生方が自らモデルとなって授業を行うことができるようになるでしょう。
4 生活におけるコミュニケーション
学校や学級で毎日行われている活動の中に英語で行うことができるものがないか探してみるのも1つです。例えば,毎朝の健康観察時に,“How
are you?” “I feel 〜.”のようなやり取りが可能です。また,道徳や総合学習で活動を行うときに,英単語を用いたり,自己開示のために自己紹介表現を使ったりすることも考えられます。これらの場面は情報のやり取りを目的としていますから,まさに本物のコミュニケーションということができます。そのための事前指導として外国語の時間を活用すればよいのです。
5 まとめ
以上のような価値観を備え,英語のリズムを多く体験した子どもたちが,多くの表現や音声を中学校で学ぶという形が広く行われることを願っています。そして,1つの中学校区にある小学校と中学校の先生方が多くの対話を持ち,互いの授業を見合うことで,スムーズな小中連携が図られることを期待します。
水野
知也 (みずの ともや)
福島県福島市立蓬莱中学校教諭。中学校教職12年目。教職7年目と8年目に,福島大学大学院で,日本人中学生のリスニングストラテジーとリーシングストラテジーの研究。教職10目と11年目に,現職教育主任として小中連携に携わる。教職12年目の今年度は,自分の中学校区の小学校と英語の連携を行っている。
〜水野知也先生の提言を受けて〜
中学校の英語の先生方から小学校外国語(英語)活動への要望を求めますと,次のような内容が目立ちます。
(1) アルファベットの大文字小文字程度はきちっと書けるところまで指導して欲しい。
(2) 身の回りの物(名詞)や基本的な動詞や形容詞ぐらいは文字を見て読めるようにして欲しい。
(3) 素地力として基本的な発音(特に母音)や英語らしいリズムとかイントネーションについては正しく発音できるように教えて欲しい。
(4) 誤った文(例えば,I have a many book. I like a baseball. He like a coffee.
など)を身につけてしまわないように注意して欲しい。
水野先生は,上記の内,主に(3)のリズムとイントネーションについて,触れてくださいました。水野先生はご自分でも小学校で英語活動を指導されてますので,小学校の事情を考慮されてのことと思います。コラムの中でも「実施可能性を最重視したものにすることが大切である」と述べられていますが,大変重要なご指摘と思います。
(3)の他に,水野先生は「すべての言語と文化は平等だという価値観」を育成することを提案されています。 英語に関する素地力ばかりに気を取られ,忘れられがちですが,このことは「外国語活動」の最も大切な狙いの1つだと思います。私も水野先生と同感です。自文化中心主義から脱し,文化相対主義を身につけるための素地力を養う教育には最大の関心を傾けるべきだと思います。
水野先生は,「この価値観を養う授業は,必ずしも英語で行わなくてもよいのではないか」と提案しておられますが,この点は皆さんいかがお考えでしょうか。私が見聞きし,また,自分でも直接関係した多くの授業を省みたとき,英語で行うことも十分に可能であるし,英語を通して行われる授業であるがゆえにむしろ,子どもたちには異文化や自文化のことについて一層鋭角的に「気づき」もあるように思われます。
最近経験した授業では,イギリスのchips は,アメリカではFrench fries, 日本ではfried
potatoes(フライイド ポテト)と呼ばれることがテーマでした。もちろん英語を通してですが,子どもたちは,文化により同じ物が異なった名前で呼ばれていることに気づきました。逆に,しばらく前に,pizza
を話題にしたとき,アメリカ出身のALTの先生から,アメリカでは日本のようにマヨネーズやコーンは使わないと聞いて,ピザは世界中どこでも同じものと思っていた子どもたちは大きく驚きました。このようにして,英語を通して子どもの世界観が徐々に広がり,自文化から解放されていくのだと思います。
先生の表情やジェスチャー,絵や写真やイラスト,地図や実物などを駆使しながら,先生やALTの先生(non-native
speakerを含めて)が英語の使い方を工夫して,子どもたちに分かるように英語をインプットすることを通して,子どもたちは英語によるコミュニケーションの素地を築いていくものと信じます。
ただ,そのように英語を使うことを小学校の先生に要求することができるのか,という問題があります。トップダウン的に与えられた英語のインプットを理解していく過程こそが素地を形作っていくことを考えると,上記のことは,是非HRTとALTの先生とが,真剣にチャレンジして欲しいと思います。また,来年度からは,中学校や高校の英語の免許状しかない人も,小学校で正規に外国語活動を担当できるようになりましたので,私の提案についてはさらに可能性の高いものとして是非ご検討いただきたく思います。
また,文字の指導についてですが,(1)は可能な範囲と思いますが,(2)のような強い要望は押し付けない方がよいと思います。ただし,日常の授業では,単語や簡単な表現などをいわゆるsight-wordsとして意図的に子どもたちの目に触れるように心がけて提示することは必要と思います。やり方次第では,ゲームなどの内容も豊かになるでしょう。 水野先生もご指摘されていますように,小学校の先生のご負担をあまり過剰にしない配慮が必要です。反面,従来は,中学校で初めて英語を学び始めるため,生徒の知的レベルを考慮して,学習内容の量と質の両方が急ピッチで進んでしまった点を考慮し,小学校英語の導入を機に,中学校の「無理」が多少でも解消される方途がないか,検討することも大切だと思います。
渡邉時夫(清泉女学院大学)
次回は,第2回〜第4回に登場していただきました先生方のご提言受けて,小学校英語活動の目標について,渡邉時夫先生におうかがいしたいと思います。
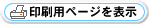
 小学校英語活動コラム バックナンバー 小学校英語活動コラム バックナンバー

  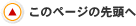
|

![]()

![]()