|
 ���ҏЉ� ���ҏЉ�
�X�Z�@�q�i���肸�݁@�܂���j
1942�N�����s���܂�B�����w�|��w��w�@�C�m�ے��C���B�V�h�j�[��w��TEFL��Diploma�擾�B��������,
��ȏ��q��, ����̋��E���o��, ����, �����ё�w��w�@�����E����w���_�����B���͉p�ꋳ��w�E���ꕶ������w�B��ٌ��ꋳ���ʂ��Ăǂ̂悤�Ȑl�Ԃ��������ő�̊S���B�����E�_���ɂ�,
�w�p�ꋳ��w�����C�u�����[�x(���� �O�ȓ�), �w�p�ꋳ��Ɠ��{��x(���� �����o��), �����Ȋw�Ȍ���ϋ��ȏ����w�p New
Crown English Series (��\���� �O�ȓ�), �����Z�pExceed English Series (��\����
�O�ȓ�), 'Simplification in Tok Pisin and Esperanto' (�w��ȏ��q��w�I�v�xNo.21),
�u�p�ꋳ���ޘ_ (1)�|(12)�v �����Ёw����p�ꋳ��x��29����1�`12���j�Ȃǂ�����B
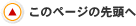
 �܂����� �܂�����
�@�{�������ɏo�邫�������́A1979�N���炠�鏬���q�ŒS�����Ă����A�ڂł���B�u�P��̕����I�Ӗ��v�Ɩ��ł��āA����A�p��̒P���1�����グ�Ă����B���e�́A���̒P��̓��p��r�����_�I�ȉ���ł���B���̘A�ڂ�50�����������A�ҏW������y���ǂݕ��Ƃ���1���ɂ܂Ƃ߂Ăق����|�̗v�����������B
�@����͕M�Ҏ��g�̖]�݂ł����������A���̂܂o���̂͂����ɂ��s�\���ł���B���グ�Ă���ꐔ�����Ȃ����A���̑I������ӓI�ł���B�N��2�`3��̘A�ڂ̂��і��ɁA�M�҂��������������ł���Ǝv�����P����A����Ώ���ɑI��ł����ɂ����Ȃ��B
�@�����ŁA�����Ȃ�Ƃ����グ��ꐔ�𑝂₵�āA���グ��P��̕���̒��������݂��B�܂��A�{�̂̑O�i�K�Ƃ��āA���Ƃƕ����̊W����p������̔��z�@�̈Ⴂ�Ȃǂ����グ�邱�Ƃɂ����B�������邱�Ƃɂ���āA�P��̕����I�Ӗ����Ր}�I�Ɍ�����ƍl��������ł���B
�@�������āA�{���͑�1���u����E�����E�v�l�v�A��2���u�P��̕����I�Ӗ��v��2���\���ɂȂ��Ă���B��1���͂���Α��_�Ȃ������͂ł���B�u�T�s�A=�E�H�[�t�̉����v�ɂ͂��܂�A�u�Ӗ��̂���v�A�u��`���v�Ȃǂ��o�āu���p���z�@�̔�r�v�܂ł����グ�Ă���B��2���͖{���̎傽�镔���ł���B���グ��P��́A�u�傫�ȊT�O�v����Ō�́u�@�\��v�Ɏ���܂ł�10��ނɕ����āA�v89���ڂƂȂ��Ă���B
�@�{����ǂ�ł��炢�����̂́A�p�����{��̋����⋳���u�]�̊w���݂̂Ȃ���ł���B����ɁA�p����͂��߈ٌ�����w��ł���l�����A���ƂΑS�̂ɊS�������Ă���l�����ł���B�����Ă���l�����Ɗw��ł���l���������ɁA�Ƒ�ϗ~�����Ă��邪�A�����₩�Ȃ���{���Ŏ��グ�����́A���Ƃ̋����w�K�̍��{�ɂ���������Ă���Ǝv������ł���B�ȉ������̗��R�ł���B
�@�܂��A�p��̒P�ꂪ�w�����Ă��镶������j��m���āA���̐��藧���̕s�v�c���₨�����낳��m���Ăق����B�P��͒P�Ɋo����悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B����o���邽�߂ɂ��A�P��ɒm�I�ɔ����Ă��炢�����B��������A���������ĂāA�L���ɂ��c��B�p��Ɍ��炸�A���Ƃ��w�Ԃ��Ƃ́A�y�����̂ł���B
�@���̒m�I�ȋC�Â��͉p��Ɠ��{��̈Ⴂ�����ł͂Ȃ��B���R�Ȃ���A���҂̈Ⴂ�͂���A�{�����������Ƃ��Ĉ����Ă���B�������A���Ă���_�������B�{����ʂ��āA���Ƃ̕��Ր��̈�[��m���Ăق����B���Ƃ̕��Ր���m��Ƃ������Ƃ́A�l�Ԃ̕��Ր���m��Ƃ������Ƃł�����B
�@����ɁA�{���ł́A��r�����I�Ȏ��_�����ł͂Ȃ��A�����E���ʂƂ����_����A�p��Ɠ��{��̖������グ������ł���B���Ƃ��A��1���̍Ō�̕������2���̍����Ȃǂ�����ł���B�P�Ɍ���╶���Ɋւ���m���������Ă��邾���Ȃ��A���̒m�����g�����Ȃ����f�́A���Ȃ킿����ς╶���ς��A���Ƃ̋����w�K�ɂ͕K�{���ƍl���Ă��邩��ł���B
�@�ȏ�A�ꌾ�ŕ\���A���Ƃ̋���E�w�K�ɂ̓��^����\�͂��K�v���Ƃ������ƂɂȂ�B���^����\�͂Ƃ͂��Ƃɑ���m������є��f�͂ł���B�����́A���H�I�R�~���j�P�[�V�����\�͂Ƃ������ƂŁA�u���ۂɎg���邱�Ɓv��ڂ����X���������Ȃ��Ă���B����͂���ł悢���Ƃł���B�������A����Ƀ��^����\�͂�������A����g�p�͔ՐɂȂ�B�K���Ȍ���ς╶���ςɊ�Â��ĉp����g�p����C�u�p��͂��܂����A�����ۓI�v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ�B
�@�{���̓��e�́A�M�҂̂���܂ł̉p�ꌗ�ł̑؍݂Ȃǂ̌l�I�ȑ̌���ʂ��ē����m�������ƂɂȂ��Ă���B�������A�����̎Q�l�����Ƃ��Čf�ڂ��Ă���悤�ɁA�����̎��T�⎖�T(�{�����ł͗��̂Ŏ����Ă���)�A�W�}�����Q�l�ɂ����Ă��������Ă���B�{���ւ̒��ڂ̈��p�̗L�����킸�A�����Ɍ�������\���グ�����B
�X�Z�@�q
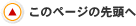
 �ځ@�@�� �ځ@�@��
�܂�����
��1���@����E�����E�v�l
�T�@�T�s�A=�E�H�[�t�̉���
�U�@�u�����v���ۂ̐�������قȂ�
�V�@�u�|��͗���v�ł���
�W�@��̌`���ߒ��ɂ����鋤�ʐ�
�X�@���p���z�@�̔�r
��2���@�P��̕����I�Ӗ�
�傫�ȊT�O
animal,gesture,greeting,music,nation,nature,
society,sport,time
���ۓI�ȊT�O
class,humour,joke,love,party,play,right,work
�����E�`�e��
die,drink,give,learn,marry,move,push/pull,
speak,think,beautiful,large/small,sorry,sweet
�F
blue,green,red,white/black,yellow
�H�ו�
apple,bread,coffee,egg,orange,salt,tea
�Z�܂��E����
bathroom,book,flag,fork,house/home,key,map,
shoe,window
�l��
child,friend,lady,man/woman,name,volunteer
�����E�g�́E���̑�
baseball,car,cat,club,fish,foot,hand,horse,
moon,school,station,three,water
�����E�l��
America,Australia,Canada,Japan,Korea,
NewZealand,TheUnitedKingdom,John,Mary
�@�\��
a(an)/the,be(is,am,are),he/she,I/you,it,Mr/Ms,
no,some/any,that,will/shall
���Ƃ���
�Q�l�ɂ��������E���T�E������
���� |

