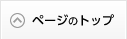教育サポート書籍
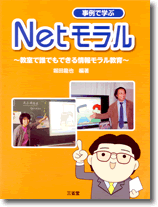
事例で学ぶ Netモラル ~教室でだれでもできる情報モラル教育~
堀田龍也 編著
定価(本体1,429円+税) A4変判 208ページ
ISBN:978-4-385-36265-6 2006年 4月15日 発行
急激なIT社会の進展にともない、インターネットの利用者もどんどん低年齢化している。子どもたちがインターネットを適切に利用する方法を、ネットモラル教育の第一人者が理論と実践をもとに解き明かす。
編著者 堀田龍也 (ほりた・たつや)
1964年生まれ。東京学芸大学卒,電気通信大学大学院修了。東京都公立小学校教諭、富山大学教育学部助教授,東京大学社会情報研究所客員助教授,静岡大学情報学部助教授等を経て,2005年10月より独立行政法人メディア教育開発センター・助教授。研究領域は教育工学・情報教育。文部科学省中央教育審議会専門部会委員、「初等中等教育におけるITの活用の推進に関する検討会議」など教育の情報化に関する政策編成の委員を歴任。NHK学校放送情報教育関連番組企画委員。著書に『学校のLAN学事始』(高陵社書店),『メディアが身近に感じる情報教育の実践』(明治図書),『メディアとのつきあい方学習』(ジャストシステム),『できる教師のデジタル仕事術』(時事通信社)など。
執筆者一覧
〈ネットモラル研究会〉(50音順)
主査 堀田 龍也 (独立行政法人メディア教育開発センター・助教授)
石井 聡 (岡山県岡山市立五城小学校・教諭)
石鎚 一則 (愛知県刈谷市立朝日中学校・教諭)
石原 一彦 (滋賀県大津市立藤尾小学校・教諭)
上杉 圭子 (静岡県富士市立元吉原小学校・教諭)
上野 真 (大分県速見郡日出町立日出小学校・教諭)
衛藤 暢一 (大分県速見郡日出町立日出小学校・教諭)
表 克昌 (富山県氷見市立海峰小学校・教諭)
笠置 隆宜 (大分県速見郡山香町立向野小学校・教諭)
梶本 佳照 (兵庫県三木市立教育センター・副所長)
片山 淳一 (岡山県赤磐市立山陽北小学校・教諭)
金井 義明 (熊本県熊本市立西原小学校・教諭)
上水流信秀 (財団法人岐阜県教育文化財団生涯学習センター・課長補佐)
蒲生 信博 (岡山県倉敷市立郷内中学校・教諭)
木口 修 (岡山県総社市立秦小学校・教諭)
佐々木弘記 (岡山県教育工学研究協議会)編集協力
笹原 克彦 (富山県富山市立寒江小学校・教諭)
竹谷 正明 (東京都狛江市立狛江第一小学校・教諭)
土井 国春 (徳島県板野郡松茂町長原小学校・教諭)
野間 俊彦 (東京都北区立赤羽台西小学校・主幹)
原田 緑 (岡山県岡山市立操明小学校・教諭)
平川 秀徳 (大分県日田市立大野小学校・教諭)
平松 茂 (岡山学校情報化研究会)編集協力
正來 洋 (石川県金沢市立額小学校・教諭)
増田 正治 (岡山県岡山市立灘崎小学校・教諭)
松橋 尚子 (東京都世田谷区立砧小学校・主幹)
丸山 力 (岡山県岡山市立五城小学校・教諭)
向井 康之 (富山県高岡市立福岡小学校・教諭)
明樂 五月 (岡山県瀬戸内市立邑久小学校・教諭)
森山 隆行 (岡山県倉敷市立連島中学校・教諭)
山脇 隆史 (鳥取県倉吉市立灘手小学校・教諭)
吉野 和美 (静岡県富士市立元吉原小学校・教諭)
特別協力 曽川 巧 ( 広島県教科用図書販売株式会社・ 「事例で学ぶNetモラル(Web版)」制作統括)
ネットモラル教材の開発について
A(情報安全)
A-01 不適切なwebに遭遇したときの対処法
A-02 なりすまし
A-03 IDとパスワードの役割
A-04 ネット上で知り合った人の約束は危険
A-05 個人情報を奪うWebサイトを見抜く
A-06 ケータイと私たちの生活
A-07 チャットに夢中にならない
A-08 フィッシングへの対処
B(責任ある情報発信)
B-01 文字だけで伝える楽しさや難しさ
B-02 掲示板を使うときの責任
B-03 電子メールのルール
B-04 情報を発信するときの責任
B-05 ネット上での情報が広がる仕組み
B-06 チェーンメールへの対処
B-07 ネットショッピング
C(健全な情報社会の形成)
C-01 写真と肖像権
C-02 著作権の概念を知る
C-03 著作権の利用
C-04 ネット依存症>
C-05 架空請求と不当請求
補遺(参考資料)
教員研修の事例
情報教育用語集
「情報教育」「教育の情報化」の流れ
あとがき
執筆者一覧
「すべての教室でネットモラル教育の実現を」
本書の目的は,これに尽きます。
教員が思っている以上に,子どもたちはメディアに浸った生活をしています。テレビのバラエティー番組,ゲーム機の氾濫,インターネット上の掲示板,ケータイによる友だちとの情報交換……これらはもはや日常茶飯事です。
思えば大人の私たちも,朝起きたらテレビのスイッチを入れ,旅行に行く前にはインターネットで調べ,時には友人と長電話をします。仕事上でもプライベートでも,メールチェックは不可欠。私たちもまたメディアに浸った毎日を過ごしているのです。
しかし,私たち大人のメディア接触と,子どもたちのメディア接触とは,違う部分があります。
ある怪しげな情報があったとき,私たち大人がそれを疑って見ることができるのは,日々の生活で獲得したさまざまな常識が備わっているからです。それらの常識は,これまで長い時間をかけて獲得してきたものであり,親から子へ受け継がれ,学校で教えられてきました。
もちろん現代の子どもたちも,親や学校から常識を学びます。しかし,常識を学んでいる途上にも関わらず,すでにたくさんのメディアに接触してしまっています。子どもたちは,それらのメディアで起こっている現実を見て,それを常識だと学習してしまう可能性があります。特にネット上では,大人から見てもふさわしくない非社会的・反社会的な行為がたくさん見られますが,子どもたちはこれを常識だと勘違いしていく可能性があるのです。
だからこそ,今,ネットモラル教育が必要です。ネットモラルは,本来的には,子どもたちがメディア体験を重ねるうちに,次第に学び取っていけばいいと私は思っています。しかし,上記のような現実が横たわっている以上,子どもたちの気づきを待っているようでは教育が手遅れになってしまいます。
すべての子どもたちに,最低限のネットモラルに関する知識や考え方を教えておくことは,彼らを健全な社会人として育て,情報社会を望ましく形成していくために,学校教育が手を出すべき重要な教育行為です。学校教育がこれを放棄したら,子どもたちは危険な世の中を形成してしまう張本人になってしまうのです。
すべての教室でネットモラル教育の実現を。そのために必要な質の高い教材を。多くの教師が取り組めるための敷居の低い事例を。本書は,これを実現した,日本で最初の書籍だと自負しています。
2006年2月
編者 堀田龍也
『事例で学ぶNetモラル』今,なぜネットモラル教育か
急速にネットワーク化が進む現代では,大人ばかりでなく子どもたちも否応なく情報社会に組み込まれていきます。情報社会はまだまだ成熟した社会とはいえず,だからこそそこでどう行動するかが問われてきます。とはいえ,情報モラル教育といってもどのように指導すればよいのか,多くの教師は見当もつかないというのが実態です。
そこで,なぜ情報モラル教育が必要とされるのか,情報モラル教育とはどのようなもので,どのように取り組めばよいのか,そして情報モラル教材『事例で学ぶNetモラル(Web版)』を開発したきっかけなどを,堀田龍也先生にうかがってみました。
I ネットモラル教育とは何か
Q 「ネットモラル教育」とはなんですか?
「情報モラル」の教育が必要だということは,いまやだれもが同意してくれることだと思います。
社会の情報化がどんどん進み,子どもたちはその中で生きていくことになります。情報化の光の部分を自分の生活の中で上手に活用する一方で,情報社会に潜むさまざまな影に気をつけなければいけないという意味で,情報モラル教育の必要性が認識されています。文部科学省の現在の情報教育の枠組みの中にも,「情報社会に参画する態度」として情報モラル教育が位置づいています。これからの社会の形成者である子どもたちが,情報に対する責任感や危険性を認識し,それを上手に利用して望ましい情報社会をつくりあげていく態度を育成しなければいけないという考え方です。したがって,情報モラル教育は,もう実際に動いています。
「ネットモラル」とは,情報モラルのうち,インターネットや携帯電話などネットワークを介してのコミュニケーションの上で必要となるモラルについて取り立てて扱うものです。すでに子どもたちはインターネットや携帯電話に囲まれた生活をしていますし,ネット経由のトラブルが頻繁に起こっています。広く情報モラルといわれていることのうち,ネットに関する部分を取り立てて強調しておきたいと考えたのです。
Q なぜ必要とされているのでしょうか?
携帯電話やインターネットは,対コンピュータではなく,メールでだれかとつながったり,だれかのつくったページを見たり書きこんだりと,ネットの向こうにいる人と交流するということになります。情報社会とは,子どもたちから見るとそのほとんどがネット社会です。ネットモラル教育は,相手がコンピュータではなく人であるため,かえって難しい問題があります。ネットモラル教育というくくりで,インターネットや携帯電話についての負の部分に対抗する教育を,きちんとやっていかなければいけないと考えています。
インターネットや携帯電話にしぼる理由は,普及率を考えてのことです。
いまや小学生のいる家庭のうち,90%以上がコンピュータを所持しています。今の時代,インターネットにつながらないコンピュータというのはほとんどありません。少なくとも,街でインターネットにつながらないコンピュータをくださいといっても,売っていません。したがって,コンピュータは必然的にインターネットが前提になっています。そう考えた場合,コンピュータの操作を覚えて,コンピュータでどう問題解決するかというようなかつての情報教育だけではなく,ネット経由の相手に対してどう表現するか,どうやりとりするか,ということに問題は必然的にシフトしていきます。
携帯電話に至っては,保護者への普及率はほぼ100%。子どもへの普及率は,2004年11月のベネッセコーポレーションによる調査のデータでは,小学生が約20%,中学生が約50%,高校生が約90%を超えています。さらに,年々低年齢化が加速しています。携帯電話を持ってから教育していては遅いのです。子どもたちの利用実態と社会の状況をふまえ,子どもたちを危険から未然に守るという意味で,携帯電話がほぼ100%普及する高校生になる前に,小中学校段階できちんとやっておかなくてはいけないネットモラル教育があるとわたしは考えています。
Q ネットの利用には,どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
まず,ネットでだれかとつながるということの意味を考えなくてはいけません。だれかとつながるということは,コミュニケーションするということです。コミュニケーションというのは,基本的にはおもしろいものです。だれかとコミュニケーションをとりたいという本質的な欲求は,人間ならだれにでもあることだと思います。これまでは,会った人としかコミュニケーションができませんでしたが,今ではメディアのおかげで,会えないときにでもできるようになりました。リアルな対人関係をさらに補強するという意味で,携帯電話が役に立っている部分もたくさんあります。
ルーブル美術館にある絵画なども,もちろん本物を見ることはなかなかできないにしても,インターネットでかなり詳細な状況まで見ることはできます。本を買うときも,書店に行って実物を手に取ることとは別に,インターネットで必要な書籍を検索し,在宅のまま購入することができます。ネットにはこのようなさまざまなメリットがあり,これからはネットが前提となって,社会が組み変わっていきつつあるといえるでしょう。
情報の流通は,ネットを経由することで,人件費がかからなくなるうえに,速度が迅速になります。ソフトウェアの販売でも,CDをつくって箱に入れて店頭で売るよりも,ネット上に置いて,自動的にバージョンアップできるようにしたほうが,圧倒的にコストダウンになります。購入する側にもメリットがあるので,必然的にその方向に進んでいくわけです。したがって,「ネットがよくない」と大きな声で言ってみたところで,社会はどんどんネット化するし,それはどんどん加速していくでしょう。
このようなメリットがたくさんある一方で,便利なものの裏側には必ずデメリットがあります。例えば,車に例えてみるとよくわかります。わたしたちの社会は,すでに車社会です。何系統もあるバスを乗り換えて通勤できますし,自家用車で家族とドライブや旅行に行くこともできます。車社会というのは,わたしたちが車を道具として活用し,問題を解決できる社会です。
しかし一方で,車社会で起こっている問題として,交通事故があります。交通事故は,命が奪われるくらい危険なことです。しかし,だからといって車がなくなるわけではありません。それは,車社会のメリットが大きいからです。交通事故というデメリットに対して,わたしたちはさまざまな対処をしています。例えば,スピードが出すぎないような車をつくる,ガードレールを整備する,横断歩道や信号を整備する,免許制にして自動車教習所をつくる,交通マナー・交通ルール,そして道路交通法をきちんと整備するなど,いろいろな社会の仕組みづくりが行われて初めて,車社会が機能しています。それでも事故は起こりますが,メリットとデメリットを比べたときに,メリットのほうが大きいので,社会の正常な形となっているのです。
ネット社会もこれからどんどん進んでいきますが,デメリットに対してどう対処していくかをきちんと考えなくてはいけません。残念ながら,今のところ野放しに近い状態になっています。例えば,個人情報が漏洩したり,ウィルスが蔓延したり,ネットショッピングで詐欺が起こったりという問題が発生しています。社会的に警察や法律が整備されていくことで,だんだん車社会のように体制ができていくと思いますが,交通安全教育があるように,子どものうちからその社会を生きていくために必要な常識の教育が必要だと思います。
ネット社会においては,これがネットモラルの教育なのです。ネット社会の利便性を教えるのと同時に,そこに潜む危険性を教えなくてはいけません。それが適切に教えられていないと,ネットは使いこなせるけれど危険性を知らない人たち,車に例えると,車の運転はできるけれど道路交通法を知らず,車での事故についてわかっていない人たちばかりになってしまいます。この人たちは,自分が事故で死ぬかもしれないし,ほかの人に危害を加えるかもしれません。本人たちは無邪気に車に乗っていても,社会的には多大な問題を引き起こす可能性があります。ネットモラルの教育も,自分の安全を守るという教育の一方で,社会に対して迷惑をかけないということの教育でもあります。ネット社会が進んでいけば,必然的にネットモラルの教育も必要になるし,その教育がきちんとされていることで初めて,ネット社会のメリットをわたしたちが享受できる健全な社会になるのだと思います。
- 三省堂教科書
- 国語教科書
- 国語教育情報:サポート書籍
- 『事例で学ぶ Netモラル ~教室でだれでもできる情報モラル教育~』