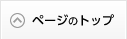教育サポート書籍

声を届ける-音読・朗読・群読の授業- CD付き
高橋俊三 著
A5判・232ページ
定価(本体価格2,400円+税)
ISBN: 978-4-385-36359-2
2008年4月15日発行
[品切れ]
高橋俊三 (たかはししゅんぞう)
1936 年生まれ。東京都公立小学校,東京学芸大学附属世田谷中学校教諭を経て,群馬大学教育学部教授。2002 年3 月定年退官。この間,同大学附属中学校校長,文部科学省学習指導要領・達成度評価問題などの作成協力委員を務める。また,NHK
テレビ「朗読入門」「話し方教室」や民放ラジオ・テレビの番組に出演。現在は,NPO 日本朗読文化協会顧問,ILEC 言語教育文化研究所常任理事,話力総合研究所特別講師。
主な編著書に,『話力をつける─若い人のために─』(文教書院),『なんとユーモア─子どもたちと楽しく─』(文教書院),『群読の授業─子どもたちと教室を活性化させる─』(明治図書),『音声言語指導大事典』(明治図書),『国語科話し合い指導の改革─グループ討議からパネル討論まで─』(明治図書),『山月記を読む』(三省堂),『教師の話力を磨く─子どもの知と心を拓く話し方・聞き方─』(明治図書)などがある。
まえがき
第1章 音読・朗読・群読の基本
1 声を届ける 声を受けとめる
2 黙読と音読と朗読
3 朗読する楽しさ・聞く楽しさ
4 群読する楽しさ
5 群読への導入
6 群読の作品創り
第2章 いろいろな作品の音読・朗読・群読
1 説明的文章の音読・朗読・群読
(1)説明文の音読・朗読
(2)論説文の群読
2 物語・小説の音読・朗読・群読
(1)物語・小説の音読・朗読
(2)物語・小説の群読
3 韻文の音読・朗読・暗誦・群読
(1)詩・短歌・俳句の音読・朗読・暗誦
(2)詩・短歌・俳句の群読
4 古典の音読・朗読・暗誦・群読
(1)古典の音読・朗読・暗誦
(2)古典の群読
第3章 音読・朗読・群読の技術
1 呼吸法・発声法・発音練習(滑舌)
2 アーティキュレーション
(アクセント/イントネーション/ポーズ/チェンジ・オブ・ペース/プロミネンス/トーン)
3 群読の「せめぎ合い」
4 朗読譜・群読譜
第4章 朗読・群読と関連する読みの形態
1 読み聞かせ・ブックトーク
2 リーディング・シアター
第5章 音読・朗読・群読と教育
1 教師の朗読と範読
2 音読・朗読の教育的効果と指導上の留意点
3 群読の教育的効果と指導上の留意点
4 戦後,音読・朗読・群読の教育史
初出一覧
あとがき
CD収録作品一覧
教師の範読にとって,天敵ともいうべき機器が出現している。自動音声発生機とでもいおうか。文章を活字で入力すると,純正な日本語で読み上げるというものだ。
その程度は,例えば「橋」と「箸」とは,アクセントが異なるから,それをきちんと読み分けるなどという初歩的なものではない。活字にすれば同じ「ハ」であっても,言葉によって音が微妙に異なる。「春」の「ハ」だ,「発」の「ハ」だと,何十とおりもの「ハ」がある。それらを全部用意しておいて,入力された言葉の意味を瞬時に捉え,それにあった音を瞬時に選択し,発音する。
私はこの音声発生機の読み音を聞いたことがある。まことに人間の声のようで,上手なアナウンサーが読んでいるようだと聞こえた。現状ではまだまだ高価であるが,日本の科学技術力からすれば,遠からず各学校予算で購入できる程度の値段になるだろう。そうなった時,教師はどうするか。その機器は,正確な日本語を発するし,絶対に読み間違えない。範読はその機械に任せて,教師は声を出して読むのを止めるか。スイッチをオンにして,後,黙っているか。
天敵にしない道がある。その機械にはできないことがある。例えば,「雨だ」という文は正確に発音できるが,日照りが続いた翌朝起きた時の「雨だ」と,期待して待った遠足当日の朝の「雨だ」は,発音し別けられない。また,「よかったね」とか「何でだヨー」とかの反応を示す聞き手と,眼差しを交わしてから次に進むということもできない。正確ではあるが,感情がない。音ではあるが,声ではない。
人間としての教師の朗読が生きる道は,ここだ。子どもたちにとっても,それは同じ(音読と朗読との違いは,本文で見ていただくことにして,ここでは朗読といっておく)。
私は,範読という言葉を注意して用いたいと考えている。教師が声にして読む行為を全て範読というのではないのだ。範読とは,模範になる読み方,規範的な読み方である。それは例えば,幼児音の矯正とか,日本語習得の場面とか,広く一般的な言語の学習には,典型としての極めて必要な読み方であるが,個性的な教材(作品)を個性的な教師(人間)が読む場合には用いない。教師の朗読と呼んで,活発に行うべきものであると考えている。
子どもの場合も同じ。子どもにとって,純正な音韻の習得は必要であるが,常に純正な音韻を発音しているのではないことを(教師は)知っておこう。そうして,子どもたちに,人間としての言葉を発する大切さを理解させ,発する力を育てていこう。
私は,朗読するとは記された文字を音声化することではない,文字が示している言葉を音声化することだと言っている。その際,言葉は,声に乗って相手に届いていく。
言葉は声である。朗読するとは,読み手の声を届けていくことである。読み手は,作品中の人物の声・語り手の声・作者の声を受けとめ,また,聞き手の声を受けとめて,読み手の声を確定し,その声を聞き手に届けていくのである。朗読とは,まさに,声を届け,声を受けとめる言語行為なのである。
教師は,そういう読みをしたい。子どもたちに,そういう読みをさせたい。
平成二〇年二月
高橋俊三
私は,今,「猫また」(『徒然草』八九段)の授業に凝っている。この話の面白さを,小学校のどの学年まで味わわせることが可能かという実験授業だ。飛び込み授業を何回やっただろう。私の指導技術では四年生は往生したが,五年生以上なら四五分の授業で笑いが起こるところまで持っていく自信がある。群読の入り口までも到達することができる。子どもたちが声を出し合って,古典の読みを楽しむ。中学生なら,なおさらだ。これは,声の力だと思う。
今回,CDの録音を付けて出版するというチャンスを得た。うれしい限りである。これまで,紙面上で,高く読むとか,優しく読むとか,文字言語で説明しても,どの程度の高さか優しさか,微妙なところは伝わらないだろうなと,歯がゆい思いをしていたのだが,CDのお蔭でずいぶんと気が晴れた。やはり,音読・朗読・群読の指導法をお伝えするには,音声言語の伝達手段が有効だ。これもまさに声の力だ。
当然のことながら,群読は一人ではできない。音声言語教育研究集団「声とことばの会」の一七人の仲間が無料奉仕で協力してくれた。録音後,面白かったとは言ってくれたものの,感謝感激である。そこには「響き合い」あり「通い合い」あり「創り合い」があった。声を合わせる力だ。
初出一覧に示したように,三分の一程度の原稿は明治図書「教科教育国語教育」誌に平成一八年度連載したものである。どれも加筆したとはいえ,転載することをお許し下さった江部満編集長に感謝申し上げる。また,三省堂編集部の多くの方にお世話になった。特に,お若い細谷幸代さんや山田桂吾さんには,編集作業だけでなく,群読録音にも参加してもらった。文字と音声と,両方の加勢である。感謝。
平成二〇年二月 高橋俊三
1 群読 「かぞえたくなる」 まど・みちお
2 群読 「帰る雁」 野口雨情
3 群読 「かっぱ」 谷川俊太郎
4 群読 「ののはな」 谷川俊太郎
5 群読 「河童と蛙」 草野心平
6 群読 「ヒロシマ神話」 嵯峨信之
7 群読 「那須与一」(『平家物語』より)
8 群読 「平泉」(『おくのほそ道』より)
9 群読 「かさこじぞう」 岩崎京子
10 朗読 「敦盛最期」(『平家物語』より)
11 朗読 「猫また」(『徒然草』より)
12 朗読 「オツベルと象」(一部抜粋) 宮沢賢治
13 朗読 「走れメロス」 太宰治
- 三省堂教科書
- 国語教科書
- 国語教育情報:サポート書籍
- 『声を届ける-音読・朗読・群読の授業- CD付き』