 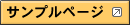
|
| *「サンプルページ」は画像ファイルで別画面に表示します。 |
主要大学の過去二十数年間の入試問題を、「入試問題の本文そのまま」にデータ化していますので、入試頻出用語をそのまま知ることができます。すべての設問は「入試問題の本文そのまま」なので、この一問一答で覚えたとおりの文章で出題されます。過去問データをA・B・Cの三つのGRADEに分けていますので、志望大学の難易度に応じた効率のよい学習ができます。教科書に沿った時代順に構成されていますので、基礎から学習したい人でも歴史の流れがつかみやすく、入試問題のポイントもつかむことができます。近・現代史を充実させているので、日本史A・Bともに十分に対応できます。
●本書の特色
- 主要大学の過去二十数年間の入試問題を出題頻度別にデータ化
→ 入試頻出用語が実践的な形で知ることができます。
- 設問を難易度に応じて、A・B・Cの三つのGRADE分類
→ 志望大学に応じた効率のよい学習ができます。
- 「入試問題の本文そのまま」の設問を基本
→ 一問一答で覚えた形がそのまま出題されるので学習効果が抜群です。
→ 教科書と併用して学習すれば、入試問題のポイントをつかむことができます。
- 問題の最後には、難解な用語を分かりやすく解説しています。
- 解答欄には、うっかり陥りやすい誤字を×印で記しています。注意してください。

●はしがき
『日本史のそのまま出るパターン』の初版が出版されて十数年、改訂版が出版されて4年が経ちました。入試問題の本文をそのまま収載した一問一答という「前例の無い」タイプの参考書だったため、全く期待されなかったのですが、出版してまたたく間に完売。皆さんの声を受けて、増刷を重ねてきました。
本書が皆さんのご支持を得た最大の理由は、金谷俊一郎先生による、過去二十数年分の全国主要大学の入試問題の完全データ化とその出題頻度の正確さにあります。このデータ化によって、「日本史の出題パターンはある程度決まっており」、「その出題パターンを学べば、次年度の入試問題でも「そのまま」出る」という事実が裏付けられました。たいへんな労力をはらって生まれた金谷俊一郎先生のアイディアが「受験生の求める」ものであったということの証です。
以下の問題を見てください。
(1) 明治政府は、1868年3月に[ ]を発布、「万機公論」にもとづく政治をおこなうことを表明した。(立命館―経営)
(2) 新政府は、1868年3月、国として進む基本方針を示す条文を[ ]として交付した。(上智―文)
(3) 明治政府は、1868年、[ ]を発布し、「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」などの基本方針を示した。(近畿―商経)
(4) 明治新政府は、その基本方針を公布した[ ]において、とりあえず公議世論の尊重を強調した。(東北学院―経済)
正解はいずれも「五箇条の誓文」
実は、これは同じ年度の入試問題です。このように同じ年度でも、同じ問題が、ほとんど同じ文章で出題されているのです。
また、以下のような例もあります。ある年の同志社大学文学部の問題です。
ペリーは1854年度再来日して、幕府に[ ]を結ばせた。
その翌年の同志社大学の商学部では、
1854年、老中阿部正弘が主導して米国と[ ]を調印した。
さらに、その翌年の同志社大学の商学部では、
ペリー提督は、1854年にふたたび来航し[ ]を締結した。
と、「日米和親条約」を答えさせる問題が、同志社大学で3年連続出題されたのです。このように、過去の出題パターンを学ぶことによって、翌年も「そっくりそのまま」出題されていくということが、入試問題の完全データ化から実証されています。
十数年前でも、本書の威力はとどまるところを知らないのですが、このたび、さらにパワーアップさせて、究極のものをつくるべく、本書を改訂しました。改訂では、出題データを更新するとともに、学習者の使い勝手を考え、皆さんの志望校に応じて効率よく・要領よく学べる一問一答となるようにしました。
最後に、受験生諸君の「合格したい」「成績を上げたい」という熱意にこたえられるような改訂を行うという、金谷俊一郎先生の熱意に感謝申しあげます。
2007年初秋
三省堂編修所
|