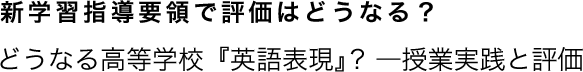![]()
![]()
新学習指導要領をどう見るか
新しい学習指導要領が出ると,そこには新しい「ことば」がいろいろと登場して,世間を賑わす。なにか「とんでもないこと」でも起こったかのごとく大騒ぎになることもある。
しかし,楽観的に考えよう。見方をちょっと変えてみることで,「どんな授業にしようか」,「こんな力をつけるにはどんな活動をすればよいだろうか」などといろいろな工夫や発想が頭を駆けめぐって,楽しくなるものだ。
ここでは,新しい高等学校の科目『英語表現』を取り上げる。学習指導要領に登場する文言をいくつか拾いながら,いわゆるPlan-Do-Checkサイクルの視点から,何が求められているのか[目標],そのためにはどのような授業実践を行えばよいのか[活動]を考えることで,評価の視点も明らかにしよう[評価]。
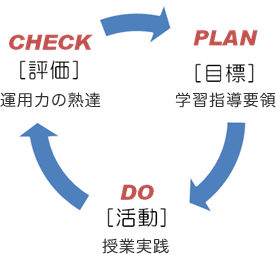
態度を育成し,評価する?!
![]() まず,『英語表現Ⅰ』の目標から次の一節を取り上げよう。
まず,『英語表現Ⅰ』の目標から次の一節を取り上げよう。
英語を通じて,積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに,(中略)伝える能力を養う。
![]() 「態度」と言われると,どんな授業をして,それをどう評価すればよいか,考え込んでしまうかもしれない。これは,①「積極的にコミュニケーションを図ろうとする」ように仕向けるにはどうしたらよいか,と言い換えることができよう。また,②「書ける!言える!」という達成感や実感をいかに持たせるかことができるか,という視点も欠かせない。
「態度」と言われると,どんな授業をして,それをどう評価すればよいか,考え込んでしまうかもしれない。これは,①「積極的にコミュニケーションを図ろうとする」ように仕向けるにはどうしたらよいか,と言い換えることができよう。また,②「書ける!言える!」という達成感や実感をいかに持たせるかことができるか,という視点も欠かせない。
何と言っても大切なのは,トピックやテーマだ。ただし,「若者受けする」トピック,というだけでは,生徒の意欲は意外と持続しないものだ。
たとえば,あるレッスンの文法事項は現在形,トピックはスポーツ。「I like ~ にスポーツ名を続けて,言ってみよう」という活動は,途中段階ではあってもよいが,これだけではあまり面白くなさそうだ。
こんなプロジェクトを仕掛けてみよう。何回かの授業を通じて,「1分間で自分のことを英語で紹介する文章を作ろう!」というプロジェクトを掲げるのだ。1分間というのは決して短くない。ざっと100語程度は必要だから,生徒にとってはチャレンジングな課題である。これを3レッスン分くらいの時間をかけて創り上げていくのだ。
話題はスポーツに限定する必要はないだろう。スポーツというのは自己紹介の「ネタ」になる参考例だ。現在形のレッスンでは,「今,何か習慣にしていることは?」,「それは毎日,それとも週に何日かやっている?」,さらに,「それは楽しい?苦しい?それとも…?」,「それはなぜ?」などと問いかけながら,言いたいこと・書いてみたいことをイメージしてもらう。
![]() こんな仕掛けをすることで,現在形という形式が現在の習慣を表すことが自然に分かってくるであろうし,何よりも自分のことを語るプロジェクトという目標があるから,意欲が増すことも期待できるだろう。そうであるならば,「態度」と「伝える力」は表裏一体と考えることができるから,生徒たちが取り組んだ結果を,①書いた英語の量,②文法的な正確さ,③自己紹介の視点と一貫性,といった観点から評価すればよいことになるだろう。
こんな仕掛けをすることで,現在形という形式が現在の習慣を表すことが自然に分かってくるであろうし,何よりも自分のことを語るプロジェクトという目標があるから,意欲が増すことも期待できるだろう。そうであるならば,「態度」と「伝える力」は表裏一体と考えることができるから,生徒たちが取り組んだ結果を,①書いた英語の量,②文法的な正確さ,③自己紹介の視点と一貫性,といった観点から評価すればよいことになるだろう。
論理的に考える力を育成し,評価する?!
![]() 次に,同じく「目標」にある次の一節を取り上げよう。
次に,同じく「目標」にある次の一節を取り上げよう。
事実や意見などを多様な観点から考察し,論理の展開や表現の方法を工夫しながら伝える能力を養う。
このことは,話すことを中心とした活動の「伝えたい内容を整理して論理的に話す」,書く活動に関する配慮事項の「つながりを示す語句などに注意しながら書くこと」などの記述とも関連する。ここでは,「論理の展開」に注目しよう。論理的に思考して話したり,書いたりすることが期待されているのである。
そもそも,「論理的」とはどういうことだろうか。梶原しげるさんの著書『即答するバカ』(新潮新書)には興味深いエピソードが紹介されている。「その「だから」は本物か」と題する一節から引用しよう。
子安大輔さん(筆者注:飲食業コンサルタント)とラジオでご一緒した。(中略)
一つ,日本語に関する興味深い指摘があった。それは,「だから」の使い方に関することである。
「私はおいしいお店を食べ歩くのが好き。だから,飲食店をやってみたい」
飲食業を始める人間がこのように話すことがあるという。しかし,ここでの「だから」という接続詞は,使い方が間違っていると子安さんは指摘している。
飲食店の食べ歩きが好きな人が,飲食店を経営したい,と考えるのは自由だ。でも,その人は,食欲と好奇心旺盛であっちの店,こっちの店とおいしいものを追いかけるのが好きなだけかもしれない。それと経営は別の話。飲食店の経営者として,毎日同じ調理場に閉じこもり,他人のためにせっせと調理や洗い物をしたり,材料調達や客集めのチラシを配ったり金策に駆け回るのが得意な人とは限らない。
![]() 英語であれば,thereforeなどを使うことになろうが,この接続表現を正しく使うためには,論理的思考が要求されることになる。「だから」,一文書いたり,言ったりするのもなかなか大変だ。いや,こう考えてみると,論理的に思考するというのはおもしろくなってくる。いきなりパラグラフを書く前に,こんなステップを踏むのがよい。
英語であれば,thereforeなどを使うことになろうが,この接続表現を正しく使うためには,論理的思考が要求されることになる。「だから」,一文書いたり,言ったりするのもなかなか大変だ。いや,こう考えてみると,論理的に思考するというのはおもしろくなってくる。いきなりパラグラフを書く前に,こんなステップを踏むのがよい。
I am interested in agriculture __________ my parents grow apples.
のように,前後関係を考えて接続表現を入れるタイプが基礎編だとすると,
I think computers have more benefits than harm because _____________________.
のように文を完成させるタイプは,コンピュータが有益である点を自分で考えなければならないから,いわば応用編である。
これを2~3考えて,それぞれを説明・補足する文を追加し,導入と結語を加えると立派なパラグラフができあがる。このときにも,「コンピュータが有益だと思われるのはどんな点?」,「どうしてそんなふうに思うの?」などと問いかけ,論理的かどうかを意識しながら少しずつ文章をふくらませていくおもしろさをぜひ体験させたい。
![]() これまで以上に,学習指導要領では,論理的思考の重要性が強調されている。「内容の要点を示す語句や文,つながりを示す語句などに注意しながら書くこと」などと言及されているのも,たとえば,つなぎの語句を意識的に使ってみることで論理的に考えてみることを促しているのだ。
これまで以上に,学習指導要領では,論理的思考の重要性が強調されている。「内容の要点を示す語句や文,つながりを示す語句などに注意しながら書くこと」などと言及されているのも,たとえば,つなぎの語句を意識的に使ってみることで論理的に考えてみることを促しているのだ。
授業では,①文脈に適切な接続表現を補うことができたか,②接続表現を使って,論理的に考え,適切な文を書くことができたか,③多様な視点で事象を捉えることができたか,④それぞれについて文を補足し,説得力のある文章を書くことができたか,などという点を評価すればよいだろう。こうしたステップを踏むことで,どこで生徒たちはつまずいたか,どのようなフィードバックが必要かが明らかになるだろう。
即興で話す力を育成し,評価する?!
![]() もう1つ。「話すことを中心とした活動」に登場する次のような一文を取り上げよう。
もう1つ。「話すことを中心とした活動」に登場する次のような一文を取り上げよう。
与えられた話題について,即興で話す。
![]() 注目すべきは,「即興で」というところだ。これは大変だ,と思ってしまうだろう。見方を変えてみよう。即興で話すように仕向け,即興で話せるようにするにはどんな活動をすればよいか。『英語表現』では,スピーキングとライティングの力を身につけることが期待されているが,音声と文字の産出スキルを同じ科目の中で堂々と扱うことができるのは,好都合だ。音声と文字でたっぷり練習したい。まず,こんな基礎訓練は欠かせない。
注目すべきは,「即興で」というところだ。これは大変だ,と思ってしまうだろう。見方を変えてみよう。即興で話すように仕向け,即興で話せるようにするにはどんな活動をすればよいか。『英語表現』では,スピーキングとライティングの力を身につけることが期待されているが,音声と文字の産出スキルを同じ科目の中で堂々と扱うことができるのは,好都合だ。音声と文字でたっぷり練習したい。まず,こんな基礎訓練は欠かせない。
a. 言いたいことを考えて,書いてみる(プラニング)。
What are you interested in? ― I’m interested in _________.
Why are you interested in ________? ― Because ________________________.
b. 書いたことを声に出して言ってみる(音読)。
I’m interested in health care because my father is a nurse.
c. 書いたものを見ないで言ってみる(暗唱)。Read & Look Up 方式でもよいし,ペアでaの形式を使って口頭練習してもよい。
こんな活動も有効である。いずれも,発音や語彙はもちろんのこと,文法操作力(つまり,文法を使う力)を鍛えることができる方法なのだ。
d. 口頭英作文:教科書の基本文を(あるいは練習問題も),口頭で音読練習したら,ペアになって,一人が日本語を読み上げ,もう一人はそれをすばやく英語で言う。言えなければ,Read & Look Up方式で練習。
e. 口頭並べ替え英作文:教科書の基本文を,3つのチャンクに区切って並べ替えたものを,口頭で正しい順序にして発話する。慣れてきたら,ペアで音声のみでやるとよい。
to make a good presentation / we worked hard / at the school festival
(→ We worked hard to make a good presentation at the school festival.)
こうした活動を通して,①考えや意見を生み出す力,②質問したり,質問に応えたりする力,③語彙を使う力,④文法を使う力,などの自動化を促進することができ,即興で話すために必要な要素を訓練し,土台を築くことができる。この土台があれば,ディスカッションやディベートの練習の場を設定することも実現可能となってくるのだ。
![]() 「即興で話す」は壮大な目標だが,それにはステップが必要であるし,そのステップをそれぞれ評価していくのがよい。上記に照らして,まずは1文単位から,①考えや意見は適切か,②すばやく応答することができたか,③文法的に正確な文を発話することができたか,④発音やイントネーションは適切であったか,などが評価のポイントになるだろう。
「即興で話す」は壮大な目標だが,それにはステップが必要であるし,そのステップをそれぞれ評価していくのがよい。上記に照らして,まずは1文単位から,①考えや意見は適切か,②すばやく応答することができたか,③文法的に正確な文を発話することができたか,④発音やイントネーションは適切であったか,などが評価のポイントになるだろう。
おわりに
新学習指導要領では,音声であれ文字であれ,英語で表現できるようになるために,これまで以上に,丁寧にステップを踏んで指導することが求められているように思う。そして,「発表の仕方や発表のために必要な表現などを学習し,実際に活用すること」などという学習指導要領の文言は,話したり書いたりするというアウトプット活動を設定することが,英語で表現する力をつけるためには有効であるというメッセージと受け取れる。どんな「仕掛け」をするか,そのためにはどのような活動が必要かを考えることが評価の視点を決めることになる。こんなふうに考えてみることで,新しい『英語表現』を意味あるものにしたい。
横川 博一 (よこかわ ひろかず)
神戸大学准教授。専門分野は,心理言語学・英語教育学。外国語運用能力の向上に伴って,言語情報処理がどのように自動化していくのかに関心がある。
著書に,中学校英語教科書New Crown English Series,高等学校英語教科書EXCEED English
Series(ともに三省堂,共著),『英語のメンタルレキシコン:語彙の獲得・処理・学習』(松柏社,分担執筆),『英語語彙指導ハンドブック』(大修館書店,分担執筆),『教育・研究のための第二言語データベース
日本人英語学習者の英単語親密度〈文字編〉,〈音声編〉』(くろしお出版,編著)などがある。
![]()
Copyright (C) 2011 SANSEIDO publishing co.,ltd. All Rights Reserved.