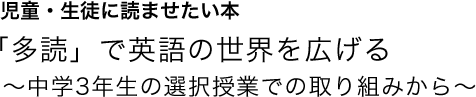![]()
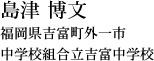
今回,「児童・生徒に英語で読ませることのできる本の紹介と,どのように読ませたらよいか」ということでお話をいただきました。そこでまず,私の過去の実践を例に,「中学校の英語の授業で,どんな本をどのように読ませることができるか」について紹介したいと思います。
次に紹介する授業を実施した学年の生徒たちは,1年生,2年生と指導し,2年間で身につけてきた英語の知識については把握することができていました。またリーディングに関しては,2年生のときに速読のトレーニングを行い,ある程度の手応えを感じていました。そこで3年生の選択授業では,「これまでの学習で身につけた知識・スキルを用い,さらに英語の世界を広げていこう」と生徒たちに投げかけ,英文多読の授業を設定してみました。この活動は『教室で読む英語100万語 ― 多読授業のすすめ』(大修館書店)の中で,「100万語多読」として紹介されている活動を授業の中で活用したものです。
この活動の留意点は,主に次の2点になります。
- 読んだ語数を記録していくことで,できるだけ多くの英語(単語・表現)に触れる。
- 辞書は使用せず,自分が読めるものを読んでいくこととする。わからなかったら本を替え,文脈や挿絵から感覚的に英語の表現をつかんでいく。
中学生(初期の英語学習者)は特に,英語の単語を一対一で日本語に置き換えていこうとしたり,すべての単語の意味がわからないと文の意味を解釈することができないと考えたりすることが多いと思います。前述のような留意点を生徒に示すと,最初はやはり戸惑うようでした。その反応が「辞書を使いたい」という声となってあらわれてきました。
そこで, Elmo Says ACHOO! (STEP INTO READING STEP 1)を一緒に読みながら,"ACHOO"とはいったいどういう言葉なのか考えていきました。すると,生徒たちはエルモのくしゃみの音が"ACHOO!"なのだということを,容易に理解することができました。
1月のコラムで宮下いづみ先生が紹介されたOxford Reading Treeも,同様に絵を見ながら語の意味を考えていくことができます。これらの本を使い,日本語の文章を読むときにも難解な語を逐一調べずに読み飛ばしたり,文脈などから類推したりしながら読み進んでいることを思い出させながら,英語の文章を読むときにも同じことができるということを感じ取らせていきました。
授業では2年間で集めた約150冊の本の中から,自由に選択して読ませるようにしていました。生徒には本の種類(シリーズ)・タイトル・語数がわかるようにした一覧表(PDFファイル参照)を渡し,読み終わったあとは,自分が読んだ本の語数と簡単な感想,または本の説明を毎時間の記録として残すようにさせていました。このようにすることで,この授業を通して,自分が合計で何語の英単語を読んだのかがわかるようにし,また,ただ文字を目で追うだけではなく,内容を解釈しているんだということを感じ取らせるようにしました。
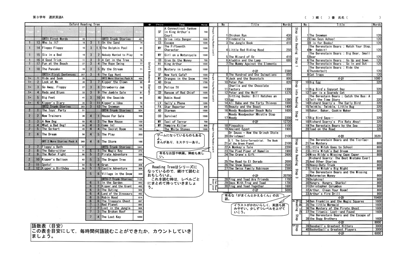
「生徒に配布した本のリスト」(![]() PDFファイル 別ウィンドウで拡大します)
PDFファイル 別ウィンドウで拡大します)
本の語数やレベルがまちまちなので,一単位時間(50分)に数冊読んでしまう生徒もいれば,一冊が読み終わらない生徒もいます。読み終わらなかったときは,次回に継続することになるのですが,途中で読むのをやめることが落ち着かず,本を借りたいと申し出る生徒も出てきたので,その場合には貸し出していました。
こういったことで,徐々に生徒たちは「英語で書かれた本を読む」ことに集中できるようになっていったと感じています。2000語前後の本を自分の席に持っていき,時間になるまで集中して本に向かっている生徒の姿を見ることもできました。この授業を終えての生徒の反応の中には次のようなものがありました。
- 長文を読むコツをつかみました(読めない単語は気にせず飛ばして読む、とりあえず大まかに訳してわからない所は推測する、など)。
- 最初はやっぱり語数が少なく、100語単位だったけど、回数を重ねるにつれて1000語単位になり、目に見えて語数が増えるのを感じることができました。
- なんだか読むスピードが上がったみたいです。
- これからも英語の本を時々読んでみたいと思いました。
- まだ苦手ではあるけれど、英語を楽しめるようになったし、もっと読んでみたいと思うようになりました。
半期17〜18時間程度の授業で生徒によって読んだ量もまちまちですが、生徒たちが英語で書かれた本を読むことの楽しさ(興味・関心が高まり意欲的に取り組もうとすること)を感じ、英文を読むコツをつかもうとしていることを手応えとして感じることができました。
* * *
以上の実践を踏まえ,生徒に読ませたいおすすめの本は,以下のシリーズです。
○STEP INTO READING / STEP 1〜5 (Random House
USA)
STEP 1の100語程度からSTEP 5の3000語程度までレベルに分かれていて,カラフルでかわいらしいイラストがなじみやすい本です。セサミストリートやTHE
SNOWMANといったおなじみのキャラクターも登場し,生徒には人気でした。またバスケットボールや野球の偉人を紹介している本もあり,スポーツの好きな生徒の興味を誘いました。
○Penguin Young Readers / Level 1〜4 (Pearson
Longman)

 Graded
Readersの中でも初期学習者向けの本です。Level 2から4までを購入して使用していました。語数はLevel 2で200語から700語程度,Level
4では2000語前後となっています。映画のタイトルや日本の物語など,表紙を見るだけでおなじみのものも多く,写真・イラストから内容を楽しんで解釈することができます。
Graded
Readersの中でも初期学習者向けの本です。Level 2から4までを購入して使用していました。語数はLevel 2で200語から700語程度,Level
4では2000語前後となっています。映画のタイトルや日本の物語など,表紙を見るだけでおなじみのものも多く,写真・イラストから内容を楽しんで解釈することができます。
○Oxford
Bookworms Starters (OXFORD UNIVERSITY PRESS)


 語数にして700語から1700語程度のもので,
SF,ミステリー,古典物語,ホラーなどの内容や,マンガ・冒険ゲームといった様々なジャンル・形式があり,語数の割には取っ付きやすい本ではないかと思います。さすがに難しいレベルのものもありますが,最も集中して読んでいる生徒の姿を見たのはこのシリーズでした。
語数にして700語から1700語程度のもので,
SF,ミステリー,古典物語,ホラーなどの内容や,マンガ・冒険ゲームといった様々なジャンル・形式があり,語数の割には取っ付きやすい本ではないかと思います。さすがに難しいレベルのものもありますが,最も集中して読んでいる生徒の姿を見たのはこのシリーズでした。
参考文献
- 酒井邦秀・神田みなみ編著 『教室で読む英語100万語 ― 多読授業のすすめ』 大修館書店 2005
- 金谷憲著 『英語授業改善のための処方箋〜マクロに考えミクロに対処する』 大修館書店 2002
島津博文 (しまず ひろふみ)
吉富中学校教諭。高等学校講師,福岡県内中学校教諭を経て現職。教員生活14年目の本年度は3年生を担任。
![]()
Copyright (C) 2011 SANSEIDO publishing co.,ltd. All Rights Reserved.