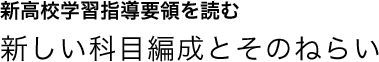![]()
![]()
はじめに
今回の高等学校学習指導要領改訂の基本的な考え方は,新学習指導要領がすでに告示済みの小・中学校と同様に,①教育基本法改正等で明確になった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成すること,②知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること,そして,③道徳教育や体育等の充実によって豊かな心や健やかな体を育成すること,の3項である。「生きる力」は,豊かな心と健やかな体を基礎に,確かな知識・技能を習得し,的確な判断力・表現力を身につけることで育成されていく。
外国語科目の編成
上記の考え方を踏まえて,「外国語を通じて,言語や文化に対する理解を深め,積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り,情報や考えなどを的確に理解したり,適切に伝えたりするコミュニケーション能力を養う」ことを高等学校の外国語の目標と定めている。何かの目的を達成するためにコミュニケーションが行われることを念頭において,「的確に」,「適切に」という文言が加えられている。また,コミュニケーションとは実践的に言葉を使って意志疎通を行うことである,という趣旨がすでに十分に浸透したと考えられるため,「実践的」という文言をことさら加えないことになった。もちろんこの文言が消えても「実践に役立つ」コミュニケーション能力の育成を目指していることに変わりはない。4技能を統合してコミュニケーションの中で内容的にまとまりのある発信ができるようにすること,中学校での学習内容の確実な定着を図り,高等学校での学習に円滑に移行させるための学習機会を設けることの2点が,今回の改善のポイントとなっている。
科目編成を比較すると以下のとおりである。
| 現行の科目編成 | 新しい科目編成 | ||
| 英語Ⅰ* | (3単位) | コミュニケーション英語基礎 | (2単位) |
| 英語Ⅱ | (4単位) | コミュニケーション英語Ⅰ★ | (3単位【2単位まで減可】) |
| OCⅠ* | (2単位) | コミュニケーション英語Ⅱ | (4単位) |
| OCⅡ | (4単位) | コミュニケーション英語Ⅲ | (4単位) |
| リーディング | (4単位) | 英語会話 | (2単位) |
| ライティング | (4単位) | 英語表現Ⅰ | (2単位) |
| 英語表現Ⅱ | (4単位) | ||
| *うち1科目必履修 | ★共通必履修 | ||
各科目のねらい
新設の「コミュニケーション英語基礎」は,中学校と高等学校の学習をスムースに繋ぐことを目的としている。身近な場面や題材に関する内容を扱い,日常的な事柄についてのコミュニケーション活動等を行いながら,中学校における基礎的な学習内容の定着を図る。
「コミュニケーション英語」は,現行の「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「リーディング」を再編し,4技能を発展的にコミュニケーション力育成へと導く科目である。英語の各科目では生徒が英語に触れる機会を充実し授業を実際のコミュニケーションの場とするために,英語での指導を基本とすることも新学習指導要領には盛り込まれている。ややもすれば,文法・訳読が中心となり聞くことや話すことが十分に指導されないなど,4技能の指導が偏りがちであると指摘されていることを踏まえての改善である。
「英語会話」は現行の「OC」の指導内容のうち,特にインタラクティブにコミュニケーションを行う能力を高めることを目的としている。
「英語表現」は,スピーキング,ライティングを中心に発信力を育成する科目として編成された。聞いたり読んだりした内容を踏まえて自分の考えなどを話したり書いたりすることを通じて,論理的思考力や発信力を養う目的も持っている。この科目では,現行の「OC」「ライティング」の指導内容のうち特に,必要な構文・文法を実際に運用して発信する力の育成が期待されている。豊富な題材に触れさせることも明記され,「コミュニケーション英語」をサポートする意味合いが濃い。
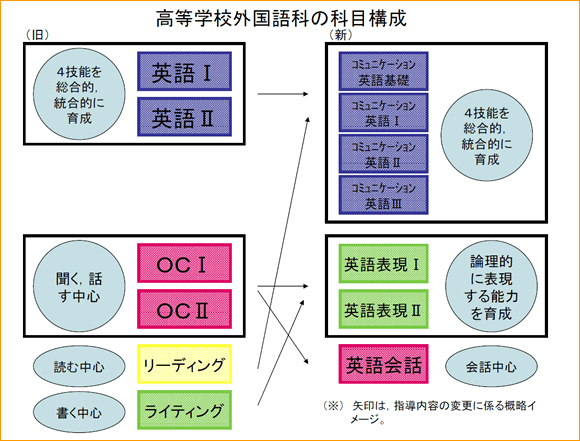
(出典:文部科学省http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/news/081223/014.pdf)
必修科目移動の経緯
卒業単位数は現行どおり74単位のままだが,週当たりの授業時数(全日制)は標準の30単位時間を超えることもできることが明確化された。また,共通性と多様性のバランスを重視して,学習の基盤となる国語,数学,外国語に新たに共通必履修科目を設定することになった。それを受けて,現行の「英語Ⅰ」と「OCⅠ」の内容にほぼ相当する「コミュニケーション英語Ⅰ」を共通必履修科目と設定した経緯がある。
語数の増加について
新学習指導要領では,言語活動,理数教育,伝統や文化に関する教育,道徳教育,体験活動,外国語教育の充実と,職業に関する教科・科目の改善を教育内容の主な改善事項としている。「外国語教育の充実」を受けて,高等学校で指導する標準的な語数を,中学校で学習した語に「コミュニケーション英語Ⅰ」でプラス400語,Ⅱでプラス700語,Ⅲでさらにプラス700語程度の新語を加えた数としている。中・高等学校を合わせて3,000語程度にまで増加する。これまで改訂を重ねるごとに,指導できる語数が少なくなりすぎるという批判があり,意思疎通を十分行うためには増加が必要という判断の結果といえる。
今回の改訂は,情報や考えなどを的確に理解し,適切に伝えるコミュニケーション能力を養うことを,以前にも増して強く打ち出しており,文法指導の改善と共に慣用表現や指導すべき語数の充実も図られている。中学校では週当たりの授業時間数が1時間増となり,指導語彙数も300語増え1,200語程度となるので,計算上は,これまで高等学校で指導していた語彙の15〜25%程がすでに中学校で指導済みとなる。高等学校ではさらに新しい語彙・慣用表現を加えて,より高いレベルのコミュニケーション能力を養っていくことが望まれる。
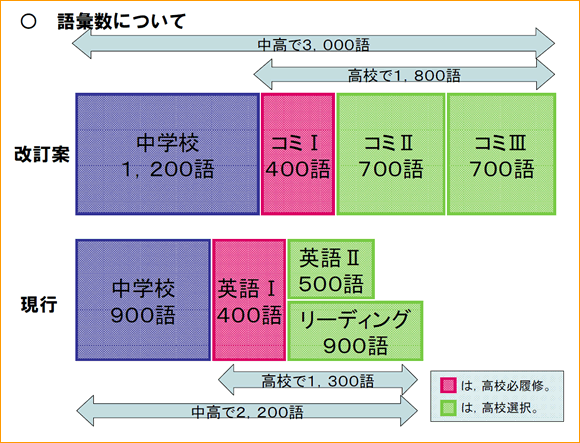
(出典:文部科学省http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/news/081223/014.pdf)
最後に
中学校英語の十分な運用力を基礎に,高校英語にスムースに移行し,必要な構文・文法を確実に身につけて初めて,コミュニケーション力が培われる。基礎的な知識がないままにコミュニケーションの練習のみを行っても,砂上の楼閣である。学習者の持つ英語力に応じて,生徒それぞれが運用力を伸ばせる授業を目指す現場の対応はそう容易くはない。
中学校で平成24年度に新学習指導要領が全面実施されるのを受けて,高等学校外国語は25年度入学生から学年進行で新学習指導要領の実施となる。他の科目に比べて,いま少しの余裕はあるが,授業科目の編成などの根本的変更に加えて,学習者中心のコミュニケーション指導や,教師の英語使用のあり方等,大きな変革に備えて着々と準備をしていきたいものである。
金子 朝子(かねこ ともこ)
昭和女子大学教授。専攻分野は第二言語習得,英語教育(特に英語学習者コーパス,教室内のインタラクション)。 主な著書に『中学総合的研究英語』(旺文社),『第二言語習得序説』(研究社)など。
![]()
Copyright (C) 2011 SANSEIDO publishing co.,ltd. All Rights Reserved.