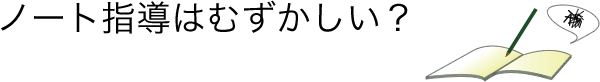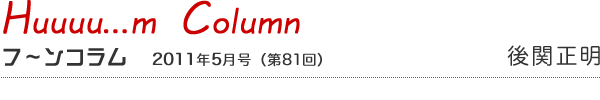
先日、都内のK先生からメールで次のような質問がありました。
「現在、中2の生徒を教えています。先日、ノートを提出させたところびっくりしました。ノートを見ると私の板書をノートしているのですが、大半の生徒はただ乱雑に写しているだけなのです。私はノート指導を重視して、特に『ふり返り学習に絶対に必要だからそのつもりで板書を写しなさい』と常に言っているのですが、なかなか徹底しません。どうしたら役に立つノートづくりをさせることができるでしょうか。ご教示ください。」
私がはるか昔の中学1年生のとき、英語のノートを熱心にとったことをよく覚えています。なぜ覚えているかというと、皮肉にもそのノートが中間や期末試験のときにほとんど役に立たなかったからです。実際、ノートのとり方も下手だったし、板書を写すにもただ先生にせかされて写すだけ、それをその日のうちにふり返り学習で活用し、足りない部分を自分で付け足して理解しておけばよかったのでしょうが、そういう指導もなかった。そのうち学年が上がるにつれてノートの重要性がだんだん分かってきたのです。「板書だけをただ写していたのではだめだ。板書の前後の先生の発言をメモしておかなくては……」と思うようになりました。K先生も中学生時代のノートのとり方について思い出してみてください。どうでしたでしょうか。
そこで私が生徒たちにノートについての指導をしたとき、特に注意を促したのは「後でノートを見たとき、授業の様子の一部だけでも思い出せるようなノートのとり方をしてごらん」ということでした。要するにノートを見返したとき、少なくとも授業のポイントだけは思い出し、それを覚え、身につけるように、という指導を早い段階から行いました。それを下記にまとめてみます。
生徒側から見たノートの役割と注意事項
- 復習として、特にテスト前の学習で役に立つノート。
(授業の内容が思い出されるような書き方を普段から心がける。)
- 整然ときれいに書くより、走り書きやメモ書きも添えてあるノート。
(見た感じがきたなくなるが、自分だけが分かっていればよい。)
- 復習や予習のとき、気付いた事柄を書き、更に詳しく調べたら、それも忘れないように記録しておくノート。
(ノートは、あらかじめ余白を多くとってゆったりと書いておくことが必要。余白が十分にあれば新出語や忘却語、またはパターンプラクティス的に入れ替えの語や文も書ける。)
- 復習をする時は、蛍光ペンで大切な部分をなぞっておく。
(あまり多くの色を使わないこと。せいぜい赤と黄色の2色が望ましい。)
教師側から見たノート指導の実際〜板書に関連させて〜
- 生徒はとりあえず教師の板書を写すので、教師は学習内容の確認と定着を図るためにまず時間ごとの板書計画を立て、整然と板書することが大切。
(コラム 第21回 参照。思いつきで縦に書いたり斜めに書いたり、また〇、△、→などで黒板を乱雑にしないこと。)
第21回 参照。思いつきで縦に書いたり斜めに書いたり、また〇、△、→などで黒板を乱雑にしないこと。)
- 先を急ぎたがる教師がいるが、板書写しでは生徒にある程度の時間を与える。(始めは遅筆の生徒も目立つが、慣れてくればだんだん速く写せるようになる。)
- 板書写しの時間を節約するため、あらかじめハンドアウトを作り、それをノートに貼らせる教師がいるが、これはごく少数回にとどめる。
(生徒が実際に手を動かして「書くこと」(書写)に慣れさせる必要があるから。)
- 折にふれてノートを提出させ点検する。
(ノートを見ればどの程度理解しているか見当がつく。すなわち生徒個々の学習状況が分かり、形成的評価の一助となる。また、そこから次の授業への反省材料が得られる。)
- 時間や手間がかかっても、ノートを点検したら「検印」だけでなく賞揚のことばを書く。
(生徒は褒められて育つもの。)
以上、自分自身の体験と実践を中心にまとめてみましたが、先生の学校の実態に応じていろいろと方法をアレンジして実践することができるでしょう。ご参考になれば幸いと思います。
次回は、板書(コラム ![]() 21回 ・
21回 ・![]() 22回 参照)とノート指導との関係についてもう少し掘り下げ、さらに練習帳としてのノートについてお話したいと思います。
22回 参照)とノート指導との関係についてもう少し掘り下げ、さらに練習帳としてのノートについてお話したいと思います。
東京都墨田区立中学校で教諭,校長を長年務める。その後,東京都滝野川女子学園中・高校で教鞭をとる。現在,NPO法人「ILEC言語教育文化研究所」常務理事。2003年より國學院大学で教職課程履修の学生を教えている。
ご質問がございましたらニュークラウン指導相談ダイヤル(03-3230-9235 受付時間 月・火・木曜日 10:00 〜 16:00)へどうぞ。
Copyright (C) 2011 SANSEIDO publishing co.,ltd. All Rights Reserved.