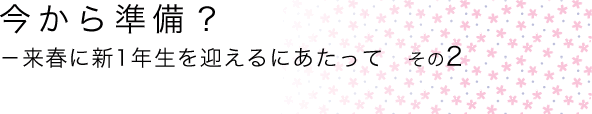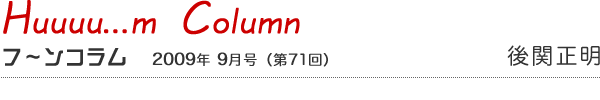
フーンコラム先月号(8月号・第70回)では,区立中学校に勤務するY先生と,小学校外国語活動を経験してくる新入生を受け入れるコツについて,話したことを載せました。今月号は,そのつづきをご紹介いたします。
| 私 : | 今と昔の新入生では,英語に対する関心の点でも差が出てきたという話を聞きます。これまでは,ほとんどの新入生が,中学校英語の授業に興味や関心を寄せていそうでしたよね。何しろ,英語は,学校教育においては,中学校で初めて学習する教科でしたから。ところが,今では状況が違っています。2009年8月8日付けの日経新聞によれば,新入生の約9割が,すでに小学校で英語にふれているようですが,そのうち,英語に興味を持った生徒は約4割ほどだそうです。この人数が多いか少ないかは別として,とにかく,英語に対する関心の点でも,以前とは違った雰囲気が中学校入門期の教室にはあるようです。 |
| Y先生: | それも1つの心配の種なんです。 |
| 私 : | 心配することはありません。新入生は,中学校に入ったら,「また新しい気持ちで英語を勉強するんだ」という気概を持っていたりもします。不安もあるでしょうけれど,生徒の期待も大きいことは確かです。その生徒の期待に応えるためにこそ,小学校と中学校の先生方の間でよい人間関係をつくり,小中連携をスムーズに進めていくことが必要になるでしょう。 |
| Y先生: | とおっしゃいますと? |
| 私 : | 来春に中学校1年生を担当する予定の英語教師(未定の場合は英語科の全教師)と,現在の小学校6年生の担任の先生とが仲良くなることです。 |
| Y先生: | 私は,小学校6年生の担任の先生はおろか,小学校の先生方は誰も知らないのです。 |
| 私 : | 実はそういうケースは多いようです。 |
| Y先生: | では,どうすれば? |
| 私 : | まず,小学校,中学校の校長先生同士や副校長先生同士に橋渡しをしていただき,話し合いの場を設けてもらうのです。もちろん,その場合には,まず前提として,双方の校長先生や副校長先生に,外国語活動や英語について,関心を持っていただく必要があると思います。 |
| Y先生: | かなり大きな話になりはしませんか。 |
| 私 : | おっしゃる通り,そうなりますね。しかしながら,小中連携については,個々の先生方を越えて,体制として,校長先生や副校長先生方に,一生懸命やってもらわないと,小学校ごとに外国語活動の質に差があるという実態が続いていくことになるともかぎりません。秋口から始めて,月に1回ぐらいの割合で会合を持つくらいの熱意が欲しいですね。 |
| Y先生: | そのための時間設定は難しいでしょうね。 |
| 私 : | それは十分承知しています。通り一遍の小中連絡会ではなく,目の前にある「小中連携」という大目標を掲げた話し合いになりますから,時間も労力もかなり使うことになるでしょう。しかしながら,結果的に,日本の英語教育全体の質を高めることに通じる仕事になるわけですから,やりがいはあるはずです。 |
| Y先生: | 忙しい中で,何とか時間を割いても行うべき大事な話し合いですね。この1年の問題ではなく,将来を見据えた問題の端緒になるのですから。 |
| 私 : | その通りです。小・中・高の間に結ばれる「コミュニケーション活動」という1本の大事な線の大本となる話し合いです。 |
| Y先生: | 中学校は,小学校からバトンを受け,高校に渡すという難しい立場ですね。 |
| 私 : | そう難しく考えると,マイナスイメージばかりが強くなってしまいます。話し合いの場においても普段の授業においても,もっと積極的に,小学校からあがってきた生徒たちのよい点を探し,それを認めることです。生徒たちは,今までとは違い,例えばALTにも臆することなく,親しみを持って接することに慣れていますよね。そういう生徒の態度面だけでもプラスに思わないと…。 |
| Y先生: | 小学校外国語活動の「素地」は,スポーツなどのウォーミングアップと考えればよいですね。 |
| 私 : | そうです。暖まった生徒の体が冷えてしまわない内に,それを活かして,いわゆる「キャッチボール」につなげていけるとよいですね。もちろん,暖まり具合には個人差があることも忘れてはいけません。話は,より固い内容のものになるかとは思いますが,私の経験では,アフターファイブの会合で,かなり打ち解けることができます。そして,1度打ち解けてしまえば,その後の会合がとてもスムーズに運びます。これは,必ずしも皆さんにお勧めするわけにはいきませんが(笑) |
| Y先生: | だいたいの方向が見えてきました。大きな課題ですが頑張ってやってみます。ありがとうございました。 |
| 私 : | ご奮闘をお祈りします。 |
後関 正明 (ごせき まさあき) 先生
東京都墨田区立中学校で教諭,校長を長年務める。その後,東京都滝野川女子学園中・高校で教鞭をとる。現在,NPO法人「ILEC言語教育文化研究所」常務理事。2003年より都内の私立大学で教職課程履修の学生を教えている。
東京都墨田区立中学校で教諭,校長を長年務める。その後,東京都滝野川女子学園中・高校で教鞭をとる。現在,NPO法人「ILEC言語教育文化研究所」常務理事。2003年より都内の私立大学で教職課程履修の学生を教えている。
ご質問がございましたらニュークラウン指導相談ダイヤル(03-3230-9235 受付時間 月・火・木曜日 10:00 〜 16:00)へどうぞ。
Copyright (C) SANSEIDO publishing co.,ltd. All Rights Reserved.