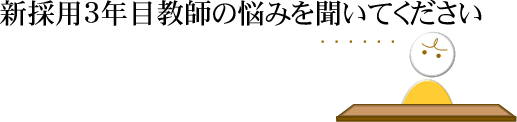![]()
![]()
今回は東京都K区T中のY先生からお電話をいただきました。
| Y先生: | 私は先日,K区の研修会に参加しました新採3年目のYと申します。その節は有難うございました。 私は,1年目,2年目と,あと先も見ず,もうひとりの先輩の後を追いかけるようにして,ただ夢中で過ごしてきました。その間,区内の研修会で授業を拝見したり,ビデオを見たり,時には「達人」と言われる評判の高い先生の講演などを拝聴しました。それらを糧に自分の授業の改善に役立てたいと考えているのですが,研究授業やビデオを拝見しても,どうもピンと来ないのです。参考にしようという気持ちはあるのですが…。 |
| 私 : | ピンと来ないというのはどういうことでしょうか。ひとつの原因としては,例えば,研修会に出たり,話を聞いたりする際に,具体的な課題を持っておられないことが考えられますが…。 |
| Y先生: | 言いかえれば,漫然とした態度で研修会に出たり,研究授業を見たりしていないかということですか。 |
| 私 : | ずばり言えばそうですね。Y先生はいろいろと3年目ならではの悩みをかかえていらっしゃいますね。 |
| Y先生: | ええ,いろいろ問題だらけなんです。 |
| 私 : | それでしたら,先生の悩んでいる課題をよく考えながら具体的に箇条書きにまとめてみたらどうでしょう。 例えば,
|
| Y先生: | あ,それそれ,うちにはそういう生徒がたくさんいるんです。 |
| 私 : | それも問題のひとつでしょう。そういうものを洗いざらいあげてみて,それでは,それぞれの問題をどうすれば解決できるかを考えてみるといいと思います。そして,すぐに改善しようと思えばできること,また自分ひとりではどうにもならないことなどを項目別に考えてみるのはいかがでしょう。そうすると,毎日の授業の中で,どの点についてどんな悩みがあるのかがはっきり見えてきます。つまり,問題点が明らかになってきます。そういう問題点をいくつか持って研究授業や研修会にいくと必ず接点が見つかるものです。同じような課題が見えれば自分のそれとくらべることもできます。同じ次元でものごとを観察できるわけですね。すると,共感したり逆に疑問を持ったりしながら会に参加することができます。解決の糸口も見つかり,ひとつでもそれがあれば参加した意義があるわけです。 ところで,現時点での具体的な悩みは何ですか。 |
| Y先生: | さっきお話した「宿題忘れ」なんです。 |
| 私 : | なるほど。でも,宿題をやってこない生徒が多いのは,出し方が悪いということも考えられないですか? 出し方に工夫が足りないとか。 |
| Y先生: | えっ,そうなんですか? |
| 私 : | そういうことも考えられます。一般的に言って,生徒を一方的に責める前に教師の側が反省すべき点も沢山ありますよ。例えば,テストのできが悪いのは問題の出し方が悪いからだ,ということも考えられます。宿題にしてもただ「やって来い」式では生徒はついてきませんよ。 |
| Y先生: | うーん,そうですか。私のやり方にも問題があったのですね。 |
| 私 : | もちろん,生徒に非があることもありますが,その前に教師が謙虚にものごとを考える必要があると私は思います。そういう私も若いころ職員室で採点中に生徒の点が悪いのでブツブツ文句を言っていたとき,ベテランの先生に「問題の出し方が悪いんじゃないの?」と言われたものです。ショックでした。思いもよらなかったことをつかれたのです。 |
| Y先生: | うーん,今の私みたいですね。 |
| 私 : | そうかもしれないですね。歴史は繰り返す,です(笑) |
| Y先生: | いやぁ,参りました(笑) |
| 私 : | それを改善するには,まず宿題の意義を生徒に分からせることですね。つまり,宿題の目的・理由をはっきりさせ,その上で宿題の内容を説明し,生徒にやる気を起こさせること。生徒が「簡単だ」「余裕だよ」とか「これは難しいぞ」「時間がかかるぞ,でも頑張るぞ」などと実感するように指示をする事が大切です。そうすれば,まるで宿題に無関心な生徒はいなくなると思います。 |
| Y先生: | 宿題ひとつに関してもそういう配慮が必要なんですね。 |
| 私 : | そうですね。そういうことが,生徒一人ひとりを大切にする教育につながっていくのだと思っています。長くなりますので一例だけを挙げましたが,また具体的にいろいろと質問してください。 |
| Y先生: | はい,分かりました。細かいところまで教えていただき,ありがとうございました。 |
| 私 : | どういたしまして。頑張ってください。 |
電話後の私の感想:
Y先生が,今後,宿題ひとつにしてもそういう配慮を続けていくことができれば,Y先生の英語授業全体に,さらには教育活動全体に配慮が行き届くことになるでしょう。そうすることで,Y先生の英語教育に対する信念が確立され,また学校の教育課程全体に対する見方が広がっていくと思いました。
後関 正明 (ごせき まさあき) 先生
東京都墨田区立中学校で教諭,校長を長年務める。その後,東京都滝野川女子学園中・高校で教鞭をとる。現在,NPO法人「ILEC言語教育文化研究所」常務理事。2003年より都内の私立大学で教職課程履修の学生を教えている。
東京都墨田区立中学校で教諭,校長を長年務める。その後,東京都滝野川女子学園中・高校で教鞭をとる。現在,NPO法人「ILEC言語教育文化研究所」常務理事。2003年より都内の私立大学で教職課程履修の学生を教えている。
ご質問がございましたらニュークラウン指導相談ダイヤル(03-3230-9235 受付時間 月・火・木曜日 10:00 〜 16:00)へどうぞ。
Copyright (C) SANSEIDO publishing co.,ltd. All Rights Reserved.