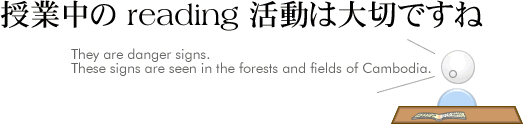![]()
![]()
S区のO先生から次のようなメールをいただきました。
最近研究授業に参加したり,ビデオによる研究授業の公開に参加したりして,勉強する機会が何度かありました。そこで感じたことがひとつあります。それは授業内でのreading活動の時間がとても少ないことです。極端に言えば「ない」に等しいときがあります。私は中学校の授業ではreading,特にoral reading(音読)が必要だと思いますし,現に,私はかなりの時間をかけてやっています。このことについて,先生はどのようにお考えでしょうか。
ざっとこんな趣旨です。
私もさっそくメールで次のようにお答えしました。
確かにおっしゃる通り,最近の研究授業では,oral readingやsilent readingなどのreadingにかける時間が少ないようです。readingはどちらかというととても地味なactivityなので,研究授業などでは,どうしても活発で一見華やかなactivity,例えば,ペアやグループでのコミュニケーション活動の方に傾きがちになるのかもしれません。しかし,私もoral readingの活動は中高生の段階では絶対に必要だと思っていますし,今までずっと実行してきました(英語教師志望の大学生にもoral readingは今でもやらせています)。今回は,silent readingは別の機会にゆずり,oral readingに絞って述べてみたいと思います。
さて,何故oral readingが大切なactivityかというと,oral readingをするには,一般的に,英文の強勢(stress)や文の調子(intonation)に注意しながら正しく読むことが要求されるからです。ともすると,声の大きさや調子を重視するあまり,内容理解や内容把握がおろそかになるとの説もありますが,私の考えでは,中学生の段階で大きく口を開き明瞭に正しい発音で英文を読む習慣を身につけることは,大切なことだと思っています。そうしないと小声で口先だけの発音になり,ちょっと難しい単語になるといい加減にごまかして発音したり飛ばしたりするようになります。それに,だんだん発音に自信がもてなくなり,内容理解や内容把握にまで悪影響を及ぼすと考えられます。
個人にしても,ペアやグループにしても,またクラスの一斉読み(これには異論があることは承知していますが,ここではあえて触れないでおきます)にしても,私は「元気よく,大きな声で,はっきりと」をモットーに指導してきました。そのときの留意点としては,いわゆる一語読みは避け,意味のかたまりを考えて語群を把握させることです。このような習慣が身につけば,家庭学習でも音読をするようになります。また,速度にも慣れれば,徐々にnormal speedになり,決して不自然な読みにはなりません。要するに,生徒がいかにreading,特にoral readingの習慣を授業中に身につけるかが問題となるのです。
また,oral readingばかりに時間をかけると生徒が飽きてしまうのでは…と心配される先生がいらっしゃいますが,そこは創意工夫で切り抜けられると思います。例をNEW CROWN 2 Lesson 8“Landmines and Children”にとってみます。私はSection 1のnarrativeを次のように展開していきます。
| A(男子): | What are these? |
| B(男子): | 同じ文を繰り返す。 |
| 男子全員: | 同じ文を繰り返す(以下「repeat」で表す)。 |
| C(女子): | They are danger signs. These signs are seen in the forests and fields of Cambodia. |
| D(女子): | (repeat) |
| 女子全員: | (repeat) |
| E(男子): | What is the danger ? |
| F(男子): | (repeat) |
| 男子全員: | (repeat) |
| G(女子) | Landmines. |
| H(女子) | (repeat) |
| 女子全員: | (repeat) |
| I(男子): | Cambodian children like to play in forests and fields, just like you and me. |
| J(男子): | (repeat) |
| 男子全員: | (repeat) ... |
ここでの手順を示すと次のようになります。
- あらかじめ繰り返しのルールを決めておきます(個人→個人→全員など)。
- 男子,女子とも個人が読む文を指名または挙手で決めます。
- 2回目は男子と女子の役割を入れ替えます。
※ 女子全員のときに男子が間違えて大きな声でrepeatすると教室にどっと笑いが起こりなごやかな気分で盛り上がります(間違えた生徒には,もちろん教師がバックアップ)。
- 誰がどこを読んでいるのかを常に注目していないと間違うので,生徒の集中力が高まり,クラスの友達の音声を注意深く聞く習慣がつきます。
- いちばん重要な文(ここではThese signs are seen in the forests and fields of Cambodia.)の場合は,臨機応変に3回,4回と繰り返しながら定着を図ります。
- 感情的に高まる語や文は,それらしくジェスチャーを交えて発音します(ここでは“Landmines.”)。
- 教科書を開いたままのoral readingから閉じたoral readingに発展させてもよいでしょう。
※ もし,このactivityをconsolidationの段階で行うとしたら,本文の活字を見ながら(または教科書を閉じて)クラスの友達のoral readingを聞くことになるので,習った教材の理解を一層深めることが期待できます。
以上のようなoral readingにより,readingが上手になり,全体の集中力が増し,他者の発音に耳を傾けるようになれば,最終的には内容の理解や把握を促進させることにもなるのではないでしょうか。ぜひ試してみてください。
東京都墨田区立中学校で教諭,校長を長年務める。その後,東京都滝野川女子学園中・高校で教鞭をとる。現在,NPO法人「ILEC言語教育文化研究所」常務理事。2003年より都内の私立大学で教職課程履修の学生を教えている。
ご質問がございましたらニュークラウン指導相談ダイヤル(03-3230-9235 受付時間 月・火・木曜日 10:00 〜 16:00)へどうぞ。
Copyright (C) SANSEIDO publishing co.,ltd. All Rights Reserved.