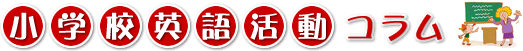
![]()
渡邉時夫 (清泉女学院大学)
1.はじめに
私が長野県内の公立小学校について調査した結果によりますと,ほとんどの場合,評価は単位時間について実施しており,学期や年間など中・長期にわたり継続的・組織的に行っているケースはかなり少ないことが分かりました。
しかし,5・6年生の2年間を通して,①ことばや文化についての体験的な理解,②積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度,③外国語(英語)の音声や基本的な表現に対する親しみ方などについて,目標達成に向かって学習が進んでいるかどうか,常に大局的な視点から評価を継続していなければならないと思います。
そこで,今回は継続的に評価を行う方法や実践結果について,具体案を述べてみたいと思います。
2.1単元(またはそれ以上)に及ぶ期間を通しての評価の実践
1単位時間だけでなく,1つの単元やレッスン全体の中で,一人ひとりの子どもたちが,それぞれの観点から見て,どのような活動をしていたかを記録・評価する試みの紹介です。
『英語ノート』(文部科学省)は,各レッスンに平均4時間を配当していますので,下記のような表を作成します。各授業の終わりに子どもたちが提出する「振り返りカード」そのものでは,全体像や個々の子どもの学習や成長過程がつかみにくいという欠点があります。そこで,子どもたちの自己評価を基礎資料として,指導者の評価を加えながら表をうめていきます。
記録することは,それ自体が比較的単純であることに加え,個々の子どもの学習上の変化が比較的明示的に表れるという利点があります。大勢の子どもを対象とすることが負担に感ずる場合は,何人かの子どもを選んで実践することもよいでしょう。
このような評価により,指導者の指導方法や授業内容について,長所や改善すべき点も明確にできるでしょう。一人ひとりの子ども用にカードを作り,子ども自身に継続的に記入させると,単に時間内の「振り返りカード」とは違った効果も期待できると思います。また「振り返りカード」の併用も一案です。
なお,表中の「◎」,「○」,「△」の記号は,それぞれ,「満足」,「ほぼ満足」,「満足とは言えない」を表しています。
例えば,表中の子どもについて,次のような評価が可能でしょう。
☆ Aさんは,①当初から意欲的であり,②次第に英語を聞くことに馴染んできたが,表現することには依然として抵抗があるようです。
☆ 第2週目については,「表現することへの慣れ親しみ」は多くの子どもが「△」になっており,「言語や文化に関する気づき」に関しては全員が「△」をつけています。このことから,指導方法,その他に問題があったのではないか,と推測されます。
☆ 総合的に見て,いずれの生徒も回を追うごとに満足度の高まりが明確です。
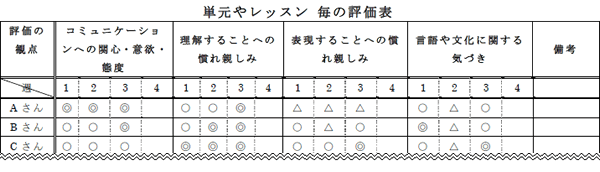
3.一人ひとりに長期用評価表を配布した実践例
次に,長野県富士見町立富士見小学校の実践例を取り上げてみましょう。下記に富士見小学校の「振り返りノート」を紹介します(フォーマットは筆者流に変えてあります)。
なお,「評価の観点」(①~④)の内容は下記の通りです(子どもたちにはこちらの表で説明)。
① 自分の良かったところ,頑張ったところ。
② 先生や友だちと楽しく会話をしましたか。
③ 友だちの良かったところ,頑張ったところ。
④ 今日の学習の感想を書きましょう。
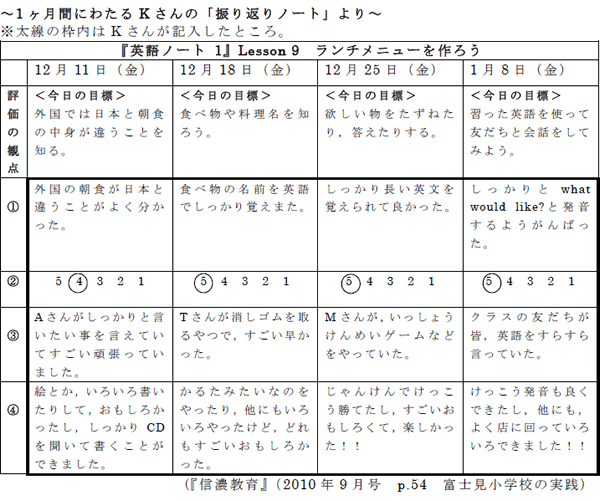
Kさんの「振り返りノート」から読み取れることなど
☆ 評価の観点①については,表に書かれている表現に引っ張られて,多少個性が出にくくなっているのではないか,と思われます。<今日の目標>の表現を変えて,「国による朝食の中身を比べてみることを通して各国の食事に興味を持つ」としたり,観点①の表現を「自分の頑張ったところや気づいた点」などとすれば多少個性的なコメントが期待できたのではないかと思います。Kさんの学びについて,広い視点から評価が可能になったかもしれません。
☆ 評価の観点②については,2回目以降ゆとりが生まれ,しっかり楽しみながら学んでいます。
☆ 評価の観点③については,Kさんは,毎回違う友達に関心を寄せています。しかも,そのすべての友達の良さを見出している様子も表出されています。コミュニケーションへの積極的な態度は,このように暖かい人間関係を築くことから始まるわけで,これこそが正に「素地」の大切な一部になっていると思います。
☆ 評価の観点④については,毎回経験的に学習が進められており,そのような活動中心の授業に興味を見出していることが分かります。
Kさんの「振り返りノート」に関する限りは,ことばや文化についての「気づき」の様子があまり明確ではありません。しかし,他の子どもたちの評価を比較したり,指導者同士が担当クラスの「振り返りノート」を交換し合ってみると,指導者にとって多様な気づきや学び合いが生まれるのではないでしょうか。このような中期的な評価法は子どもたちの学びの過程が明示的であり,子どもたちにとっても,また指導者にとっても有効であることは間違いありません。ただ,子どもたちの内面をもっと多様な形で表出させるために,評価の観点の表現を工夫する必要があるように思います。
4.長期的な視点に立った評価
子どもたち自身の言葉による評価は,子どもたちの評価能力の伸長や学習意欲の向上等にとって,大変有効だと思います。しかし,表現力の乏しさなどにより,評価が的外れであったり,指導者が求めている点について言及がなかったりなどの欠点は免れません。
そこで,指導者が評価したい点について,進歩の度合いが段階的に分かるような説明文を考えて,一覧表を作成し,1ヶ月か2ヶ月に1度,該当する説明文を選択するような方法も有効と思います。下記の具体例をご覧下さい。説明文については,指導者個々が授業のねらいにより,子どもたちの進歩の様子が分かるよう適宜工夫すると良いと思います。観点毎に,熟達度を表す表現を考え,「具体的な評価表現」欄に記入します。
観点毎に4~5くらいの段階に分けて表現するのが適当と思います。子どもの姿を表している表現の数字に○印をする。例えば,渡邉君の場合,6月には「理解すること・表現することに慣れ親しむ」が6だったのが,9月には4,12月には3に上がっているなど,子どもたち一人ひとりの進歩の様子が具体的に分かるでしょう。
○で囲む場合に,例えば6月は黒で,9月は赤で,12月は青を使えば分かり易いでしょう。
また,例えば,多くの子どもたちが,「言語や文化に関する気づき」が一定のレベルで留まっている傾向があることが分かれば,指導者は,この面における自分の教授内容や方法に問題があるかもしれない,と気づくこともできますので,子どもの評価だけでなく,指導者の評価にも役立つ事になると思います。
下記の表を参考にして下さい。
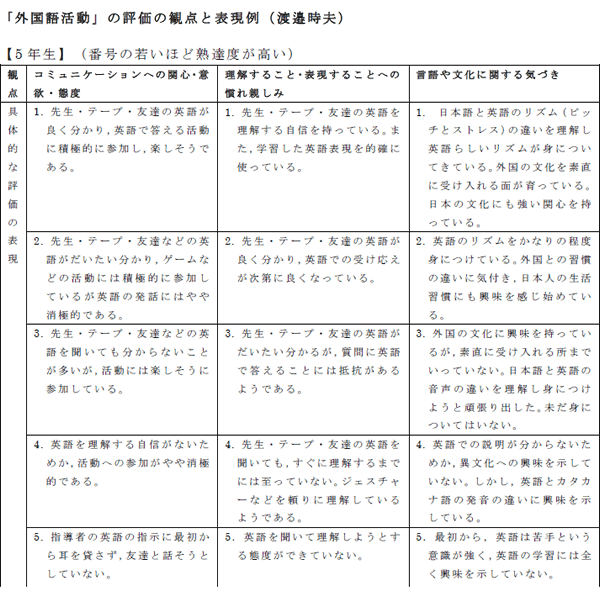
5.おわりに
個々の指導者から集めた若干の資料を基に,渡邉のコメントを追加し,第24回のコラムを締めくくります。
(1) ことばや文化について…大多数の教員は『英語ノート』を多用しており,そのためもあって,教員が一方的に情報を与えてしまっている,と反省している教員が非常に多い。文化については,どんなテーマを選ぶか,そして,どのような資料を準備し,どのような活動を導入するか,『英語ノート』のみに頼らない姿勢がほしいと思います。「自文化中心主義」から「文化相対主義」へと子どもたちを導く工夫が求められています。
ことばの教育の面では,発音に偏る傾向が認められます。ことばの使い方や生活習慣との関わり等,ことばの不思議や面白さをもっと発掘する必要を感じます。
(2) Listeningと英語による表現について…‘listening before speaking’が徹底してきたと感じました。ALTの配置が不十分な地域や学校の中には,listeningの量や質を考慮し,事前にnative speakers等に録音を依頼し,授業で活用しているところもあり,このような努力は是非参考にしたいと思います。Listeningの機会が多いクラスほど子どもたちの発話が多い,という傾向も多くの教員が認めています。
(3) その他…保護者を対象に「外国語活動」の目標を正しく伝えてほしいという希望も多いことが分かりました。評価の在り方と併せて今後の大きな課題だと思います。
「コミュニケーション能力の素地」が,目標どおりに達成された場合,どのような状態を意味するのでしょうか。次回から数回に渡り,今春卒業生を中学校に送り出した先生方に活動の内容と育成された素地についてご具体的にご報告いただきたいと思います。
Copyright (C) 2011 SANSEIDO publishing co.,ltd. All Rights Reserved.