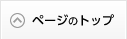国立教育政策研究所は、2013年3月に「教育課程の編成に関する基礎的研究」の[報告書5]において、「21世紀型能力」を提案しました。
以降、大きな反響を呼び、翌2014年3月には理論的検討・事例研究を加えた[報告書7]が出されました。
さらに本年2015年にも新しい教育課程編成・授業実践に資する資料とともに再提案される予定になっています。
「知識基盤社会」「多文化共生社会」「情報化社会」の本格化・高度化が進み、これまで誰も経験したことのない、複雑で激しく変化する社会を生きるために、教育も常に改革が求められています。
知識・技能の習得を学びのゴールとするのではなく、状況や課題に応じてそれらを活用し、また、他者とコミュニケーションをとりながら協働的に問題解決にあたる資質や能力が、社会を構成する私たち一人一人に必要とされる時代を迎えているといえます。
このような社会を背景として、「何を知っているか」を学力の中心とする近代型の教育から、「実生活や実社会においていかに知識や技能を活用して問題が解決できるか」を育成すべき力の中核に据える教育への転換が志向されてきました。
この流れのなかで登場したのが「21世紀型能力」です。こうした教育施策の潮流は、「コンピテンシー」(OECD、EU、ドイツ・フィンランド・ニュージーランドなど)や「21世紀型スキル」(アメリカ)に見られるように、世界の教育界の動向に共通するものです。
「21世紀型能力」は、「生きる力」として必要な資質・能力をより明確に定めており、「生きる力」をより実効性のあるものとして発揮させるために、それらの資質・能力をどのようなかたちで教育目標・教育内容に落とし込んでいくかという、今後の教育課程の方向性を示唆するモデルとなっています。
21世紀型能力では、
教科・領域横断的に学習することが求められる能力を
汎用的能力として抽出し、
それらは「基礎」「思考」「実践」の3つの観点で再構成されます。

*3つの力は相互に関連しながら高め合っていく(そのため、長方形の階段状の積み重なりではなく、円の重なりで図化される)。
[例]基礎力は思考力の支えとなるが、思考力育成に伴って基礎力が育成されることもある。
*3つの円が重なることで、どのような授業でも、21世紀型能力という資質・能力を意識して行う必要があることを示している。

自分の行動を調整し、生き方を主体的に選択するキャリア設計力、他者と効果的なコミュニケーションをとる力、協力して社会づくりに参画する力、倫理や市民的責任を自覚して行動する力などが含まれます。


自分の行動を調整し、生き方を主体的に選択するキャリア設計力、他者と効果的なコミュニケーションをとる力、協力して社会づくりに参画する力、倫理や市民的責任を自覚して行動する力などが含まれます。


言語、数、情報(ICT)を目的に応じて道具として使いこなす力とされます。「読み書き」「計算」などの基礎的な知識・技能とともに、技術革新を背景に情報化が著しく進む時代を生き抜く基礎力として「ICTスキル・情報リテラシー」が不可欠なものとして設定されます。

社会の変化に対応する教育課程を編成するために、
次の3点を共通認識とする必要があるとされています。

※報告書5p.26「教育課程の編成原理と「21世紀型能力」」(*1)より抜粋
これを今後の検討の出発点とするべく、「原理」と呼び、それに基づいて、具体的な教育目標を構想する。まず、変化の激しい時代には、読み書き計算といった基礎的なリテラシーを超えた教育目標が必要なことは明白である。社会の変化の特徴と諸外国、我が国の教育政策の動向を踏まえると、それは、未知の問題に答えが出せるような思考力と、教室外の現実の問題も他者との対話を通して解決できるような実践力だと言える。「生きる力」が、この21世紀を生き抜く力だと考えれば、こうした実践的な問題解決力・発見力こそが、その根幹を成すと考えられる。
参考:
*1 国立教育政策研究所(2013).『社会の変化に対応する資質や能力を育成する教育課程編成の基本原理』(教育課程の編成に関する基礎的研究 報告書5).
*2 国立教育政策研究所(2014).『資質や能力の包括的育成に向けた教育課程の基準の原理』(教育課程の編成に関する基礎的研究 報告書7).
*3 文部科学省(2014).「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会」の「論点整理」.
*4 石井英真(2014).「21世紀をよりよく生きていくのに必要な資質・能力をとらえる枠組み─目標の分類と構造化─」(『指導と評価』第60巻6月号 図書文化).
*5 西岡加名恵(2014).「カリキュラムにおいて汎用的スキル等をどう位置づけるか」(『指導と評価』第60巻7月号 図書文化).
*6 P.グリフィン他編/三宅なほみ(監訳)益川弘如・望月俊男(編訳)(2014).『21世紀型スキル:学びと評価の新たなかたち』北大路書房.
21世紀型能力を育成するための
授業や教育課程編成の視点
「報告書7」(*2)では、学習理論や学習に関連する諸研究の調査・分析をもとにして、21世紀型能力を育成するための授業づくりや教育課程編成の視点として以下の7つが提案されています。これらの視点にもとづき、教育内容、指導方法、評価の改善を含めた授業のデザインや学習活動のプログラム、それに適した教材開発が求められます。
例えば、次のようなことが求められると考えられます。
❶学びの文脈を創る意味のある問いや課題
「自分が今からどのような内容を(何を)、何のために学ぶのか、学んだ結果何ができるようになるのか」といった目的や意味をつかむことができると学びやすくなる。
問いの「質」を吟味し、学習者のモチベーションを高め、思考を駆動して多様な解が導き出される問いを設定することが重要。
❷子どもから引き出す考えの多様性
学習者は各々自分の考えをもっている。「自分の考えを聞いてほしい」「いろいろな意見が聞けてよかった」と思えるような状況作りが重要。
❸考えを深めるための対話活動の導入
21世紀型能力の基礎力・思考力・実践力すべての根幹にかかわるのが他者との対話・交流による協働的な学習活動。
❹考えるための材料の提供
指導者による明快な説明がむしろ知識の「カプセル化」を招き、次の学習への転移や学校外での実践力につながらないことがある。学習者が「自分事」として思考することによって既有知識が変容・再構成されていく学習過程が重要。
❺学習活動やツールへのすべ・手立ての埋め込み
❻子どもが学びを振り返り、学び方を自覚する機会
❼教室や学校に創る学び合いの文化
21世紀型能力の育成においては、その基本原理からしても他者との対話・協働を担保・促進する学び合いの文化は必須ともいえる。